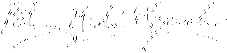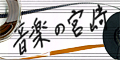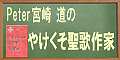長い期間、居間に飾られていた“原住民レコード”
このジャケット…最初に見た時は絶対、アフリカの或る民族の音楽を記録した実況録音盤だと思いました。父は世界の民族音楽のレコードをかなり持っており、アフリカのものも結構あったのです。だからこれもそうかなと。それにしては“T-CONNECTION”と書かれた文字がメタリックで、スペースオペラっぽい。このミスマッチ…なんじゃこのレコードは?子供心に気味が悪く、いつも見ないようにしていました。
実を言いますと、私は恥ずかしながらその当時(小学校5〜6年生頃)、レコードで聞く音楽というものは全て“付随音楽”みたいなものだと思っていたのです。映画、TV番組、ラジオ番組などに付けられた音楽がレコードとして出回っているもので、唯一の例外がクラシックと、サンバ・カーニバルの“実況録音盤”などの文化的資料なのだと信じ込んでいました。時のアイドル歌手や演歌歌手のレコードというものはTV番組「8時だヨ!全員集合」や「見ごろ食べごろ笑いごろ」に出ているから、映画のサウンドトラック盤みたいな感じでレコードが出ているのだという…まさかレコードが先にあって、それを売るためのプロモーション活動として数々の歌手が番組に出ているなどとは思いもよらず、音楽は独立したものだとまるっきり理解してなかったんです。ですから“T-CONNECTION”が同名バンドのレコード(アルバム)なのだという発想など、あり得なかった。だから或る民族の資料的記録盤としか思わなかったんです。激しい思いこみ故の大勘違いなんですがね。
しかし本当に長い間、居間に飾られていたため、15匹もいたネコたちの襲撃を幾度と無く受け、頻繁にマーキングの対象にもなりました。お陰で、20数年前につけられた雄猫のマーキングの跡が黄色く変色し、現在もジャケットにしっかりと残っています…きたないなぁ。
ファンクってなんだ?
父は1970年代半ば以降、ファンク・ミュージックにハマりました。その発端としてハービー・ハンコックの『ヘッドハンターズ』があったことは明白ですが、何より重要なのは御大クィンシー・ジョーンズのファンクへの急速な接近だと言えます。カウント・ベイシー派の宮崎尚志としては、その流れを汲むクインシーが1975年の『メロウ・マッドネス』等で提示してきた音楽に、来るべき80年代への音楽シーンの未来像を見出したのでしょう。そしてその頃にブレイクし始めたアース・ウィンド&ファイアー(EW&F)にハマってしまうワケですが、時代はアメリカを発信源とする一大ディスコ・ブームへと流れていく中、ファンク・ミュージックは確かにディスコ・シーンの最重要且つ強力なファクターとして機能しました。
しかしファンクの歴史は結構古い。ファンクの代名詞といえば“Pファンク”軍団の親分ジョージ・クリントン(パーラメント or ファンカデリック)と言っても良いし、スライ&ザ・ファミリーストーンと言っても良いでしょう。スティーヴィー・ワンダーの「迷信」なんてとってもファンク! もっと古くはジェームズ・ブラウンの「セックス・マシーン」なんてソウル・ナンバーはモロにファンク! カーティス・メイフィールドが手がけたサントラ盤『スーパーフライ』なんか、すっかりファンクっ!!…あ、そういえば『スーパーフライ』はレコード棚にあった!
しかしファンクに共通していたのはブラス&コーラス入り“ビッグ・バンド”サウンドで、どこかアブナいフィーリングに満ちていて、しかもソウル特有の汗臭さ(体臭?)があること。このソウルな臭いがリスナーの好みを分けたと言って間違いはなく、故にかつてのファンクは決してメジャーではありませんでした。しかし1976年にワイルド・ベリーのディスコ・ナンバー「プレイ・ザット・ファンキー・ミュージック(Play That Funky Music)」が全米で大ヒットした辺りから、ファンクはディスコ・ブームの中に確実に取り込まれ、一気にメジャーに浮上します。パーラメントがブレイクしたのもこれと前後してでしたし、アース・ウィンド&ファイアーは“ソウルな臭い”を上手く回避して次第に“ブラック・コンテンポラリー”なるものを形成していきます。“ブラ・コン”は、白人でもとっつきやすいファンク…都会的なファンクと言いましょうか。
そんな中、バハマから登場したのがT-コネクションで、彼らのプレイする音楽はファンクの王道を行きながらソウルな臭いを抑え、極めて大都会的なサウンドに仕上げ、アメリカ本土でもブレイクしたバンドです。ブラック・コンテンポラリーで王道ファンクといった感じかな?
ナッソーでCM音楽録音
父から小中学校の時分に聞いた話で多少間違いがあるかもしれません。記憶しているところでは、資生堂か何かのCMだったと思いますが、バハマのナッソーでロケ撮影から音楽録りまで全てをやるという製作プランが立てられた折り、父は撮影班の一行と共にバハマを訪れました。猛烈な日差しの下で無事に撮影が終わって、音楽録音のため用意されたスタジオに行くとそこは…
|
まるでほっ立て小屋みたいな建物で、中にはクーラーなんかなくて凄く暑く、防音処理もロクにされてなかったので、外をトラックが通る度に録音が中断した。 (宮崎尚志談)
|
確かこのスタジオのオーナー兼エンジニアが、このCM録音のコーディネートをしてくれたような話だったかと記憶しています。当日、現地の若いミュージシャン達がスタジオにやってきた。オーナーは「こいつらはバハマ最高のバンドだ。お前らを満足させるために特別に呼んだんだ」と始まって、ずっと自慢話をしながらアンプやドラムにマイク・セッティングを行っていたそうです。
|
すごくアバウトにマイク立ててるんで、ホントにそれでいいのか? 良い音に録れるのか? と聞いたら、これでいいんだと言う。だから一度だけ音を聞いたらダメ出しして、全部自分の言うとおりにセッティングしなおさせようと待ちかまえていたら、本当にいいサウンドが出てきたから驚いた。けどもっと驚いたのは、スタジオはサウナみたいになっているのに、中のミュージシャン達は涼しい顔で何度でも素晴らしいサウンドでプレイした事、しかも最高の腕を持った連中だったって事だ。
(宮崎尚志談)
|
オーナーは、今プレイしているスタジオ・ミュージシャン達は「“T-コネクション”ってバンド。アメリカでもデビューしている」と更に自慢爆発して、話が止まらなかったそうです。このバンドのサウンドに惚れ込んだ父は…
|
そいつに、彼らのレコードはどこで手に入るのかと聞いたら、街のレコード屋に行けばどこでも売ってるというので、翌日には大急ぎでレコード屋に駆け込んで数枚手に入れて、帰りの飛行機に飛び乗った。日本じゃ聞いたこともないバンドだったから。
(宮崎尚志談)
|
T-コネクションに出会って、父が作るコンボ・サウンドは大きくチェンジしました。明らかにファンキーになり、リズム隊が強調されるようになったのです。更に面白いのは、相当入れ込んでいたハービー・ハンコックもアース・ウィンド&ファイアーも聞き続けるのを辞めてしまいました。T-コネクションの持つ都会的なフィーリングが父の求めるものに合致したのでしょう。NHK教育番組(例えば「なかよしリズム」とか)であろうがレコードであろうがCMであろうが、ダンサブルな音楽にはとことんファンキーさを加味していきました。
「YC-45Dは貴方の国の製品ですヨ!」

このT-コネクションのキーボーディストが弾いていた、見たこともないコンボオルガン形態のヤマハ・エレクトーン出てくるサウンドが、どう聞いてもハモンド・オルガンにしか聞こえないのに驚いて、「これはハモンドではないのか?」 と聞いたら、逆に「何を言ってるんですか、貴方の国のヤマハの製品ですヨ!」と答えられてしまったとか。確かに家にはエレクトーンが1台ありましたが、コンボ・オルガンのスタイルをしたヤマハ・エレクトーンなんか知らない。エレクトーンはエレクトーンの音しか出ないと決め込んでいたところに、目の前にエレクトーンじゃないエレクトーンが…(なんか文章がややこしくなってきたな)。で、父が「いや、ハモンドとしか思えない。改造してあるんじゃないか?」 と更に追求すると、「本当はハモンドが欲しかったのだけど、ツアーに持っていくには難しいから(重量もあり図体もでかい為)、安心して使えるコンボオルガンを探したらコレを見つけた。自分はとても気に入っているんだが、どう思う?」と聞き返される始末。
このオルガンこそ、ヤマハ・コンボオルガンの名機中の名機YC-45Dで、父は帰国してすぐにこれをフルセット(ペダル鍵盤付き本体、プリアンプ、スピーカー)で購入しました。私は茶色のエレクトーンが鎮座していた場所に、突然やってきたゴツくて軽音楽っぽい(!!)ルックスの灰色のオルガンにビックリしたものです。

全く余談で申し訳ありませんが、フルスケール2段鍵盤のYC-45Dには“グライド(グリッサンド)”なる黒いフェルト製のバーがあり(写真上を参照)、指で軽く押すと発音し、特殊効果専用の3段目の鍵盤として使うことができました。オンド・マルトゥノみたい指をウネウネ左右に動かすと、その通りにウネウネとした音程が出る。専用のサウンド・タブレット(音色を選ぶスイッチ)も結構笑えるもので、シンセサイザー風のUFOサウンドがプリセットされていたので、私ら息子たちはこれで思いっきり遊びました。そうそう、YC-45Dと同時にリズムボックスもAceToneの木目調のヤツをやめて、京王技研から社名変更したばかりの“KORG”の黒いヤツ(ドンカマチックではない)に買い換えてたっけ。
T-コネクションを聞く
ジャケットの印象が悪かったせいではありませんが、私はつい先日までT-コネクションを一度も聞いたことがありませんでした。ですから彼らのファンキー・ミュージックについて、父と話しあったことはありません。でもこの機会だから聞いてみようと思い、父がバハマで買ったこのレコードをプレイヤーに乗せてみました。この原稿を書く上で気軽に聞けるようにiPodに入れておこうとも思い、パソコンのレコーディング・ソフトも回しました。買ってから29年も経っているし、父はよく聞いていたので、音溝もガタガタだろう…・しかもネコにマーキングされてるし!
塩化ビニール製のレコード盤を取り出してみる…重いぞ。盤自体の厚さが結構ある。ブルーノートの『クール・ストラッティン』みたいな、ズッシリとした感触。盤面もキレイでピカピカ。カビひとつ生えてない。で、針を落として聞いてみると、まるで真新しいレコードのようでした!信じがたい程に、凄く状態が良くてビックリ。CDで買い直さなくても、これなら十分満足。バハマのレコード(製作元はフロリダ・マイアミみたいだが)って質が良いんだなぁ。同年の映画『サタデー・ナイト・フィーバー』の日本盤サントラなんか、もう音がジャリジャリですよ。父が「レコードは財産だ」 と言っていた意味が分かったような気がしました。良い材質で長持ちするレコード盤は、やっぱり重くて高価なんだ。
で、聞いてみた。演奏時間40分弱のアルバム全体を、バンドは緩み無く一気に聞かせてくれる。間違いなく王道のヒット・アルバムだ、実に良く出来ている。非常に良くプロデュースされていて、アルバムの構成(曲の並び方)が上手い。長すぎず短すぎず、何度でもリプレイしてくれと言わんばかりの充実した内容…・思えばこういうアルバムの作り方って、懐かしいなぁ。全部聞き終えて、もう少し聞きたいから最初から聞き返してみようとする心理誘導。これがヒット・アルバムの醍醐味だと思うんだなぁ。
A面1曲目の「Funkannection」は、まるでPファンクみたいなタイトルだなぁ〜と思ったら、歌もそんな感じだった。あ、歌じゃなく、“ラップ(RAP)”って書いてある。そうか、ラップって70年代からあったんだ、知らなかった。A面はファンクの王道を行っていて、メロディーよりもグルーヴを重視した作り。一方、B面に移るとヒット性の高いディスコ・ファンクのオンパレードで、キャッチーなフレーズを持つ歌メロが増えて聞き易くなる。最後の曲「Love Supreme」はEW&Fの「暗黒への挑戦(That's The Way of The World)」にそっくりなんですがね…。
クリーンなファンク

私は『T-CONNECTION』は一聴して凄く気に入りました。ファンク・ミュージックを聞きたいなぁ…と言っている人が居たら、今後は迷わず、T-コネクションを薦めるでしょう。ファンク特有の臭いが無いし、マリファナやドラッグの影響も感じられず、スピリチュアルな(宗教的なまでの)音楽世界観とは良い意味で乖離した一大メジャーなフィーリングに溢れている故です。そうか、父が彼らの音楽に惚れ込んだのは、そのクリーンなファンキー・テイストなんだな。うむ、その手法は確かに新しかったんだ!
しかし父はこのフィーリングを、そのまま借用することはしませんでした…というより、出来ませんでした。日本に戻ってきて、さぁこのアーバンなファンキー・フィーリングでやりましょう!と言っても、スタジオに来る百戦錬磨の凄腕ミュージシャン達ですら難しかった。だからといってファンクをやってる若手を連れてきても、良い結果にならなかった。故に父は「このセンスはきっと黒人特有のタイム感なんだ。日本で酔っぱらったオッサンがカラオケで“こぶし”をくるくる回しているのを聴いて、外国人がビックリしたってぇ〜のと似ているかもしれないな。」 と言いました。
子供のためのファンキー・ダンス
「ダンシング・エンジェルス」

それで父はすぐにファンキーさを白人化したような(?!)ディスコ・ミュージックへと興味の対象を向けていきました。ところが一番のお気に入りはドナ・サマー(プロデューサーは“ミュンヘン・サウンド”のジョルジオ・モロダー)で、続いてルーファス(チャカ・カーン在籍)、そして父がCMソング録音では定型のフォーマットとなっていた女声3人のコーラス・グループということで、最も参考にしたであろうポインター・シスターズ…。結局のところ、ソウルフルな女声リードボーカル若しくはコーラスを、リズムを強調したディスコ・サウンドがバックを固めるという、全く奇をてらわない(ある意味でミュージカル・ファッションリーダーとしてのCM音楽作家というスタンスから一歩後退したかのような)サウンドの録音を1980年代初頭には少なからず残すことになりました。これらはハッキリいって、あんまり面白くない。
しかしその中でも挑戦的な試みだったのは、小学校の運動会などで使う目的で製作されたダンス教材レコードの1曲「ダンシング・エンジェルス」で、16ビートのディスコ・ナンバーでした。NHKの「ヤンヤンムゥくん」(1973)ではアーバン・ジャズのモダン・ハーモニー感を持ち込んで斬新なサウンドを求めていましたが、その後の教育テレビ「ワン・ツー・ドン」、「なかよしリズム」、「ばくさんのかばん」等では“音楽に貴賤なし”とのNaoshismの信条に基づき、南米のダンスビートをも積極的に取り入れたアンサンブルで物議を醸した程、子供の教育については次から次へと音楽的な刺激を与え、音楽の愉しみを否応なく啓発するというやり方は昔から一貫していました。
「ダンシング・エンジェルス」はファンクの切れ味とディスコ・ミュージックの分かりやすさ、スリリングに強調されたビートの上で、ポインターシスターズが和製アニメになったような女声コーラスが乗って、“ファンクな臭い”は完全に中和されています。SFではなく、どこかにあるかもしれない“街”の匂いがするかのような、独特のシュールなテイストを持ちながら、全くスマートではない着崩れしたようなファンキー・ディスコになりました。丁度、2歳児がまだブカブカの子供服を来てはしゃいでいるような感じ…「ストップ・メイキング・センス」の頃のデヴィッド・バーン(=トーキングヘッズ)ではないぞ…わかんねーよ。一人ボケ・ツッコミ。
都会的なファンクのエッセンスを抽出し、多様な場に適用するという点に於いて、そのアイディアの原点となったのはT-コネクションとの出会いだったように感じます。ナッソーでの思い出は、父の人生にとっては音楽的にワンダフルなものだったせいか、バハマの印象が最高で、何故か春とか秋になると思い出したかのように「バハマは最高だぞ、一度行ってみろ」と繰り返したものです。…うん、そのうち行くよ。