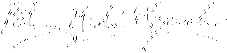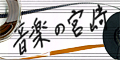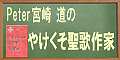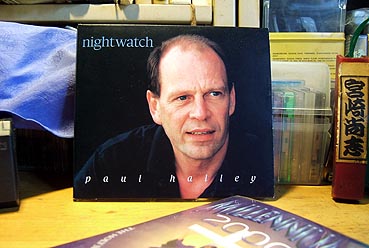
必聴!驚愕のオルガン即興的組曲
ジョン・マクラフリンの『地中海』に続き、再びCDのアルバムです。又、これは“宮崎尚志のレコード棚”にあったものではなく、実は2003年1月に、私がAmazon.com(米国の本店?)から買ったものです。今回は少々趣向を変えて、この『ナイトウォッチ』を取り上げてみます。
ポール・ハーレーという天才的な鍵盤奏者/作曲家/編曲家をご存じでしょうか? 1977年頃からアメリカ・ニューヨークにある聖ヨハネ大聖堂(The Cathedral of St. John The Divine)の首席オルガニスト(いわゆるひとつの“カントル”)に就任、時を同じくして同聖堂の住み込みの音楽家だった名サックス奏者=ポール・ウィンターと出会い、約10年間、行動を共にしています。一般的には、そのポール・ウィンター率いる“ウィンター・コンソート”のピアニストという姿で知られていますが、ウィンター・コンソートの一員だった時代、ある意味ではグループの音楽的リーダーであり(ポール・ウィンターは“スピリチュアルなリーダー”だな)、主要なナンバーのほとんどを作曲しています。1989年に聖ヨハネ大聖堂首席オルガニストの座を退き、コンソートとのパーマネントな活動からも離れた後、盟友ポール・ウィンターもコンソートから離れて、愛用のソプラノサックス一本持って荒野や大峡谷に分け入っては、ソロ・インプロヴィゼーションをレコーディングしたような地味なアルバムを連発。超絶技巧ソリストによる鉄壁のアンサンブルを誇ったウィンター・コンソートでのダイナミックで美しい音楽性は、ポール・ウィンター名義のスタジオ・アルバムではもはや聞けず、故にポール・ハーレーの存在の巨大さが伺い知れます。
ポール・ハーレーのピアノ・プレイを一度でもライヴで聴いたならば、必ずやそのサウンドの虜になります。ジェントルでエモーショナルであり、しかもクールでクラシカルな味わいのジャズ・ピアノ。しかしハーレーの真骨頂は、やはり本業のパイプオルガン。日夜弾き込んでいた聖ヨハネ大聖堂の巨大パイプオルガンを縦横無尽に駆使して、オーケストラに匹敵するサウンドを一人で弾いているのが1982年発表の『ナイトウォッチ』であり、徹底的にオルガンインプロヴィゼーションによる組曲が展開されています。アルバム・コンセプトは日没から日の出まで、即ち「徹夜」?!…そんなアホな。
タイトルの“Nightwatch”は、直訳すると“夜警”とか“夜番”ですが、聖ヨハネ大聖堂には青年伝道の1つとして、大聖堂に泊まり込み、夜を徹して様々な催しを行う“ナイトウォッチ”というプログラムがあり、アルバムのコンセプトはまさにそのことに違いないでしょう。
しかし何がどうであれ、『ナイトウォッチ』はパイプオルガン演奏者にとって必聴の1作であります。ここには最高峰のオルガン・インプロヴィゼーション・ミュージックが収められています。演奏の凄さは言うまでもなく、所々に聖歌を混ぜ込んだ楽曲そのものが非常に良い。どう聴いても譜面に書かれた作品としか思えない、ガッチリと構築された(かのように聞こえる)即興演奏には“隙”が一切ない。しかも録音にはテープ編集でツギハギした痕跡がひとつもなく、完全に無編集の一発録音。大聖堂の巨大なオルガンから繊細なピアニッシモ、更にステレオのスピーカーがブっ飛ぶようなフォルッシモまで引き出し、モダンなオルガンを使い切った壮絶なサウンドを聴かせてくれます。

そもそもポール・ハーレーは米国聖公会に属する聖ヨハネ大聖堂の首席オルガニストであり、礼拝に於ける教会オルガニストは聖歌等の旋律を用い、豊かな和声、対位法、高い演奏技術を縦横無尽に駆使し、多彩なインプロヴィゼーションを行います。毎週のようにそんなことやってるんですから、教会オルガニストは卓越したインプロヴァイザーであるべきとも言え、その精神はJ.S.バッハ以前の時代からずっと受け継がれてきたものです。
宮崎尚志、最期の愛聴盤
湿っぽい話をするつもりは毛頭ありませんが、これは父にとって生涯最期の愛聴盤であり、癌治療のため入院した病院のベッドで、宮崎尚志は深夜にこのアルバムをヘッドフォンで聴き、頬に涙したのであります。
|
ポール・ハーレー、もう最高だよ。夕べ聞いて、感動して泣いちゃった。NYのセント・ジョン(聖ヨハネ大聖堂)の礼拝で聴いて、震えて立ち上がれないぐらい感動した、正にあのオルガン(の演奏)だよ。あの感動が甦ってきた!これ聴いて確信したんだけどさ、セント・ジョンでボクを感動に打ち震えさせたスゲーオルガンを弾いてたのって間違いない、コイツだよ、ポール・ハーレーだよ。
宮崎尚志・談
|

そもそも私らがポール・ハーレーというキーボード・ヴィルトゥオーゾを知ったのは、父が1984年頃に単身でアメリカに出かけ、NYの聖ヨハネ大聖堂での主日礼拝に参加した折、教会の売店で売っていた数あるレコードの中から、ポール・ウィンターの2枚組アルバム『ミサ・ガイア(Missa Gaia/Earth Mass)』を買って帰ってきた時です。NY聖ヨハネ大聖堂は400年後に完成すれば世界最大のゴシック建築となるだけでなく、非常にリベラルな方針を持ったキリスト教会だそうで、1981年以来、10月4日の“アッシジのフランシス日”に毎年行われる大ミサ「ミサ・ガイア(地球ミサ)」は、大聖堂に大型・小型の動物、鳥、爬虫類などが入ってきて司祭陣から祝福を受ける、さながら“ノアの箱舟”のような光景が展開することで、世界的にもよく知られていました。この音楽を手がけたのがポール・ウィンター・コンソートであり、ピアノ&オルガンで大活躍していたのがポール・ハーレーでした。
ニューヨークにて
父は単身アメリカに何をしに行ったかは、母も知らないほどハッキリしていません。昔から世界各国に一人でフラリと何週間も出かけてしまうような人でしたが、意外にもニューヨークを訪れるのはその時が初めて。北アメリカ各地を回り、最後に来たのはNYブロードウェイだったようです。ガーシュウィンに憧れ、ニューヨークへの強い思いを抱いていた父としては、ブロードウェイに乗るミュージカル作品を書くことが積年の夢でした。ミュージカルの本場でその下調べをしに行ったものだと、私ら息子達は思っていたものです。が、日本へ帰ってくるなり…
|
ホントは、日曜の午前中にハーレムの入口にあるセント・ジョンの礼拝に出てから、午後は『ママ、アイ・ウォント・トゥ・シング』を観る予定だったのに、教会のオルガン奏楽のあまりの素晴らしさで全身の力が抜けちゃってね、礼拝終わっても腰抜かして立ち上がれなくなっちゃったんだ。でっかい聖堂の空気が、ぶっといブルドン(低音管のこと)で震えるんだぜ。午後に『ママ…』を観に行く気力がなくなっちゃったから、そのままホテルに帰っちゃった。その日の凄いオルガニストのお陰で、ブロードウェイがトンじゃったのさ! (宮崎尚志・談)
|

父のレコード棚には『聖なるヘアー/ミサ曲ヘ長調(Divine Hair - Mass in F)』という、1971年のライヴ・アルバムがありました。これはNY聖ヨハネ大聖堂で、オフ・ブロードウェイで大ヒットを飛ばしていたロック・ミュージカル『ヘアー』の作曲家ギャルト・マクダーモットが書き下ろした「ミサ曲ヘ長調」を用い、聖ヨハネ大聖堂がモダンなイーブンソングを行った、いわば一夜限りの“企画礼拝”のライヴ録音で、『ヘアー』のキャストが総出演し、アンセム等に『ヘアー』のナンバーを用いるという、それはそれは画期的でフラワーな(?!)礼拝の記録でした。世界最大級のゴシック建築となる大聖堂でロックバンドが礼拝奏楽をするというのは当時、世界の聖公会では大変ユニークなものだったようです。この礼拝中、当時の大聖堂のオルガニストが「アクエリアス」の旋律を用い、パイプが唸りを上げる壮絶な即興演奏を展開する場面があり、そのサウンドは伝統的なパイプオルガンの範疇を越え、シンセサイザーのようでした。故に、父は昔から聖ヨハネ大聖堂について、少しばかりのインプットがあったと言えます。
その大聖堂で聞いた大オルガン。それは確かに、無数のパイプ+電子楽器(アーレン社製)の組み合わせによって、聖堂の床を振動させ、空気全体を振るわせるハイブリッド・オルガンだったようです。アメリカでは昔から多いオルガン・スタイル(シアターオルガンの開発で培った技術を応用した)だと父は言っていました。しかし『ナイトウォッチ』で聞けるレスポンスの速い、歯切れの良いタッチ、それを効果的に響かせるストップ(音詮)の選び方は、ポール・ハーレーの演奏技術の高さとサウンド・センスの良さ他なりません。パイプオルガン演奏独特の、和音の塊がドロドロと流れているような瞬間がひとつもないのは奇跡的です。
ウィンター・コンソート at サントリーホール
父がNYから帰国して1年後ぐらいでしたか、ポール・ウィンターがコンソートを率いて来日公演を行うという情報をキャッチしました。コンソートとしては初来日でした。ただ、“コンソート”(Consort=運命共同体の意)という言葉が珍しかったのか、チケットを見たら公演アーティスト名が“ポール・ウィンター・コンサート”になっていて笑えたものです。
丁度その頃、ポール・ウィンターは大作『キャニオン』を発表し、その製作の過程を追ったドキュメンタリー・フィルムが作られ、アルバムはグラミー賞ノミネートされるなど、話題の多かった頃で、日本ではウィンダム・ヒル・レーベルがディストリビュートしてアルバムのほとんどが日本発売されていました。アメリカ大使館が共催するそのコンサートは、サントリーホールで行われました。早速、私の兄が父と相談してチケットを取り、一家全員で聴きに行ったものです。確かポール・ウィンター(sop.sax)、ポール・ハーレー(pf,org)、ユージン・フリーゼン(vc)、ロンダ・ラーソン(fl)、テッド・ムーア(perc)に加えて、もう一人のパーカッショニスト(グレン・ヴェレツではなかった)の総勢6名のコンソートでの演奏は、ラフな顔していながら鉄壁のアンサンブルを組み上げ、室内楽的な編成ながら、それを軽く凌駕するダイナミックなサウンドを聞かせました。そのアンサンブルの中核を担っていたのは明らかにポール・ハーレーのピアノ。更にメンバー各人のソロ・パフォーマンスもあり、コンソートは超一流のソリスト集団だという事を強く印象づけましたが、やはり最強だったのはサントリー・ホールの大オルガン(ステージ用のコンソールで弾いた)をフル・ボリュームで唸らせて、荘厳且つ鮮やかなインプロヴィゼーションを披露したポール・ハーレー。私は文字通り、釘付けになりました。サントリーホールのオルガンって、こんなに鳴るモンなんだ…。こんな天才的な音楽家が、なんで日本では無名に等しいのだろうか?それって間違ってないか?
しかし父は言いました。
|
アメリカには、無名だけどムチャクチャ上手いヤツがいっぱいいるんだよ。日本よりずっと人口が多いからさ。 (宮崎尚志・談)
|
…しかしポール・ハーレーはムチャクチャ上手いっていう以上に、こりゃ天才だよ! ところが父は、
|
でもセント・ジョンで聞いた、身震いするオルガンを弾いていたヤツの方が、コイツよりずっと凄かったよ。 (宮崎尚志・談)
|
この時はまだ、父は聖ヨハネ大聖堂で聞いたオルガンが、ポール・ハーレーのプレイだったワケがない、と思っていたんですね。
実は私は、このコンサートでの体験が忘れられず、それから数年間に渡って、ウィンター・コンソートの来日公演には必ず足を運びました。2度目の来日となった人見記念講堂でのコンサートでは、ポール・ハーレーが自身の1stソロ・アルバム『ピアノソング(pianosong)』から「賛歌(Anthem)」を演奏(ユージン・フリーゼンがチェロを置き、オルガンを弾いてサポートに入った)した時は、それに合わせて思わず祈ったものです。
祈りを奏でる事は、命を奏でること
1980年代から“賞男”となったポール・ウィンターの、代表的なナンバーを作曲したポール・ハーレーは、(私が思うに)作曲家としても群を抜いて素晴らしい。その音楽には必ず“祈り”があります。祈りを言葉ではなく、楽音で奏でる音楽家であります。彼の祈りは決して個人的なものではなく、「共に祈る」姿勢が貫かれており、故にその音楽は非常にオープンなセンスを発揮し、私たち聴き手はそれに「共鳴」する。この関係性をハーレーの音楽と演奏は、我々にさりげなく求めてきます。それは音楽の最も素敵な在り方だと思いますし、実にジャズの国=アメリカらしいロジックだとも思います。この辺も、宮崎尚志のツボにハマった要因だと考えられます。
“祈り”の音楽だからといって、決して“宗教曲”を指すものではありません。歴史に名を残す作曲家陣の多くが書いた「レクイエム」とか「ミサ曲」とか、「テ・デウム」などは、宮崎尚志にとっては、あまり興味がなかったようです。とはいっても20世紀の礼拝に於ける、新しい教会音楽の在り方を秘かに模索していたのか、そういった動きが海外で見られると、生涯に渡って非常に敏感に反応しました。例えば…
|
エレクトリック・プルーンズ:『ミサ曲ヘ長調(Mass in F)』 これは古いですね。でも名盤です。腕の立つGSバンドが、意外と伝統的な精神性で書かれたミサ曲を演っている、時代的にとってもサイケデリックな匂いのするレコードです。 |
|
ギャルト・マクダーモット:『聖なるヘアー』 先述の通り。 |
|
グスタフ・ブロン・オーケストラ:『ミサ・ジャズ』 個人的にとても気に入ってます。ビッグバンドがスウィングしながら祈ります。 |
|
レナード・バーンスタイン:『ミサ 〜 歌い手、演奏家、舞踊家のためのシアターピース』 バーンスタインがケネディー・センターのこけら落としに書き下ろした強力な作品で、父はいつも「バーンスタインのミサは面白いだろう、滅茶苦茶おかしいだろう?」と、ケタケタ笑っていたものです。 |
|
ヴァンゲリス:『天国と地獄』 父は大絶賛。宗教曲ではないのに、深い祈りの教会音楽だと言い張った!コンテンポラリーな教会音楽の方向性を感じたらしい。 |
|
アンドリュー・ロイド・ウェバー:『レクイエム』 コンサート・ビデオも買って結構入れ込んでいたが、大好きだったサラ・ブライトマンを観たかっただけかも。 |
|
ポール・ウィンター:『ミサ・ガイア』 先述の通り。 |
|
アリエス・ラミレス:『ミサ・クリオラ』 これも大絶賛。 |
宮崎尚志が多摩美術大学等で行った講義では、“祈りは命”であるとの考えを度々明言しています。故に“祈りを奏でる”ことは“命を奏でる”ことであり、それは即ち、(例えば神に)生かされている喜びや感謝を表すことであります。作る者、奏でる者の、その命の輝きこそが、作品を崇高な芸術へと昇華させるのです(勿論、これは芸術全般に言えることで、こうした謙遜の姿勢がオープンな空気を取り入れ、単なる陶酔や自己満足からの脱却を促します)。まず何を語るのか、それをどのように表現するか、そのためにはどのようなテクニックが必要か、といった作品創作の順次プロセスの一番最初と最後に“祈り”がなければ、どのような芸術も無に等しいとした宮崎尚志流芸術論は、何とポール・ハーレーの『ナイトウォッチ』にはパーフェクトに具現化されているのだそうですよ。興味を持たれたら、是非ご一聴あれ。