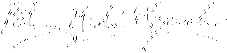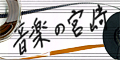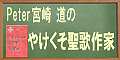説明不要!
アーバン・ジャズの名盤
ジャズ・ファンには説明不要の歴史的名盤。タイトル通りの“クールに気取った”カバーアートも秀逸な1枚。本当に説明不要な1枚なので、気になったらすぐに買って聞く…ジャズ好きなら絶対損しない。ジャズ嫌いなら“ジャズの歴史的名盤”を1枚ぐらい持っていても損はない?!
さて、このアルバムはレコード棚の一番良いところに常に入っていました。丁度カウントベイシー等、ビッグバンドジャズの素晴らしいアルバムが入っていたのと同じところです。父はこのアルバムを非常に大事にしており、聞いてみろとは言うモノの「カセットにダビングしたヤツを貸してやる!」と、レコードから直接聞くことを良しとしませんでした。思い出も詰まった特別な盤だったのでしょう。実際に手にとってみると分厚いレコード盤で妙に重い…明らかに米国輸入盤です。ブルーノート・レーベルはその昔日本盤がなかったらしく、輸入盤は今とは比べモノにならないほど高価だったとか…それも要因だったのかな?
実は私がこれを聞いたのはつい最近になってからです。父亡き後、無数に残されたレコードは“音楽の資産”として、友人から貰ったレコードプレイヤーで聞きまくっております。その時、手を付けずにいたこのレコードに初めて針を落として聞いたのです…聞いて初めて、あぁ〜、この音楽かっ!と驚いた。耳にしたことなら何度もあったからです。盤の状態はかなり良く、昔のレコードは塩化ビニールの質が良いなぁ〜…などと思ったりします。
私はかつて、父に「このレコードはどんなジャズ・アルバムなのか?」と聞いたところ、明確な答えがまるっきり返ってこなかったものです。とにかく「ジャズの歴史が変わった1枚」とか「クールってのを絵に描いたようなもの」だとしか言わないのです。確かに聞いてみれば何が凄くて大ヒットしたのかを表現するに形容しがたいアルバムですが、今で言えばいわゆる“ジャズ”の定番のサウンドであり、明らかに泥臭さを廃したアーバン・ジャズを形作ったことが重要な1枚のようです。
アートとしてのレコード
父=宮崎尚志は音そのものを語るよりジャケットのカバーアートを常に話題にしました。「このジャケット、この写真!素晴らしいなんてモンじゃないよコレは。この足下の写真1枚でニューヨークの空気を感じるんだよ。世界中にどこにもなかったアメリカの大都会さ!」と始まったかと思えば、「ジャケット見ながらレコードかけると、写真そのまんまの雰囲気のジャズが出てくるんだからたまんないよ!」と鼻息粗く語りました。で、このレコードを聞いてみたいなと言うと「ダビングしたカセットテープを貸してやる!」になってしまうんです…それだけは勘弁してよ、レコードから聞きたいんだからさ。
このレコードの話の最後には必ず、父は「ジャケットの写真とレコードの音楽が相互作用で高め合うレコード芸術の最初の1作」と言いました。1960〜70年代のロックのアルバムが目指した、レコードという媒体全てを利用したアートの先駆けであるというわけです。実際、このジャケットの写真は誰の目にもモダン(今やクラシック・モダンですが)であり、卓越した芸術的センスに支えられたものであり、アルバム・タイトルを脳裏に鮮明に印象づけます。Cool Struttin'の文字の“踊り方”も斜に構えたようなユーモアに溢れています。このジャケットから想像する音楽とは…聞いたことのないあなたなら、どんなサウンドを思い描きます?
音楽家は音楽で語るべき
 このアルバム、ブルーノートの盤なのに主役のソニー・クラーク(pf)の写真がジャケットにない。ジャケ裏にもない。よく知らない私にしてみれば“古いジャズのレコード”には必ず演奏者・歌唱者の写真がジャケットであるか、若しくは裏ジャケ、内ジャケのどこかにあるはずだと思い込んでいましたから、ソニー・クラークってどういう人なんじゃ?と困惑しました。
このアルバム、ブルーノートの盤なのに主役のソニー・クラーク(pf)の写真がジャケットにない。ジャケ裏にもない。よく知らない私にしてみれば“古いジャズのレコード”には必ず演奏者・歌唱者の写真がジャケットであるか、若しくは裏ジャケ、内ジャケのどこかにあるはずだと思い込んでいましたから、ソニー・クラークってどういう人なんじゃ?と困惑しました。
ところが父はこう言いました。
本来、音楽家は音楽で表現するんだし、小説家は文章を綴って表現するだろう? 落語家は喋りで、ダンサーは踊りで、役者は全身で演技することで表現するワケだし、演出家はみんなをうまく動かして一つの世界を描くことで自らの芸術を表現するんだ。
例えば文章では表現できないことがあるからといって 小説家がTVに出て勝手に喋りはじめたらどうだろう? んでもって、その喋りが「凄く上手い」って思われたらどうだろう? その人の仕事が増えて、小説ももっと売れるかもしれないけど、一般的には“ゲストコメンテーター”の人であって、小説家じゃなくなる。
小説家の本分は新しい言葉の表現を追求して、自分の内にあるモノを表現していく事にある。 今ある言葉を適当に並べてドラマを作る程度なら、小説家じゃなくって“作文作者”だ。
強い意識のない芸術なんてあり得ないんだ。音楽家にだって同じことさ。 演奏している人の写真がレコードにないからといって、聞く前に中身をどうこう言うことない。 なんならただ聞いてみればいいんだから。 その音楽家の言いたいことや生き方、価値観とか諸々は音楽になってレコードに入ってるモンだ。 名盤って言われてるレコードは、みんなそうなんだよ。だから名盤なんだ。
けどそれが理解できないっていうんなら、別に難しいことなんかない、 気に入らないってことで、途中で聞くのをやめれば良いだけの話さ!
「遙かなる憧れ・ギロチン恋の旅」にみるクール
 『Cool Struttin'』が様々な音楽家に大きな影響を与えたことは想像に難くないものの、作曲家=宮崎尚志にも多大な影響を与えています。その最たる作品が大林宣彦監督の1969年の自主映画『Confession〜遙かなる憧れ・ギロチン恋の旅』で、そのサウンドトラックにそれが強く感じ取れます。この映画は全体的なテーマと大まかなプロットだけを決め、映像と音楽が同時進行で全く別個に作られた異色作で、既に完成している映像に対して書かれたサウンドトラックではないので“映画音楽”とは到底思えない、極めて自由な音楽が展開されており、さながら室内楽にバップ・ピアノとモード・サックスが乱入するかのような刺激的なものです。
『Cool Struttin'』が様々な音楽家に大きな影響を与えたことは想像に難くないものの、作曲家=宮崎尚志にも多大な影響を与えています。その最たる作品が大林宣彦監督の1969年の自主映画『Confession〜遙かなる憧れ・ギロチン恋の旅』で、そのサウンドトラックにそれが強く感じ取れます。この映画は全体的なテーマと大まかなプロットだけを決め、映像と音楽が同時進行で全く別個に作られた異色作で、既に完成している映像に対して書かれたサウンドトラックではないので“映画音楽”とは到底思えない、極めて自由な音楽が展開されており、さながら室内楽にバップ・ピアノとモード・サックスが乱入するかのような刺激的なものです。
この音楽でのジャズ・サウンドは何故か『Cool Struttin'』を彷彿とさせます。興味深いのは『ギロチン』の前作『EMOTION〜伝説の午後・いつかみたドラキュラ』(こちらも音楽は宮崎尚志)で聞かせる音楽は似たような編成でありながら、狙っているサウンドはまるっきり違う点です。『ドラキュラ』がグランドピアノや竹の風琴を深いエコーでブっ飛ばしたり、ヨーロッパの前衛音楽の(一見アヴァンギャルドな)エッセンスをふんだんに含んだ具体的幻想性を打ち出している反面、『ギロチン』はもっぱら楽器演奏によってモダンでクールな恋愛幻想を表現しているのです。ただし『Cool Struttin'』の発表から11年も経っての『ギロチン』だけに、当然音楽はより様々なスタイルが絡み合う過剰にホットなものになっていることは事実です。
室内楽(クラシカルな要素)とジャズといえばデイヴ・ブルーベック・カルテット(「テイク・ファイヴ」というよりは「トルコ風ブルーロンド」を…)を思い出してもいいものを、『ギロチン』から『Cool Struttin'』を強く連想させるのが興味深いところです。察するに宮崎尚志は“青春と恋”がテーマの『ギロチン』に於いて自ら人生の足取りを振り返った音楽を作ったのでしょう。幼少時代に暮らしていた北海道での思い出、東京での学生生活、“音楽に垣根はない”と痛烈に教えられたガーシュウィンの「ラプソディー・イン・ブルー」、そしてジャズ…そしてサントラの中に於いて最も躍動的な部分に全てアーバンなジャズを用いており、そこに家庭を持つ以前(1950年代/青春)の自分自身を投影したとすれば『Cool Struttin'』の面影があるのは十分に納得できることです。
CD化されたクール・ストラッティン
私はこのレコードが気に入ったので、最近ではパソコンで録音してiPodに入れ込んで頻繁に聞いていました。古いレコードにツキモノのスクラッチ・ノイズ(針ノイズ等)がかなり入りますが、スタジオのアンビエンス(室内の響き)を生かした録音と、どこかくぐもった音色が耳に心地よいので、ついつい聞いてしまいます。
ですが、つい先日、CD化されているこのアルバムを手に入れて聞いてみたところ、音質がメチャクチャ良いのにビックリ! デジタル・リマスターされているらしく各楽器が鮮明に聞こえる上、意外なほどオンマイク(楽器に凄く近い位置にマイクを立てて録音すること)で録音されていて、レコードで聞けるスタジオのアンビエンスなんかほとんどない! 印象がまるっきり変わってしまいました。CD化されているこのアルバムには宮崎尚志の『ギロチン』に相通ずるサウンドが希薄なのです。
しかしCD『クール・ストラッティン』を聞き込むと面白い。パンチがあって艶のあるブラスの音がしている。聞いていて気分がいい。いわゆる“ゴキゲン”な音です。こんな音を作るのは一体誰だ?…ジャケットを見てみると、やっぱりエンジニアはルディー・ヴァン・ゲルダー…レコード原盤のカッティングにまで手を出した、こだわりのエンジニアだ。なるほど、そういうことだったのか。生前にこのリマスターCD化された『クール・ストラッティン』を父に聞かせときゃよかったな…青春の恋の記憶はリマスターされないけど。