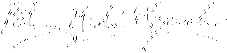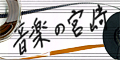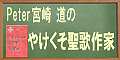Powerd by
sogaku.com
宮崎尚志のレコード棚
ドン・エリス・オーケストラ
『モントレーのドンエリス〜ビッグバンドによる前衛的な実験』
Don Ellis Orchestra: "Live" at Monterey! (1966)

驚愕の変拍子スウィング・ビッグバンド・ジャズ
ジャズ・トランペッター=ドン・エリス率いるビッグバンドの1966年モントレー・ジャズ・フェスでのライヴ盤であり、デビュー盤です。ドン・エリスの名は映画音楽ファンならばウィリアム・フリードキン監督の1971年の名作『フレンチ・コネクション』(ジーン・ハックマンが主演でしたっけ)の音楽を担当したモダン・ビッグバンドジャズの大御所として覚えているかもしれません。
そのドン・エリスが、ジャズに於ける新たなリズム探求欲とガッチリと構築されたビッグバンドサウンドの融合を実現する目的で、プロ&アマチュアで組織したリハーサルバンドが“ドン・エリス・オーケストラ”です。このアルバムでは通常のビッグバンドの編成に加えてドラマー3人、ベーシストが3人と、前代未聞のおかしな編成になっています。しかもその音楽は徹底した変拍子スウィング・ジャズなのですっ! 正に世界が驚いた、驚愕のビッグバンドジャズの誕生を聞くことが出来ます。ドン・エリスの登場した時代は、正に白人ジャズがシリアスなコンポジションを超絶技巧で実現するといった緊張感を伴ってきており、何となくフォア・フレッシュメンが登場した頃とは世のムードが全然違ったようです。
父が所有しているこのレコードは赤い塩化ビニール盤で(そういえばピンクフロイドの『原子心母』もそうでした)、現在CD化されているものよりも収録曲数は少ないので、これから聞くなら絶対CDだな! 実はまだ買い直してないの。
東欧民族舞踊には奇数拍子(5拍子とか7拍子とか奇数拍で一巡するリズム)が数多くあり、それで現地の人々が、子供も含めていともたやすく一斉に踊るという事実を知った事が大きな刺激になって、ドン・エリスの執拗なまでの変拍子ビッグバンドジャズへの追求が始まったと言われています。変拍子で如何にナチュラルにスウィングするか…、これがドン・エリスの基本姿勢です。
1,2,3 - 1,2,3 - 1,2 - 1,2 - 1,2 - 1 - 1,2 - 1,2 - 1,2
私は小学生で洋楽(西洋ポップス)に接して、中学の頃には英国のプログレッシヴ・ロックを聞き親しんでいました。別項でも紹介したキング・クリムゾン然り、ピンク・フロイド然り、イエス(yes)然り、エマーソン・レイク&パーマー(ELP)然り、とにかく“複雑な曲を上手い演奏で聞かせる熱いロック”に夢中になったワケです。レコードを買ってくると、居間のステレオセットでジャンジャカ聞きました…勿論、父がスタジオや打ち合わせで出かけていて居ない時を見計らってのことです。仕事中にジャンジャカやったら、途端に「うるさい!」とお叱りを受けたものですから。
家に誰もいなかった夕暮れ時、私は一人で学校帰りに買ってきたばかりのELPをデカい音で聞き始めた時、たまたま父が早々帰ってきて、その音を耳にしたんですね。たまたま変拍子の曲が流れていたんです・・・『タルカス』だったかな。背広姿の父は珍しく興味を示し、こんなやりとりをしました。
|
尚志: 「なんだこりゃ? 何聞いてんだい?」 道 : 「これ?今日買ってきたレコード。ELPだよ。」 尚志: 「エマーソンレイクにこんなのあったっけ?」 道 : 「ウチにないから買ってきたんだってば。」 尚志: 「へぇー、道は変拍子でも平気なのか?」 道 : 「変拍子って面白いね、拍子の取り方はすぐに判るようになったよ。」 尚志: 「…これは5/4(5拍子)だな…ジャズではこんな拍割りはあんまりないなぁ…」 道 : 「2/4 + 3/8 + 3/8で、10/8になるんじゃない?」 尚志: 「ははぁー、そうかもしれないけど、演奏している連中はみんな5/4を勝手に割ってアンサンブルしてるように聞こえるなぁ。」 |
…とまぁ、要するに珍しく、私がレコードを聞いていても「これから仕事するから静かにしろ」とか「テレビ見たいからステレオ消せ」とは言わなかったのです。
その日の夕食時、父がいきなり「変拍子が好きなら絶好のレコードがあそこにあるんだ」と言って、ドン・エリスの名を挙げました。聞いたこともない名前だぞ?誰だそりゃ?
| ワンツースリーワンツースリー、ワンツーワンツーワンツー、ワン、ワンツーワンツーワンツーってカウントするそのまんまの名前の曲をやってんだけど、それが19拍子なんだ。19拍子なんて聞いたことないだろう? しかも変態的な変拍子なのに、これがゴキゲンにスウィングするんだ。複合リズムの勉強にもなるから聞くと良いよ。 |
父は笑顔でそう言ったので、カウントの和を数えてみると確かに19拍。面白そうなので早速、ご自慢の“レコード棚”から出してもらいました。まず、オープニングの曲名を見てビックリ。確かにタイトルに「33 222 1 222」と数字が書いてある! これは明らかにヘンだ! そうかと思えば「パッサカリアとフーガ」や「コンチェルト・フォー・トランペット」といったクラシカルなタイトルも見える…これは一体どんな音楽が詰まったレコードなんだ?
こ、これはっ! 確かにスゴい。
このアルバムで私が今でも特に気に入ったナンバーは「33 222 1 222」(ドン・エリス作)と「パッサカリアとフーガ(ハンク・レヴィ作)の2曲のオリジナル。何をさしおいても楽曲が素晴らしい。ビッグバンド・ジャズの醍醐味を十分に聞かせつつ、対位法で組み上げられたクラシカルな要素が強く表れた楽曲であり、正にバンマス=ドン・エリスの美意識が表れています。
通常拍子で演奏できないリハーサル・バンド?

ドン・エリスはそれまでの常識の通用しない複雑なリズム構成(といってもエリス本人はプリミティヴなエッセンスをジャズに混ぜ込んだと考えている)を一糸乱れぬコンビネーションで演奏するため、ジャズの一流どころも含めた根気強いオーディションを行いながらメンバーを選りすぐって楽団を組織したとのこと。しかしある決まったリズムを細分化してスウィング・ジャズにするという行為は常人には出来かねることである故、この楽団に長期間身を置いていると逆に4ビートが演奏できなくなるとかで、メンバー固定の楽団というより、メンバー流動的なリハーサルバンドという形態でスタートしたとか・・・・ホントか?!
変拍子ジャズはデイヴ・ブルーベックの「テイク・ファイヴ」、「ロンド風ブルーロンド(Rondo a la Turk)」で既に実践されているし、この人達は4ビートの名手でもあるじゃないか。どうしてだろう? まぁいいや。
更にレコード棚を漁ってみたら、ドン・エリスのレコードは意外にも『驚異のビッグバンド(Live In 3 2/3 4 Time)』、『エレクトリック・バス』、『Don Ellis at Fillmore』と数点ありました。しかしながら当時の私の耳ではロックに接近していった感の強い『・・・at Fillmore』はダントツに良かったものの、この『モントレーのドン・エリス』を越えるものではありませんでした。後に聞いた『驚異のビッグバンド』は内容的には全てを凌駕するライヴアルバムだと感じましたが・・・。
父のレコード棚には“モダンジャズの歴史”みたいな黒いボックスセットが1つ入っていて、1930年代ジャズからマイルス・デイヴィス/ジョン・コルトレーン辺りまでの録音が詰まったものがありました。とはいってもマイルスのアルバムは1枚もなかったし、コルトレーンですら1枚しかなかった。その代わりヘッドハンターズ〜V.S.O.P時代のハービー・ハンコックは全て揃っていたんですがね。
アメリカン・ジャズの歴史に於いて1960〜70年代にかけてシーンを大転換させたトランペッターといえばマイルス・デイヴィスと言う他ないでしょう。決してドン・エリスやフレディー・ハバードじゃないんです。時代の最先端を知り、オリジナリティーを追求し、その先にあるものを掴んでいち早く実現していくのが宮崎尚志流、即ちNaoshismな方法論(特にCM業界はそれが出来得る土壌だった)なのですが、マイルスはどうした? 『ビッチェズ・ブリュー』は、『イン・ア・サイレント・ウェイ』がウチにないのは何故だ?
Naoshismとドン・エリスの比較
〜或る暴れん坊トランペッターの話
宮崎尚志はスタジオやステージで曲を演奏する際、どんな編成であってもトップ・トランペットに必ず指名する或るスタジオ・プレイヤーさんがいました。そのプレイヤーさんは非常にプライドが高く気難しい人として知られ、録音する音楽が気に入らなかったりメンバーとの相性が悪いと、録音中でも怒ってスタジオを出ていってしまうほどだったそうです。譜面の初見も利くしサウンドは最高だし演奏も超一級品なので、上手くいけば仕事は速くて確実ですが、常に一触即発の暴れん坊だったとか。そんなアブナいトランペッターが宮崎尚志と妙にウマがあったというのは興味深いのですが、両者が終生互いにリスペクトし合い、音楽での意志疎通が可能なまでに高め合いました。そのサウンド/センスに惚れ込み、熱い信頼を置いていた作曲家=宮崎尚志のトランペットという楽器に対するイメージは、暴れん坊トランペッターの“生き方”に共鳴した結果でした。

───暴れん坊トランペッターさんは回想します。─── 「オレのスタイル? 古い古い…バップなんかよりずっと前だよ。どれかっていえばデキシーよ。(ディジー)ガレスピー? それより古いんで、スタイルなんていってもね…それでも若い頃はモダーンなのをやってみたもんだよ、イキがってね。スタジオなんかやりはじめたら作家とか製作の要求に応えなくちゃならないから、色んなの聞きかじってみたからね、“それっぽい感じ”は出来たんだよ、一応ね。」 ───何故ガレスピー以前にまで遡ったプレイ・スタイルを行ってきたのだろう?─── 日本のモダーンなのは全部モノマネ…モノマネにもなってない、それ以下だったんだよ。昔ね、アメリカで新しい演奏の形が広まって、それが日本にも来た時にね、そういうプレイする若い日本人が何人か出てきたの。今じゃ、みんな大物って言われてるけどさ。で、聞きに行ってみたら、そいつらアドリブできねーでやんの! ビックリしちゃってさー! どういう事か、アンタ判る? 今日演奏した曲のアドリブの部分と、次の日に別の場所で同じ曲のアドリブが、全く同じ音符なの。書いてある譜面みたいに同じ事やってやんの、自動演奏じゃねーだろーにって。おいおい、そりゃージャズじゃねーだろー!て思ったんだけどさ、これがウケちゃうようじゃ日本でジャズやってんのもバカバカしくなっちゃってさ。コイツら全然大したことねーや、やっぱりオレが日本一だとか思ったりしたんだよ、何しろイキがってたからね! ───マイルス・デイヴィスなんかどういう印象なんだろう?─── マイルスが流行った時にさ、丁度アメリカに行ってたから聞いたんだよ。1ドル360円の時代だけど5ドルか10ドルとか、そこら中で気軽に誰でも聞けたのよ、やってんのがクラブみたいなトコだからさ。どんな凄い音で、凄い演奏すンのかと思ったらさ、大して離れてないオレんトコに全然聞こえねーの。なんだあのトランペットは?って思ったの。なーんであんなに小さい音なんだろう?って。でもそんなトランペットがもてはやされてさ、日本じゃ1500万円も積んでマイルス呼んでコンサートやらせてさ。向こうじゃ1500円程度で普通に聞けた演奏をバカ高いギャラで呼んでだよ、しかも音聞こえねーし、クスリ漬けでワケわかんなくなってるようなヤツにカネ積んで拝むみたいなことしてさ。そんで高い入場料とって“見せモノ”にしようってんだからね。そん時、オレはもう全部辞めちゃえって思ったの。 |
その結果、暴れん坊トランペッターさんはデキシーに行き着いたのだと言います。ジャズ・アンサンブルの形態の中でも最も自由で明るく、アメリカン・ビッグバンドの基本とも言えるデキシーランド・ジャズは、ある意味で1960〜1970年代のジャズ・シーンの激流の中にあって時代の流れ等と全く関係なく存在していた数少ない場です。そこでトランペット固有のブライトな音色を響かせられ、しかも(時代の潮流とは関係ない場で)自分の中にある音楽心を表現することを主として生きてきた、とおっしゃいました。本当の音楽とはスタイルとか流行りによるものにはなく、プレイヤー本人の音楽心(歌心のセンスを磨くこと)と、その音楽心による演奏家同士や聴衆との“対話”にある、というワケです。
その生き方、トランペットという楽器で純粋に演奏を楽しむポリシーがそのまま音になっていた事で、そのサウンドにゾッコン惚れ込んだ宮崎尚志だからこそマイルスではなく、ドン・エリスを好んで聞いたことが理解出来たような気がしました。まず、ドン・エリスのトランペットにはデキシーの影響が強く感じられます。又、アメリカン・ジャズの伝統技法に則していながら1960年代末の若者らしいインド音楽のエッセンスをまぶして独特のサイケデリック・テイストを醸し出すという方向性は、古風でありながらも西洋音楽的な構築方法としては堅実なやり方だからです。それとは逆に、マイルスのモード(旋法)によるジャズの在り方は、明らかに“革命”でありました。そこはどうしたって否定できませんよね。
ドン・エリスはどちらかというと、世界に存在する様々な音楽要素を、ジャズを土台にゴチャゴチャにミックスし、ビッグバンド上で再構築したフュージョン・ミュージックだと考えられます。まさに“オール・ザット・ジャズ(なんでもアリ)です。時代をリードするアメリカ音楽が“多様な音楽性のフュージョンである”とした宮崎尚志にしてみれば、ドン・エリスの方法論はジョージ・ガーシュウィンの「ラプソディー・イン・ブルー」以来の流れにピッタリ合致するものであり、実にアメリカらしい新しいジャズを創作していたと考えられます。
多大なるロックへの影響力
私の認識では、ドン・エリスはここ日本に於いては知名度が低いようです。父も全く同感でしたが、これは大変残念なことです。マイルス・デイヴィスを船頭とするモード・ジャズ
一方、ドン・エリスの楽団で修行した者の中には、1980年代にデイヴ・グルーシンらとフュージョン・シーンをリードしたトム・スコット(Alto Sax)、1970年代にフランク・ザッパ大先生のマザーズ・オブ・インヴェンションでも活躍したドラム・マスター=ラルフ・ハンフリー(dr)、マンハッタン・トランスファーの大ヒット『エクステンションズ』のプロデュースやデヴィッド・フォスターとの伝説のプロジェクト“エアプレイ”で、特に日本のスタジオ・サウンドの指標となったエキサイティングなサウンドを作り出したプロデューサーであり天才ギタリスト=ジェイ・グレイドン(g)など、正に玄人好みの渋いメンツが揃っています。ユニークなのは、それら全員が卓越したソリストでありながら、音楽的にはアンサンブルに重点を置いたドン・エリス楽団と同じ指向性で今でも音楽やっていることです。しかも全員、かなりヘンだと思います。