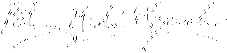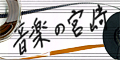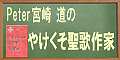Powerd by
sogaku.com
宮崎尚志のレコード棚
フォア・フレッシュメン:
『フォア・フレッシュメン&ファイブ・トロンボーンズ』
Four Freshmen and 5 Trombones (1956)

前回の『オン・ステージ』に続き、フォア・フレッシュメンにまつわる連載第2回目です。
幸福と美の音楽生活
1950年代に一世風靡した男声四部オープン・ハーモニー・コーラスの大家=フォア・フレッシュメンが前代未聞の5本のトロンボーン・アンサンブルを加えて製作した、極めて意欲的なジャズの大傑作アルバムとして現在も有名な1枚。ここで聞けるサウンドは驚くほど厳かで、ダイナミックで、そして美しいビッグバンド・ジャズです。若かりし頃、父が聞きまくったレコードの1枚である以上に、当時の世界のジャズ・ファンを虜にしたレコードです。ここで聞けるオープン・ハーモニーをアナリーゼし、コカコーラ日本最初のコマーシャルソング「スカっとさわやかコカコーラ」のサウンドが誕生したことは前回記しました。
フォア・フレッシュメンらが活躍した時代は白人ならではのコンボ・ジャズが急速に洗練されていった時だと言って構わないでしょう。が、言い換えれば比較的裕福な中流階級白人社会を中心に広まったこともあって、従来のジャズに比べて泥臭さも切迫感もなく、概ね穏やかで爽快で幸福感に満ちた美しいアンサンブルを聞かせるのが常です。聞いていて幸せな気分になる音楽というのは最近はトンと耳にできなくなりましたが、この味わいこそ20世紀のGood Old Times of America最大の資産でしょう。そういう意味で、特にフォア・フレッシュメンのこのアルバムは、本当に至福のリスニングタイムを与えてくれます。しかし、もしかしたら、当時はこれが最も“ホット”なサウンドであり、“スリリング”なものだったのかもしれませんね。
父がフォア・フレッシュメンの所蔵盤の中でも特にコレを聞けとプッシュしたのには、ライヴならではのラフさが魅力の『オン・ステージ』よりもずっと正確なハーモニーと、フォーカスのハッキリした音像によって“聞き取りやすい”こと、そしてオープン・ハーモニーの基礎の基礎、正に教科書であるこのサウンドに耳を慣らさせるにはもってこいだと考えたのでしょう。私は、このハーモニー感に慣れてアナリーゼしたらマンハッタン・トランスファーを聴いていいぞ、と父から言われたものです。実は、家にあったマン・トランは全部聞いてしまった後だったんですがね・・・。
ブライアン・ウィルソンも学んだ最先端のサウンド

このアルバムは、音域がほとんど同じ男声とトロンボーンの集団共演でありながら、その実オープン・ハーモニー(コーラスの書法)と密集和音(トロンボーン書法)のコラボレーションと言い換えることが出来ます。ジャズ・コーラスの新たな可能性と、世間をアッと驚かせる実験精神が見事な成果を挙げたことは、これを今聞いても凄く重厚な音なのに爽やかで、耳に馴染む懐かしい響きがあるという、実に新鮮な響きを持っていることでも十分伺い知ることが出来ます。結局、トロンボーンの楽器的特性(スライド奏法など)を存分に生かしながらもトータルなサウンドは誠にまっとうなもので、異種格闘技のような顔合わせがまるでウソのように自然なジャズに帰結しているのは見事という他ありません。
このレコードに夢中になり、ハーモニーを徹底的にアナリーゼして自分の音楽に積極的に取り入れた数多くの人物の中でも、ブライアン・ウィルソン(元ビーチボーイズ)は特筆すべき存在です。初期ビーチボーイズは流行のサーフ・サウンドにフォア・フレッシュメン的なコーラスが乗る・・・・いわば砂浜に摩天楼を立てるようなユニークなサウンドでしたが、次第にコーラスワークを複雑ながら明解な対位法で書き込むことで独自の音を作り上げ、アメリカン・コーラスの第一人者と言われるまでになったブライアン・ウィルソン。その基礎がフォア・フレッシュメンにあることは一度聞けば誰でも直ぐに判るものです。
2004年に日本語訳本が発行された『ペット・サウンズ・ストーリー〜ブライアン・ウィルソン奇跡の名作の秘密』(キングスレイ・アボット・著/雨海弘美・訳/ストレンジデイズ刊)で、少年時代のブライアン・ウィルソンがラジオでフォア・フレッシュメンを聞き、すぐにこの『フォア・フレッシュメン&ファイヴ・トロンボーンズ』を皮切りに彼らのレコードを聞き漁りながらコーラスのアナリーゼをはじめたことが記されています。そしてブライアンはフォア・フレッシュメンから音楽を学んだのみならず、そのハーモニーに夢中になることで自身が幸せになる方法を会得した、とも書かれています。フォア・フレッシュメンの型破りな活動とその成果は、その後1960年代半ばに正に型破りで革新的な方法論で時代を超越した『ペット・サウンズ』、『スマイル』を製作する天才ブライアン・ウィルソンの音楽性を育んだのです。
無茶苦茶やってもポップに軟着陸させる方法論の基礎

実を言うと父=宮崎尚志とブライアン・ウィルソンとの接点はまったくありません。又、父はビーチボーイズはじめ、ブライアンの作品は全くといっていいほど聞くことはありませんでした(ラジオで耳にした事はあるでしょうが)。が、この2人には多くの共通点を見いだせるのです。
まずジョージ・ガーシュウィンの「ラプソディー・イン・ブルー」を自己の音楽のバイブルとし、そしてクラシックとジャズに親しみ、『フォア・フレッシュメン&ファイヴ・トロンボーンズ』でオープン・ハーモニーのジャズコーラスに開眼。この異種格闘技的取り組みに夢中になっています。更に共に音楽家となってからは作曲・アレンジを他人に任せず、録音された音に関するまで全てに徹底的にこだわる完全主義者的な側面が強い。レコーディング・スタジオの虫であり、現実的(生演奏)にはアンサンブルが困難な編成をも“録音”という上で実現させるスタジオ・マジックに邁進。楽器ではないものをリズムに用い(ブライアンは野菜、父はバケツに張った水・・・など)演奏に取り込んでいったり、録音された演奏テープをコラージュして予定されていた音楽とは全く別のものを作り出す実験精神。いち早いテルミンの使用。新しいサウンドを求めるためならスタジオ・エンジニアリングの常識をも逸脱する野心。コーラスをアンサンブルの最も重要なインストゥメントとして常にウェイトを置く。そして何より、基本はメロディーメイカーであったこと。
父の録音には日本スタジオ・シーンの超凄腕ミュージシャンがこぞって喜んで参加したものですが、彼らが譜面が難しくて頭を抱えている場面に私も何度か目の当たりにしました。その度にミュージシャン達が互いの譜面を見比べて、自分の弾く音の意味を把握し合っていたものですが、父が最も大切にしていたのは全体のフィーリングでした。ブライアン・ウィルソンもハリウッドの超一流スタジオミュージシャンからは尊敬の眼差しで見られていたそうで、譜面では判りかねる曲のフィーリングを自ら歌って伝え、全体のフィーリングさえ良ければ個々の楽器のミスタッチなども気にしなかったといいます。
つまり2人の音楽性は違いますが、目指すところは似通っていたと思うのです。一見、常軌を逸した無茶苦茶なことをやっていながら、最終的な完成品は常に素直なポップに着地している。そのベクトルの出発点は必ず『フォア・フレッシュメン&ファイヴ・トロンボーンズ』から学んだ、新しい音を追求しながらも王道ジャズに着地させた実験精神・冒険心だったのではないかと思います。
フォア・フレッシュメン・トゥデイ…イエスタデイ?!

父が所有していたフォア・フレッシュメンのアルバムは3枚でしたが、私に聞くように勧めたのは2枚だけで、年代的に最も新しい『トゥデイ(A Today Kind of Things)』は「それは別に聞かなくてもいい」といった感じでした。それまでジャズ・スタンダードが基本だったフォア・フレッシュメンが1960年代のポピュラー・ヒットを歌うという指向のもので、ビートルズやタートルズ等も含まれていて選曲が良いので、それでは聞いてみよう(?!)となったものの、確かにこれは聞かなくても良かった?! オープンハーモニーの魅力が半減し、リハモナイズ(和音を新たに付けていく行為)は非常に窮屈な感じで、無理してジャズ化している印象が残る。ふむ、父がこのアルバムでフォア・フレッシュメンとお別れ(??)したのは納得できる内容でした。特に最後の「Homeward Bound」で、乾いたエレキの若大将ギターみたいのが出てきて、水準以下のビーチボーイズ・コピーバンドにさえ聞こえる。これは悲し過ぎる。オッサン達が若ぶってやってみたはいいが超ダサくなっちまった、って感じ!
晩年、父にこれら3枚のレコードをコンピューターで取り込み、デジタル処理で盤面のスクラッチノイズ除去し、音質補正してCD-Rに焼いてプレゼントしたところ、「最後のヤツ(=Today)は全然、らしくないんだよな、他と比べるとかなり最近の録音なんだけど」とコメントしておりました。どうも昔から気に入らなかったようですな。ふむ、私もこれは誰にもお薦めしないなぁ。