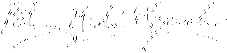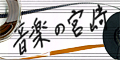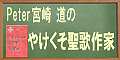今回はシンセサイザーのお話がいっぱい出てきます。ワカランひとにはまるでチンプンカンプンな話がテンコ盛りです、どうもスミマセン。とはいうものの今回のエピソードは、私ら息子達がレコード棚で“救済”した1枚のレコードによって、作曲家・宮崎尚志に若干の意識改革を促したという珍しいお語です。
Vintage Synthesizer
アープ2600とEMS SYNTHI-AKS
 1972〜73年頃、父はシンセサイザー=アープ2600(ARP2600)を購入し、自宅の仕事部屋に設置しました。確かモリダイラが日本国内の代理店をやっていたと言っていた覚えがあるのですが、納品時には米国本社から販売担当のエンジニアらしき人物(日本語はほとんど話せなかったらしい)が来て、マニュアルに添付する予定だったサウンド・セッティング・チャート(例えばヴァイオリンのような音はこうやれば出る、といった図面)が間に合わなかったからという理由で、お詫びとしてその場で白紙のセッティング・シートに何枚も、様々な音色のセッティング例を書き込んでいったそうです。これはシンセサイザー黎明期の、実に微笑ましい(??)エピソードです。
1972〜73年頃、父はシンセサイザー=アープ2600(ARP2600)を購入し、自宅の仕事部屋に設置しました。確かモリダイラが日本国内の代理店をやっていたと言っていた覚えがあるのですが、納品時には米国本社から販売担当のエンジニアらしき人物(日本語はほとんど話せなかったらしい)が来て、マニュアルに添付する予定だったサウンド・セッティング・チャート(例えばヴァイオリンのような音はこうやれば出る、といった図面)が間に合わなかったからという理由で、お詫びとしてその場で白紙のセッティング・シートに何枚も、様々な音色のセッティング例を書き込んでいったそうです。これはシンセサイザー黎明期の、実に微笑ましい(??)エピソードです。
確かにミュージック・シンセサイザーの代名詞である“モーグ(MOOG)”が登場したばかりの頃、物珍しさから手に入れた購入者からのクレーム・ランキングのトップは、「どこをどうひねってみても音が出ないぞ、不良品じゃないのか?」だったそうですから、例えばヴァイオリンに似た音はこうやって作るんですヨ、トランペットはこうですよ、と説明しないと、楽器がひとつも音を出してくれなかったんですって
シンセサイザーが導入された為、四畳半ほどの広さしかない父の仕事部屋は急速に“自宅スタジオ”化していきました。スタジオで録音したテイクを自宅に持ち帰り、アープ2600を自ら弾いてシンセ・サウンドをオーバーダビングし、完パケを作るといった作業が行われていました。しかしウチのアープ2600は初期型で衝撃に弱く、自宅から外に持ち出して使用する事は故障するリスクが非常に大きかったそうです(実際、私が引っ越しで何度か移動させる度にモジュールが1つずつ不調になっている)。故に1970年代半ばにはアタッシュケースに収まった超コンパクト設計で、しかもアープ2600並にサウンドの幅があり、最新鋭のデジタル・シークェンサーを内蔵した、英国EMS社製の“AKS”(SYNTHI AKS)を購入します。

ヘンな話、英国製のシンセサイザーなんて聞いたこともなかった。英国製の新しい鍵盤楽器といえばメロトロンぐらいしか思い付かなかったし、シンセサイザーはアメリカ・オンリーだと思い込んでいた頃で、「EMS[Made in England].Ltd」と書いてあるのには驚きました…へぇー!イギリスのシンセサイザーなんて、あったんだ!
父はEMS AKSを手に入れてから、レコーディング・スタジオ、自宅スタジオを問わず愛用しました。このシンセサイザーの極めて優秀なポイントは、内蔵デジタル・シークェンサーにありました。アナログ・シークェンサーをデジタル化した発想を持っていて、音階のパターン(シークェンス)をメモリーさせてループ再生させている最中に、鍵盤で移調させることが出来ました。この機能が優れていたため、主に“演奏”のためではなく、シークェンスを走らせるシンセサイザーとしての使用度ばかりになってしまいましたが…。
この2つのシンセサイザーは、滅多にライヴ・ステージで見ることが無かったほどに“スタジオ仕様”だったようで、実際、アープ・シンセサイザーは姿は見えなくとも(?)、当時のどんなレコードでも容易に聞けましたし、EMSはピンク・フロイドのアルバム『狂気』(1973)の中の「走り回って」でのシークェンサーを使ったシンセ・サウンド(ライヴ映画『ピンクフロイド・ライヴ・アット・ポンペイ』でその録音風景が見られ、ロジャー・ウォータースがAKSをいじっています)、他にもカーヴド・エアとかの純英国バンドのレコードでは比較的多く聞けました。余談ですが最大のEMS偏愛者は、多分間違いなく英国のブライアン・イーノでしょう、ご自分でそうおっしゃってましたから。
父の“シンセサイザー”に対する認識は、今まで誰も聞いたことのない、全く新しいサウンドを出すための最新鋭の楽器でしたから、アンサンブルの中で、とかく耳を惹くヘンなリード音や、鋭いショッキングなアタック・サウンドを使いたがりました。故に、既存の楽器のシミュレーションには全くと言って良いほど興味がなく、クラシック曲をシンセサイザーで演奏する事にも懐疑的でした。唯一の例外が、かつてNHKで仕事仲間の一人だった冨田 勲さんの一連のアルバム群でしょうか。しかし冨田さんはモーグ(MOOG)の熱烈ユーザーでした。

ARP+EMSという2台を好んで使っているという人は、世界中のミュージシャンを見渡してもなかなか見つからない。が、フランスから登場した若いイケメンのシンセシスト(シンセイサイザー奏者)が、これらをメインに据えて製作したアルバムを発表、しかもそれがフランスで大ヒットし、そのシンセシストは国民的ニュー・ヒーローであるとのこと。その人こそ、ジャン・ミッシェル・ジャールでした。
レコード棚唯一のダメ盤?
J=M.ジャールがワールドワイドの1stアルバム『幻想惑星』で登場した折、日本での紹介の筆頭に挙げられていたのは、やはり映画音楽の大巨匠=モーリス・ジャールの息子であるという点でした。それは宣伝文句としては良かったかもしれませんが、内容的には若干の誤解を招いたと思います。父はモーリス・ジャールが好きで、ハリウッドの[作曲家+オーケストレーター]という分業スタイルを嫌い、頑固一徹、フル・オーケストラのフィルム・スコアを直接書いてしまう、その音楽家としての姿勢(オールドファッションには違いないが)を大変尊敬していました。その息子が、自分と同じ楽器を使ったシンセサイザー組曲を作ったのですから、過度な期待をするなと言う方が無理というものです。
しかし父はこの作品を一度聞いて憤慨し、レコード棚に入れずに、ほったらかしにしました。尚、地球の地表が剥けて骸骨が半分あらわれている不気味なカバーアート(ジャケット画)はとても怖く、当時小学生だった私にはとても直視したくないものでした。1977〜78年頃のことではないかと思います。
私が中学生になったばかりの1980年頃、祖母がJ.S.バッハのオルガン・レコードと間違えて買ってきたシンセサイザー・レコードの古典『スウィッチト・オン・バッハ』(旧姓ウォルター・カーロス!)を聞き、シンセサイザー・ミュージックに一気に目覚めた私は、兄からこの『幻想惑星』を紹介されました…
あ、あの恐怖レコードじゃないか!!
その時、父が言うには、「ジャン・ミッチェル? それ、面白いかぁ? ボクは一度聞いただけで物凄く腹が立ったぜ。インチキだよ、ロクな音楽じゃないよ。新しくも何ともないし。レコード屋に返品しようか、捨てちゃおうって思ったんだけど、君たちが面白いって言うんなら、捨てなくて良かったのかなー。」 …とまぁ、最低の評価。
そこまで言う音楽なら、是非とも聞いてみようじゃないか、という事になって、私は早速『幻想惑星』に針を落として聞いてみました。結論から言ってしまえば、そんなに酷くない…というより、とっても気に入りました。ディレイ(エコー)を多用したフワフワとした、耳障りの良い質感が全体を覆っていて、しかも神秘的なほどの“暗闇”に覆われていて、中には明確なメロディーが全くない曲もある。『スウィッチト・オン・バッハ』とは全く違う世界観に驚きました。
ですが正直に言うと一番驚いたのは、「躍動(Part IV)」。リズムボックス(クレジットには“リズミン・コンピューター”とある)にビートを刻ませ、まるでシャンソンの如き…いや、日本の小椋 圭さんの「ふりむけば愛」の主題歌のような、信じられないほど親しみやすいカンタービレな(?!)メロディーが飛び出した瞬間でした。なんか、シンセサイザー・ミュージックにはマッチしないような“生ヌルさ”(今で言うところの“ユルさ”かも)があって、しかもスゴくチープに聞こえました。生演奏が入っているレストランやビアホールで、エレクトーンで演奏しているインスト・シャンソンを強く思わせました…もっと端的に言ってしまえば、ダッせぇー!
ただ、いかにも“シンセサイザー”な、ピョ〜〜〜ンとかブチュブチュブチュ〜〜とかいう“宇宙音(Space Sound)”がやたら入っていて、こういうレコードもあるのだな、と思いました。随分、シンセで遊んでいるな…と。但し、どうやってその音を出しているかなど、全く気に止めませんでした。

何だかだ言っても、このレコードのトータル・サウンドが大変気に入ったので、私はすぐにお小遣いをためてレコード屋に行き、2nd『軌跡(EQUINOXE)』(1978)、3rd『磁界(Les Chants Magnetiques)』(1981)を買い求めました。この2作品は『幻想惑星』より飛躍的に完成度がアップしていて、現在も愛聴盤です。特に『磁界』では“フェアライトCMI”という当時最新鋭のデジタル・キーボードが使われていて、21世紀の現在聞いても依然刺激的です。私にとっていわゆる“サンプリング”の音を初めて聞いたレコードでもあります。
ドキュメンタリー『コンサート・イン・チャイナ』

ジャールを居間のステレオセットで聴いていると、父はあまり良い顔をしませんでしたが、それでも「音楽が好きなことは良いことだ」というワケで許容してくれたものです。そんな折、ジャールの中国公演を収めたライヴ・アルバム『コンサート・イン・チャイナ』が発売されたというニュースを、テクノ好きの友人から聞きました。シンセシストのライヴ盤? そんなもんが面白いのか? 懐疑的な私に、YMOのライヴ盤はレコードで聞いてきた大好きな曲の“別バージョン”みたいで凄く面白かったから絶対に楽しめるよと、是非聞くように薦めたのもその友人でした。それで買って聞いてみたら、確かに楽しかった。なるほど、ライヴ盤ってのは結構イイもんだな、と(ライヴ・アルバムというものを手にしたのは、これが最初でした)。
このライヴ盤を聞いて、私はやたらと刺激的な音のするシンセ・ドラムに夢中になりまし。“シモンズ・エレクトリック・ドラム”です。ここでのシモンズの音は、当時大変な話題になっていたサンプリング・ドラムマシンの草分け“リン・ドラム”を軽く吹き飛ばすだけの魅力がありました。
暫くしてNHKの番組「ヤング・ミュージック・ショー」で、ドキュメンタリー・フィルム『ジャン・ミッシェル・ジャール・ライヴ/コンサート・イン・チャイナ』が放映され、父はこれを私と一緒に見ました(ビデオでも録画した)。文化大革命以来初となる中国本土での西洋音楽の公演、シンセサイザーという電子楽器の存在を全く知らない中国人民に向けてのアリーナ・ツアーといったトピックスをまるで意に介さず、父が大仰天していたのは、アンサンブルのリーダーであるジャールが、鍵盤で楽音を奏でることなく、6〜8数台もあろうかといったEMS AKS(又は入れ物違いのVCS3)を縦に、壁状にセッティングし、あのピョ〜〜〜ンといった宇宙音を“演奏”していた事でした。

EMS AKSにはジョイスティックが付いており、中央にある黒いマトリックス・パッチボード(針を刺してモジュール間を連結する画期的なシステム・シンセだった)でボリューム、ピッチ、モジュレーション等を上手くアサインし、パッチボードの横にある赤いスイッチ(トリガー・キー)があり、これを押すと鍵盤がなくても音を出すことが出来ます。ジャールはこれらを大変上手に扱い、レコードで聞ける様々な宇宙音をライヴで演奏してみせたのでした。
| あっ、EMS!これ、ウチにあるヤツ。・・・一体何台あるんだよ、これ。・・・ひゃぁ〜、EMSはこういう使い方もあったかぁ〜・・・宇宙音を演奏してんだもんな、こりゃースゴい。こんなことやってんの、見たこともないぞ。サスガのボクもビックリ仰天だ! |
当時、父はスタジオ・レコーディングに於いては、EMS AKS内蔵のデジタル・シークェンサーにシークェンス・パターンを入力しておき、キラキラしたシンセ・シークェンス・サウンドをアンサンブルのバックに配するというやり方が定着しており、もはやそれ以上を求めなくなっていました。故にこの1981年のドキュメンタリー映像は、父には「EMSはまだまだ現役だ!」という強い意識を植え付けたようです。しかしその後、すぐにプリント鍵盤部分が壊れてしまい(父は「石が飛んじゃった」と表現していた)、シークェンサーのコントロールが出来なくなって現役引退させてしまいましたが…トホホ。
ともあれ、このドキュメンタリー・フィルムを見たことで、ジャールに対する父の評価はかなり上方修正されました。ジャールの専属フォトグラファーとして同行していた女性が、かの名女優シャーロット・ランプリングで、当時ジャールの奥さんだったというのも父にとってはポイントを高かったかも。こういう顔した女優さんが好きだったので・・・ソフィア・ローレンとかフェイ・ダナウェイとかね。
シモンズを導入しろ!キャンペーン

私が注目していたのはフェアライトCMIとシモンズ・ドラムです。初めて見る両機材にワクワクしましたが、PCディスプレイ(緑色で表示される古いヤツ!)がある以外は白くて素っ気ないフェアライトに対し、シモンズは打面が六角形をしたスタイリッシュなドラムで、しかも映像では赤いヤツ。抜群にカッコ良かった。父は「なんだなんだ、このシンセ・ドラムは?見たこともないぞ!」 と言うので、これがシモンズという最新のシンセドラムらしい、と教えたものです。
シンセ・ドラム(略して“シン・ドラ”と呼んでいた)というものは意外と古くから存在していましたが、まるっきり発展しなかった分野でもありました。「ポ〜ン!」とか「ピョ〜ン!」とか、気の抜けたシンセ・サウンドを発するだけで、楽器としては“効果”として使う以外にありませんでした。シモンズ・ドラムは、シンセサイザー部を根本的にドラム専用にデザインし直して“時代的な必然性のあるサウンド”を作り出したこと、これこそがエポックメイキングな事でした
それまで聞いたこともない斬新なサウンドを出す楽器に敏感なNaoshism宮崎尚志としては、刺激的なシモンズの音が大変気に入った様子。父はまず手始めにCM録音に使おうと思い、スタジオに出入りするマニュピレーターさん達(機材貸し出し業者/操作屋)に当たったところ、誰一人として持ってない(T.スギヤマ氏も持ってなかった)。というよりシモンズそのものがまだ世界のポップスシーンではほとんど使われておらず、ましてや1981〜1982年当時の日本にはまだ入ってきてませんでしたから、スタジオ・シーンでは知られていなかったのです。録音を終えてスタジオから帰ってきた父は、「まだ日本に入ってきてないんだってサ!でもそのドラムのことを口にしたのは、宮崎先生が初めてデスよ、とか言われちゃった。」 と残念そうでしたが、スタジオに来るマニュピレーターさんには「シモンズを買え、とにかく早く入れろ、使わせろ」と必ず催促していたそうです。
その甲斐あってか、1984年頃にはようやくスタジオにシモンズが来るようになりました。1985年の科学万博「つくばEXPO'85」(通称:つくば万博)の「KDDテレコムランド」のテーマソングや音楽に、1986年の映画『彼のオートバイ、彼女の島』(監督:大林宣彦)のサントラに全面使用・・・何故か伊勢の“赤福餅”のCM(宮崎尚志がずっと音楽を手がけてきた)で使ったりもしてましたがね・・・。ともあれ1980年代末まで、父は自身のレコーディングに於いて、シモンズを使い倒しました。
日本で一般的にその“音”が知られるようになったのは、1983年の「Cat's Eye」(杏里/アニメ「Cat's Eye」主題歌)、1984年の「HERO」(麻倉未希/TV「スクールウォーズ」主題歌)あたりでしょうが、その“物”がお茶の間に知られたのは、何といっても1985年のC-C-Bの大ヒット「Romanticが止まらない」でしょうね。TVの歌番組で黄色い(??うろ覚え)シモンズを叩きながら歌う笠 浩二(dr,vo)さんの姿は、洋楽を聞かない人達には強烈にカッコ良かったハズです。そうえいば笠 浩二さんはピンクの染め髪でしたけど、大きめの丸眼鏡だし小柄だし、歌声もハイトーンだし、どうにも“バグルス”時代のトレバー・ホーン(後に超大物プロデューサーになった)を思わせてならなかったな・・・関係ない話だけど
フェアライト購入計画

「シモンズを導入しろキャンペーン」活動と同時期、何と父は「フェアライトCMIを買おう、資料請求しよう」と言い出した時には仰天しました。ウチにそんなお金、ねぇ〜よ! フェアライトの広告が初めて載った音楽雑誌を前にして、父曰く・・・
| なっ、コレ! ジャールが使ってたヤツ。これは絶対に使えるぞ。聞いたことないような新しいサウンドが出てきそうだよ。フルセットでも多分、600万ぐらいじゃないかな? 君が使えるようになれば、仕事ではマニュピレーター雇わなくて済むし、一石二鳥じゃないか。 |
私はおおよその値段を知っていたので、やめろやめろ!絶対無茶だ、と説得しましたが、父のニュー・サウンドへの飽くなき探求心には歯が立たず(聞く耳持たず)。しかし1週間後ぐらいにスタジオから帰ってくるなり・・・
| フェアライトのこと、知ってるヤツがいたから聞いてみたら、1,200万円もするんだってサ! 久石(譲)はそれ買って、自宅で仕事してるらしいよ。キーボードだけじゃ音が出ないんだって。テレビ(ディスプレイのこと)とビデオデッキ(コンピューターの心臓部のこと)と鍵盤の、全部揃って初めて使えるってんだから、簡単に持ち運びできないって。そんなのとても買えないよな! |
あぁ〜、諦めてくれてよかった、家潰れちゃうよ。でも、フェアライトのマニュピレーターとしての仕事がとれたかもしれなかったけどね・・・やりたかないけど。
とはいえ、その当時の宮崎尚志はアープやEMSに替わる新しいシンセサイザーを欲していたようで、“サンプリング・キーボード”の草分けであるE-MU社のイーミュレーターには目もくれず(デジタル版メロトロンだと言っていた)、サンプリング音すら波形レベルで書き換えることができたフェアライトCMIは正にドンピシャに見えたんでしょう。実際はそうならなかったと思うんですがね。(当時のバージョンはIIだったと思う)
J=M.ジャール、幻の日本公演の話
話は変わりますが、※1990年代初頭だったか、東京の自宅の前にフランス大使館員が住んでいました。隣組でよく顔を会わせていたので話をする機会があったのですが、その方は父に、ジャールが日本でのコンサートを行いたいと熱望している、よってしかるべき人を紹介して欲くれない(とかなんとか)との旨を伝えました。候補地として東京・新宿と、英国のロンドンが上がっているが、ジャールとしては新宿副都心での開催を一番に望んでおり、コンサートの模様は全世界に衛星中継する一大プロジェクトになるとか。これを聞いた私は狂喜しました。いいぞいいぞ、やれやれ〜!
丁度その頃、ジャールは母国フランスのラ・デファンスのグランダルシュ(新凱旋門)コンサートを行ったばかりで、この模様はNHK-BSでも放送され、私達親子はそれをじっくり観て、「コンサート・イン・チャイナ」から遥かに進化したスタイリッシュでスペクタクルなステージに、大いに感動させられたものです。ここではEMSはもう見られなかった覚えがあるんですがね。
ジャールのコンサートは常に屋外、しかも高層ビル街の谷間にピラミッド型のセンター・ステージを作り、周辺のビルをスクリーンにしたり、様々にライトアップして舞台美術的に用いたり、レーザーを空に向かって放つなど、その様子は遠く離れた地からも鑑賞できるほどスケールの大きなもので、新宿副都心の高層ビル街でそれが行われると思うと、ワクワクしました。当時、地元の豊島区・池袋駅周辺で様々な大規模野外イベントを発案し、プロデュースしていた父としては、これは面白いぞと思ったものの、新宿区となると話は別。都知事や政治家を通じ、この企画を推進するのが良いだろうとアドバイスしたとか。
その話があった1年ほど後、ジャールはロンドンでコンサートを行い、そのニュースは日本にも伝えられました。が、新宿では一向に行われる気配がない。で、お向かいの大使館員に聞いたところ、残念ながら新宿では許可が下りずに断念し、許可が取れていたロンドン公演を行ったと。新宿では道路をストップさせることはNG、ビル街の電気を消したり操作することはNG、大きなボリュームで音楽を奏でることは騒音公害となりNG、ジャール側が見込んでいる観客動員数を収容するだけの物理的な広さがないのでNG。その他、交通整理で大勢の警察官を動員することはNG、警備のための人員を調達できないためNGなど、完全に“現実的に不可能”により不許可だったとこのとでした。
この顛末を聞いて、私は大変残念に思ったものです。しかし実際、その当時は既に日本のポリドールはジャールのアルバムの国内発売を打ち切っており、一般的な知名度も欧州ほどではなかったのだし・・・。ともあれ、ジャールが新宿でコンサートをしようと画策していたという話、しかも許可が下りず、ジャールは酷く残念がっていたという話を聞けただけでも、非常に面白かったものです。
|
※追記(2011年10月3日) 1990年初頭頃というのは私の記憶違い。これは1987年の話。ジャールはどうやら新作のプレミア公演を新宿副都心でと考えていたようで、在日フランス大使館を通じて実際にコンタクトが計られたが東京都から断られたらしい。一方のロンドンではドッグランドが公演を許可したため、産業革命からスタートする“革命”コンセプトにした新作アルバム『Revolutions』が作られ、大コンサート“Destination Docklands”が実現し、その模様はライヴ・アルバム『ジャール・ライヴ』にまとめられた。又、放送されたコンサート映像は現在はYouTubeでも一部確認することが出来る。もしも新宿で開催されたとなれば、ジャールの新作は全く違ったものになっていた可能性もある。アルバム収録曲にして唯一異質なムードの「Tokyo Kid」は、ジャールの夢の追想といった趣なのかもしれない。経済効果という点でも、長きに渡って新宿はモニュメンタルな都市として記憶されただろうし、日本がコンセプトの中心となるようなアルバムが作られたかもしれない。又はジャールが大好きな「現地の人達と共に作り、共演する」というコンセプトの上で考えれば、ジャールとステージで共演する日本のミュージシャンがライヴの世界放送によって一気に宣伝になるということも考えられただろうし、日本にとってはワールドワイド展開に向けての大きなチャンスがあった。だが当時、そんなものを不問にする世論が日本を覆っていたのも事実だ。「バブル景気」である。 その後、1991年に新凱旋門コンサート“Paris La Defense”が行われた模様がNHK-BSで放送され、それを私ら親子が見たわけだ。実はその放送予定を番組表から見つけたのは両親であり、ジャールの日本プレミア公演の話を聴いていなかったなら両親の興味の対象外にあり、私も確実に見逃していたに違いない。 |
ゴミ箱から宝モノ
時代の最先端(ファッション、テクノロジー、生活習慣でも何でも)を敏感に察知する嗅覚と、時代の先を行こうとするフロンティア精神が結びつくと、その足跡は必然的に“流行”というものになると言った宮崎尚志は、時代遅れでインチキと切り捨てた『幻想惑星』の作者であるジャン=ミッシェル・ジャールから、皮肉にも海外の“最先端”を色々と学ぶハメに陥ったというワケです。しかし、そもそも私ら兄弟が面白がって聞いていなければ『幻想惑星』は確実にゴミ箱行きでしたし、ジャールのその後の大躍進すら知らなかったに違いない。となるとシモンズもフェアライトもいち早く知ることは出来なかったでしょう。即ち『幻想惑星』は、その音楽自体ではなく、レコードが家に在ったという事自体に大きな意味があったわけです。でなければ、多分私らもFIFAサッカーワールドカップ・フランス大会の「Together Now」で、あの日本の“TK”のバック(?!)で極端な猫背パン(ジャール得意の超前傾姿勢。ツール・ド・フランスの選手みたいな!)でシンセを弾いていた、誠にパっとしないフランス人キーボーディストとして、印象にも残らずに素通りしていたかもしれない。
ちなみに現在も尚、私はジャールの音楽もサウンドも、大好きです。いやはや『幻想惑星』のお陰か?それともジャールをこき下ろした父の言動のお陰か?