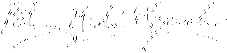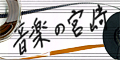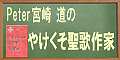反骨精神丸出しのインテリジェント白人ブラスロック
これまた説明不要、現在も活動を続けるブラスロックの巨人=シカゴのデビュー・アルバム。これぞロックと言わんばかりのインテリジェントでロジカルな“怒り”に満ち、音楽的にも優れ、ベトナム戦争真っ直中の“お先真っ暗”な時代にあって前向きに社会に関わっていこうとする尖った若者像の象徴的アルバムです。
故フランク・ザッパ大先生の率いる“マザーズ・オブ・インヴェンション”にギタリストとして在籍していた経験があるジェームズ・ウィリアム・ガルシオがプロデュース。このガルシアはいわば白人ブラスロックを世界に広めた立役者であり、シカゴと同時期にブラッド・スウェット&ティアーズ(BS&T)をプロデュースしています。
シカゴのこのデビュー盤はなんと2枚組!狂ったシステム社会からの逸脱の自由を訴えたマザーズ・オブ・インヴェンションのデビュー盤『フリーク・アウト!』(1966)が2枚組でしたから、ガルシアは“反骨ロックには2枚組で”という基本的アイディアがあったかもしれません。ガルシア曰く“お行儀の良い大人しいバンド”だったBS&Tはシングル・アルバムばかりですが、シカゴはこのデビュー盤から4作目ぐらいまでダブル・アルバム(2枚組)で通しました…そいつぁースゲーよ!
素直になれなくてよ…
私がシカゴの名を知ったのは中学生だった1982年頃でしたか、シングル「素直になれなくて(Hard To Say I'm Sorry)」が爆発的にヒットしており、ラジオで盛んに流されていたのを聞き、なんて素晴らしい曲だろうと感動した時でした。小林克也さんのTV番組『ザ・ベストヒットU.S.A.』を見始めたのもこの頃でした。その後、1984年頃には新しいアルバムが出て(17th『シカゴ17』)、「ステイ・ザ・ナイト」や「忘れ得ぬ君へ」等がビデオクリップ付きでTVから流れてきました。それを聞いた父は一言…
「これがシカゴか?…シカゴはこんなンなっちゃったのか…」
面白い演出のビデオクリップとシカゴの音楽を楽しんでいた私とは正反対に、父は物凄く寂しげな声でそう呟きました。かつてシカゴが反骨ロックの急先鋒であり、社会制度の改革を叫ぶ若者達を代弁するパブリック・メッセンジャーだった事実からすれば、失恋ソングを歌うAORバンドとなってシーンの第一線に返り咲いたシカゴの雄姿(??)なぞ、出来れば見たくなかったのでしょう。デブだったフロントマンのピーター・セテラ(vo,b)は、すっかりスリムになって別人みたいだし…?!
これぞロック!
ブラスロックは当然、ビッグバンド・ジャズからの流れを汲みます。ですからビッグバンド好きで、アメリカの若者に大ウケしたシカゴの音楽に宮崎尚志がこれに飛びつかないワケがありません。とはいってもレコード棚にあったシカゴのレコードは1st『シカゴの軌跡』、2nd『シカゴと21の誓い』、10th『シカゴX』の3作だけ…あれ、随分寂しいじゃないか!

父が寂しがるシカゴの栄光の歴史を紐解くため、私はレコード棚から2ndアルバムを引っぱり出し、初期の大ヒット曲「長い夜(25 or 6 to 4)」を居間のレコードプレイヤーで聞いてみました…おぉ、無骨でゴリゴリだぜ!これがあの美しい「素直になれなくて」のシカゴか?!…ちょっぴりショック。ところで原題の“25 or 6 to 4”ってどういう意味だ?“午前4時25〜26分前”…なんだそりゃ?
そこへ父がやってきて「お、シカゴか?シカゴ聞くなら最初のヤツを聞きなよ。そこにあるだろ?黒いヤツ。」と言いました。何故なのかと問うと、「最初のヤツほどの凄い作品はシカゴの他の作品にはないよ。社会運動に参加して世の中を変えようとした若者たちの声が丸ごと音楽になってるんだ。これがロックなんだ!」。
 そう言いながら父は、レコード棚から黒いアルバム『シカゴの軌跡』を引っぱり出してきました。ですが私はすぐにそれを聞く気にならなかったのでレコード棚に戻してしまいました。レコードD面にあたる「1968年8月29日シカゴ,民主党大会〜流血の日(1968年8月29日)〜解放」というタイトルからしてアブナっかしい感じがしましたし、何しろグループそのものの名前が違ったのです。“シカゴ・トランジット・オーソリティー”が『シカゴの軌跡』を製作したグループ名でした…シカゴじゃねぇーじゃん!!
そう言いながら父は、レコード棚から黒いアルバム『シカゴの軌跡』を引っぱり出してきました。ですが私はすぐにそれを聞く気にならなかったのでレコード棚に戻してしまいました。レコードD面にあたる「1968年8月29日シカゴ,民主党大会〜流血の日(1968年8月29日)〜解放」というタイトルからしてアブナっかしい感じがしましたし、何しろグループそのものの名前が違ったのです。“シカゴ・トランジット・オーソリティー”が『シカゴの軌跡』を製作したグループ名でした…シカゴじゃねぇーじゃん!!
それから数年後、『シカゴの軌跡』を改めて聞いてみようと思う出来事がありました。どこかの雑誌の一部のコラムで「1970年前後はキース・エマーソンがオルガンでそれまで聞いたこともないような音を出し、シカゴのテリー・キャスも[フリーフォームギター]でエレキギターの可能性を広げたとか言われたものだが、今聞けばすべて雑音。そんな馬鹿げたものを世の若者がマジメぶって聞いていた、まことにおめでたい時代があった」といった感じの記述を読んで大いに興味を惹かれ、その“雑音”を聴いてみようじゃないか…と相成りました。ですが聴いてビックリ!素直に耳に馴染む優れた曲が、カッコいいサウンドに彩られて目一杯詰まっていたのです。…こ、これが「素直になれなくて」のシカゴの出発点か…。
オープニングの「イントロダクション」の押しの強さ、続く「いったい現実を把握している者はいるだろうか?」のしなやかなポップ・フィーリング、「ビギニングス」の爽やかさ。レコードA面でノックアウト寸前だ!しかもB面にひっくり返して針を落とすと名曲「クエスチョンズ67/68」が流れ出します。ブラス・ファンファーレと共に歌い上げられる華やかで美しいメロディーに、私はKO負けしました。前半4曲の流れは完璧、あまりに素晴らしい!
その後、アルバムは次第に暗雲立ちこめる世界に突入し、「フリー・フォーム・ギター」で若者の怒りと困惑が、不安と衝動に変化するかのような雑然とした心情がエレキギターの“音”と“フレーズ”で表現される…結構キテます!
そして最後の大作「1968年8月29日シカゴ,民主党大会」、「流血の日(1968年8月29日)」、「解放」の3曲は、怪しいタイトルとは裏腹の、カッコ良いブラスロックでした。
で、肝心の「フリーフォーム・ギター」なんですが、確かにノイズに等しいです。テリー・キャス(g)が一人でエレキギターのフリー・インプロヴィゼーションを聞かせているんですが、これが結構長いんです。メロディアスなアドリブじゃないので、少しばかり耐える事が必要になります。但し、気の向くままにフィーリングで勝手に弾いているというより、最初から明確な意図を持って音を出しているように聞こえ、非常にイライラしている感性が十分にくみ取れます。続く「サウス・カリフォルニア・パープルズ」を経て、スペンサー・デイヴィス・グループのヒット曲の爽快なカヴァー・ナンバー「アイム・ア・マン」(若き日のスティーヴ・ウィンウッドの作)に突入した時のカタルシスはたまらないものがあり、ロックって素晴らしい! と思わず叫んでしまうほど。プロデューサーのアルバム構成手腕の勝利です。
発言力のある音楽
『ヘロン』の項目でも触れましたが、どういった方法論であっても(フォークであれでロックであれ)“音楽”は常に“主張”すべきもの、というのが父の音楽芸術論でしたから、シカゴは正にその王道を行く [ロックの中のロック] でした。但し、シカゴにはオーソドックス且つモダンなジャズ・フィーリングを骨太ロックの上に塗した、アメリカらしいハイブリッド・ロックだったことは注目に値すべきで、そういう点で方向性は完全に逆ですが、英国のキング・クリムゾンの『クリムゾン・キングの宮殿』に同様の匂いを感じるのは私だけではないのではないかしら?
ただ世界的にみても社会に対してストレートに文句を言っているバンドや、混迷の時代に愛と平和を訴えるアーティストは多くとも、ロジカルに聞き手の知性とハートに訴えかけて世界中で受け入れられた社会派大衆楽団は、シカゴを置いて他にないんではないか? 何はともあれ、トランペット/トロンボーン/アルトサックスの独自の3ホーンを有し、ダニエル・セラフィン(dr)の4ビートの上でテリー・キャス(g)のロック・ギターが唸るという事自体が画期的だったのでしょうが、シカゴは極めてプログレッシヴなロックバンドだったと言えます。ただ、様々な音楽的ファクターを持ちながら飽くまで社会参画しようとする外向的姿勢が発言力のある音楽を形成し、社会との関係性よりも個人や集団の表現主義へと向かっていったプログレとは結果的に違う位置に立つことになります。

シカゴが行ってきた社会参画型音楽製作の集大成といいますか、その目的のフィナーレは大ヒット曲「サタデー・イン・ザ・パーク」(『シカゴV』に収録)にある事はリーダーのロバート・ラム(key,vo)もそれとなく口にしていますし、昔からのシカゴ・ファンの誰もがそう思っている事でしょう。ところがどっこい、この曲はウチのレコード棚にはなかった! なるほど、父は“シカゴ”が好きだったのではなく、“シカゴ・トランジット・オーソリティー”が好きだったんだ!
ブラスロックはNaoshismに如何に影を落としたか?
1970年代初頭、次々に台頭する新しいロック・サウンドに強い関心を示していた宮崎尚志ですが、意外なことにそれらの影響は、当時の父の作品にはほとんど感じられません。当時の膨大な録音を聞き返してもシカゴからの影響なぞ微塵も感じられない。又、父はキング・クリムゾンをブラスロックだと思って聞いていたのですが、その影響も皆無です。
これは歴史を振り返ってみれば簡単な話で、当時の日本放送業界/CM業界の勢いは、想像以上に凄いものでした。スケールの大きいジョークをやろうと「笑点音頭」(立川談志師匠が司会を務めた初代“笑点”の主題歌)のように大編成の録音を軽くやってしまう時代。音楽にかける予算が少ないから、演奏メンバーは4〜5人、且つビッグバンドに近い音を…みたいなクライアントの要求がない限りは、シカゴのような形態で音楽をやる必要がなかったのです。しかも自らが望むサウンドのためには作曲料(ギャラ)を注ぎ込んでまで優れたミュージシャンをかき集めさせた宮崎尚志ですから尚更です。
しかしながら時代は流れ、1970年代末になると業界も変化していく兆しが見られ、CMに限らず録音作品の多くがブラスロックではなくブラス入りのディスコになっていきました。父が自ら“ブラスロック”という方法論を敢えて狙ったのは1980年代半ば以降になってからで、大林宣彦監督との久々のコンビを組んだ角川映画『彼のオートバイ、彼女の島』(1986年製作。プロデューサー=大林恭子さんにとって最愛のサントラの1つだそうです)の音楽、そして1990年代初頭のCM「ロッテTOPPO」(稲森いずみさんのデビューCMにしてTOPPOの最初のCM)の音楽の2つです。『彼のオートバイ…』はレコード/CDで発売されましたし、映画もDVDになっていますので聞いて頂くのは簡単で、その方法論は時折ブラスロックの手法が匂うライト・フュージョンって感じに仕上がっているのは映画のイメージに沿った結果だったのでしょう。但し、ロッテTOPPOに関してはバリトンサックスまで含む、さながらタワー・オブ・パワーかジェリー・ヘイ・グループのような、これぞブラスロック(確かドラムはそうる透さんだったから尚更…)といったスリリングでインパクトのあるサウンドに仕上げていました。ここではお聞かせできないのが残念ですが…。
ブラスロックに傾倒していた宮崎尚志は、実はシカゴよりも深く聞き込んで研究していたグループがいくつかありました。いわゆるブラック・コンテンポラリーとファンク・ジャズです。そのお話はまた別項で。