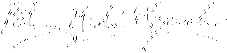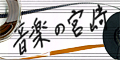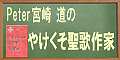希代の奇才の音楽に触れるには・・・
ポピュラー音楽の世界には“奇才”と呼ばれている人が存在します。多分、彼らは没後10年もすれば、無条件で“天才”に格上げされ、記録され、崇め奉られていくのでしょう。歴史とは、そんなものです。とはいえ、“奇才”の中には正真正銘の天才が大勢居て、それが如何なる種類の天才(人が天からの才を発揮するのには様々な要素が絡むのです)であれ、常にどこか時代とズレています。それがトッド・ラングレンのように「先読みによるズレ」であったり、E.L.O.のジェフ・リンのように「固有の音色を持つが故のズレ」であったりするワケですが、その“微妙なズレ”に大きな魅力があり、時代を超越する力があります。反対にそれが原因で取っつきにくい印象も与えてしまうのも事実です。私にとって、アル・クーパーは奇才ロッカー列伝の中でも高いランクに位置する一人で、一種独特のムードを持った“シンガーソングライター”でした。放っておいたら、現在まで聞くことはなかったかもしれません。ところがレコード棚にあったのです、『赤心の歌』が! 自分でアルバムを買うには相当な勇気がいるアーティストの音楽を、若いうちに聞くことが出来るのは、家にそれがあるということが非常に重要です。父が常に口にしていた「レコードは財産だ!」というのはホントですよ。
フィルモアの奇跡?
1960年代末、映画作家=吉川透さんの強い薦めで多摩芸術学園(多摩美術大学内にあった芸術系専門学校。現在、多摩美大に合併)の非常勤講師を始めたばかりだった父は、“ニューロック”と呼ばれていたロック・ミュージックのアルバムに興味があったようで、シカゴやピンクフロイドのように自ら買って所蔵しているレコードとは別に、何故かダビングされたオープンリール・テープも所有していました。それらは全て「多摩芸の誰かから、宮崎先生のために資料としてダビングしたから聞けといわれて渡されたモノ」だと言っていましたが、宮崎尚志先生という人は当時、ロックンロールな授業をすることで知られていたそうです。実際、1970年頃に多摩芸で宮崎尚志先生のクラスを取っていた方々から聞くところによれば、最初の授業にピンクフロイドの『原子心母(Atom Heart Mother)』を持ってきて、「これは素晴らしいから…」と言っていきなり全編聞かせ、アナリーゼをしたというエピソードがあります(映像理論を貪欲に学ぼうとする当時の血気盛んな学生にとって衝撃的な授業だったそうで、受講した学生の多くが『原子心母』を買いに走ったらしい)。
で、中学〜高校生だった頃の私はシンセサイザーに夢中で、電気オルガンは好きではありませんでした。古くてドン臭い感じがしたからですが、父が持っていたオープンリールにあったイエスの『時間と言葉』を聞いて印象が一変しました。ここで聞けたトニー・ケイ(key)が弾く、オーバードライヴしたハモンド・オルガンのロックな音色に魅了されてしまったのです。それを居間で聞いていたところ、父はおもむろに仕事部屋から出てきて、「道はハモンド・オルガンが好きか?」と言うのです。私は、好きではないのだがこのアルバムから聞こえてくる音には好感が持てる…と答えましたら、父はこう切り返しました。
|
これはハモンドらしくないなぁ。ホンモノの、すっげーいいハモンドのプレイが聞けるレコードがあるんだよ。マイク・ブルームフィールドだよ。こいつのハモンドはグっとくるよ、最高だよ。ハモンド聞くなら、ブルームフィールドが一番だよ! 宮崎尚志・談
|
父の話によりますとぉ〜、どうもマイク・ブルームフィールドという素晴らしいハモンド・オルガン・プレイヤー(?!)がいるそうでして〜、彼のバンドがアルバムを出しているらしい…。マイク・オールドフィールドなら知ってるが、ブルームフィールドなんて名前は聞いたこともない(勿論その当時の話)。
父はすぐに2本のオープンリールを引っぱり出して来ました。レコードからのダビングテープで、聞いてみるとライヴ録音でした。聞こえてくる音楽はドロドロのブルースっぽい…ハモンドは私の好きじゃないドン臭い音をしている。このバンドのギタリストは素晴らしいのに…。わー、こりゃーダメだ、ブルースは苦手なんだ!私は全てを聞かずテープを巻き戻して、すぐにワケを話して父に返しました。父は「そうかー、ブルームフィールドは好みじゃなかったか、残念だなー。」と言ってました。
実は随分後になって知ったのですが、このアルバムこそ名盤として知られるライヴ盤『フィルモアの奇蹟』であり、父が惚れ込んでいたハモンドを弾いていた人こそアル・クーパーでした(ブルームフィールドはギタリストだ!)。何か勘違いしていたようです。ともあれ、私は知らず知らずの内にアル・クーパーのプレイに出会っていたのでした…ドン臭いハモンドを弾くプレイヤーとして!
なんてぇ歌だ!
とはいえ、家にあった古いロック・アルバムを引っぱり出すと、レコードが入っている紙製の内袋(半透明のビニールじゃなかった)には、当時レコード会社がプッシュしていた色々なアルバムが、カタログとして印刷されていました。勿論レコード会社によって全く違うカタログになるワケですが、ニール・ヤング(「アフター・ザ・ゴールドラッシュ」!)やジェームズ・テイラー(「ベイビー・ジェームズ・テイラー」!!)やら、ブルースバンド時代のフリートウット・マック、日本のフラワー・トラベリン・バンドの「サトリ」、柳田ヒロなんかもありました。家にはCBS/SONYのレコードが多くあり、それ故によく目にしたのはアル・クーパーが自由の女神像になっている『アイ・スタンド・アローン』。このジャケットでニヒルな笑みを浮かべて、斜に構えた印象のアル・クーパーに、毎度のように「なんなんだこいつは?とても普通じゃない!」と、強く興味をひかれておりました。残念ながらそれは家にはなかったんですが。
しかし田園フォークバンド『HERON』が収まっていたレコード棚の一角に、Al Kooperの名のあるレコードを1つ、見つけました。タイトルは『Naked Songs』とあり、なんというゴイスな(?!)アルバムタイトルだ!と思ったものです。いきなり“裸歌集”!なんスかそりゃー。ただ、こんなアルバムはカタログの中にも見たことがない。人気のないマイナーな作品なんだろうか?と思いつつ、ジャケットを開いてみると、1曲目の「あなた自身でありなさい(Be Yourself,Be Real)」という曲名に心惹かれました。これは、ゴスペルだろうか?気になってしょうがなくなり、レコードをプレイヤーに乗せて、針を落としてみました。
聞き始めてビックリしました。囁くようであり、語るようであり、時に力強く、しかし消え入りそうなほど頼りなくなったりする、それはそれは危なっかしい(音程も危なっかしい)歌声が聞こえてきたのです。80年代半ばのヒットチャート・サウンドに聞き親しんだ私の耳にしてみれば、こんな歌にはお目にかかったことがないほど(『HERON』に匹敵するほど)、正直、全然上手くない!
っていうか、歌ヘタ過ぎ!!
こ、このヘタクソが奇才と呼ばれるアル・クーパーなのか…。しかし「あなた自身でありなさい」の曲の良さは格別で、しかも歌詞の一つ一つが心に残る、強い説得力がありました。又、シンセサイザーで奏でるカウンターラインが素晴らしく、決して目立たないのにサウンドの盛り上がりや厚みを演出するハモンド・オルガンの入れ方など、全体のサウンドはキレイにオーケストレイトされた印象を持ちました。一曲目を聞き終えた直後、私はまず、この曲が大好きになり、アル・クーパーの不思議な魅力(歌以外で!)に酔いました。
しかし次の「時の流れるごとく(As The Years Go Passing)」がドロドロのブルースで、レスリーを効かせたドン臭いハモンドが聞こえてきた瞬間、うわーっ!苦手だー!と、折角の好印象がメチャメチャに。しかも掻きむしるようなブルース・ギターがアドリブで大暴れする。ところがクレジットを見ると、ハモンドもピアノもギターも全て、アル・クーパーの多重録音演奏によるもので、これにまた驚いた!ギターも上手いキーボーディストなんて、そんなのアリか?!
なーんて思っていたら、3曲目の「ジョリー(Jolie)」が始まった…モロにニューミュージックなイントロでガーンとなり(レコードをかけ間違えたかと思った)、抜群にポップでキャッチーな歌メロ、職人的な“おいしい”アレンジにブっ飛びました。なのに4曲目「ブラインド・ベイビー(Blind Baby)」はフィドルが聞こえてきて、まるでビートルズが暢気にケイジャン・ミュージックやってるみたいな曲。このアルバムはリスナーの期待と予想をことごとくハズすような、意外な展開でグイグイと引っ張ります…というか、一歩間違えれば“メチャクチャ”です。
アルバムは1972年という時代ながら、まだ出始めだったシンセサイザーの使い方が驚くほど上手く、アンサンブルの一部としてガッチリと機能しており、ミックスも「シンセサイザーを使っているんだゼー、ほらこれだゼー、よく聞けよ!」といった押しつけがましさは一切ない、卓越したサウンドメイク・センスで独自の世界観を作り出していました。特にベテラン・アレンジャーが編曲したんじゃないかと思うほどナチュラルで手慣れた「ジョリー」はダントツの出来で、フレンチホルンとグロッケンシュピールのユニゾンによるアクセントは、ここぞ!という箇所に登場します。何とこれがアル・クーパー自身の編曲と演奏だとクレジットされていて、また驚いた。コイツは本当に凄いんだと感じたものです。押しと引きのバランスが絶妙で、風格すら漂っています。今聞いても、抜群のセンスは普遍ですよ。
一聴して「ジョリー」は大ヒット・シングルだと直感しましたが、古いヒットチャートを調べても、オリヴィア・ニュートン・ジョンの「ジョリーン」ならありましたが、この曲は出てこない。どうやらシングルでもなく、ヒット曲でもなんでもなかった…なんでこんな極上のポップソングがシングルになってないんだ?と首をひねったものです。最近になって知ったのですが、当時の日本では頻繁にラジオで流されていたため、ある世代には深く愛されているラジオ・ヒットなのだとか。なるほど、後の日本ニューミュージック・シーンへの多大な影響を感じます。
で、このアルバムについて父に聞いてみたところ、「?…そのレコードは聞いた覚えがないなぁ。多摩芸の誰かからプレゼントされたものだと思うんだけど。そういうのいっぱいあったんだよ」。…『フィルモアの奇蹟』のハモンド・プレイヤーのソロ・アルバムだぞ、そりゃーねぇだろー、名曲「ジョリー」が入ってんだぞ、ちゃんと聞けよー!と思ったものの、父が大好きだったであろうクーパーのハモンドのブルース・プレイを存分に聞かせる箇所がほとんどないので、残念ながら全く記憶に残らなかったのでしょう。
宮崎尚志のハモンド史:“夜の名奏者”=泉氏との出会い
宮崎尚志は、実は達者な“電気オルガン奏者”でした。立教大学時代にトーマス・カーサー氏(立教学院の先生)に師事(?!)、本場アメリカのジャズ、それもカウント・ベイシーのピアノ・スタイルを教えられ夢中になり、腕を磨いて銀座のナイトクラブでジャズピアノ弾きとしてアルバイトをするようになります(この時に「偽レナード・バーンスタインによるサイン強要事件」に遭遇します。詳しくは「ジョージ・ガーシュウィン追悼コンサート」の項目を参照)。一方でベイシーがハモンド・オルガンも達者に弾くと知るや、父も「彼のように弾きたい」と思ったらしく、ピアノよりもオルガンの方が上手かったカーサー氏に相談。すると…
|
ハモンドを弾くには足鍵盤を使いこなすことが基本なのだ。 左右の足首を自由に動かせるようにするのだ。 そのために、まずタップダンスをやるのだ! by トーマス・カーサー
|
…とのこと。それでタップダンスまでかじったとか。そのお陰でペダルも器用に使える電気オルガン・プレイヤーになり、ジャズ・ピアニストだけでなく、隣のクラブをハシゴしてオルガン弾きもやっていたとか。
そんな中、別のクラブで弾いていたハモンド・オルガニストのプレイに衝撃を受け、顔パスでそのクラブにタダで入って聞きにいくほど通い詰めました。プレイヤーのお名前は“泉さん”といい、ハモンド奏法で最も影響を受けた人物だと言いました。
この泉さん、父はプレイを聞いただけで一度も話した事がない。つまり面識はなかった。今はどうしているか判らないということでしたが、奇しくも約30年後、直接出会うことになります。1980年代末、多摩美術大学に新たに設置される映像・音楽用のスタジオに関し、シンセサイザー等の相互通信のためのデジタル・ディバイス=MIDIで全ての機器を繋ぐ“MIDIスタジオ”にと提案、そのシステム構築の可能性について美大の教授陣と共にRolandへ出向き、同社の取締役・則安治男氏にお話を伺いました(私も同行した)。会合で則安氏と対面した、父は急に「失礼ですが、昔、銀座の『○○○○』でハモンドを弾いてらっしゃった、泉さんではありませんか?私は『××××』でピアノを弾いてましたが、泉さんのハモンドがあんまりに素晴らしいので何度も聞きにいったんです。」と父が言い出すと則安氏は笑顔で「はい、遙か昔のことですが…今はこんな感じで人前では全く弾いてないんですが。よく覚えてらっしゃいましたね!」と。そしてお二人は暫しの間、美大教授陣がポカーンとしているのも関係なく、華やかなりし頃の銀座クラブ談義に花を咲かせたものです。
さて話は戻りますが、トーマス・カーサー氏の特訓、泉さんのプレイから盗んだワザを実戦で鍛えた腕をもって大学卒業後に作曲家として一本立ち、ラジオの生番組をはじめ、NHKのTV実験放送(試験放送)などのBGMの“生付け”でスタジオにあるハモンド・オルガンを自ら即興で弾きました。この仕事は作曲家であると同時に、即興に長けたプレイヤーであるという両方の資質を必要とするものだったそうで、独立したベース・パートを足(ペダル)でまかえる上、音色のヴァリエーションがある2段鍵盤オルガンの方がピアノ・ソロよりも適していたとか。もっとも、電気オルガンはまだまだ“最先端のサウンド”だった時代で、しかもその斬新な音色をたった一人で操る(演奏メンバーを複数人雇わなくて良いから安上がり)のですから、番組プロデューサーとしては使いたがったのでしょう。
そんなワケですからハモンド・オルガンについて熟知しており、そのサウンドメイクの奥深さを思い知っていましたので、電気オルガンには滅法うるさい男でした。私が幼い頃、家には茶色のエレクトーンがありましたが、「ハモンドB3は大きいし、重いし、家に置くスペースがなかったから欲しくても買えなかった。でもスタジオには大体あるからいいんだ。」と言っていたものです。後にヤマハのコンボオルガン=YC-45Dを急に手に入れたのは、ハモンド・オルガンに非常によく似たサウンドを出せたからでした。(この話は“T-CONNECTION”のコーナーで詳しく書いていますので、宜しかったらお読み下さい)
その宮崎尚志がカウント・ベイシーに継いで惚れ込んだハモンド・オルガニストは、かのジミー・スミスではなく、アル・クーパーだったというのは実に興味深い。クーパーは俗に言う“スーパー・キーボーディスト”とは呼ばれることはなく、プロデューサーとしての評価が圧倒的に高いアーティスト。プレイヤー馬鹿ではなかったことが、かえってサウンドとフレーズに対するセンスを研ぎ澄ます結果になり、ボブ・ディランの「ライク・ア・ローリング・ストーン」や「我が道を往く」などの、味があって独創的なプレイになったのでしょう。父はアル・クーパーのそういうところに共鳴したのかもしれません。そういえばもう一人、父が好きなロック系オルガン弾きがいました。ピンク・フロイドの故リック・ライトです。派手な弾きまくりタイプのジョン・ロードやキース・エマーソンじゃないってところに、父の趣味が出ているなと思います。
こんな事書いていたら、久々にアル・クーパー聞きたくなっちゃったなぁ。でも、今もやっぱり、『赤心の歌』での歌声はヘタだと思いますよ。でも聞けば確実に言葉が心に届くんだから、やっぱりアル・クーパーの歌は「いい」のだと思うんです。上手いとか下手とか、時にそういった理屈なんかブっ飛んだところに「伝わる」バイブレーションがある、それが音楽の不思議さでしょうね。科学的に言ったって音楽って空気振動による伝達、即ち“バイブレーション”なんですからねぇ。