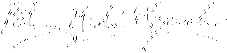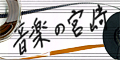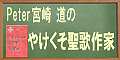Powerd by
sogaku.com
宮崎尚志のレコード棚
ジョージ・ガーシュウィン
『The Historic George Gershwin Memorial Concert』
Hollywood Bowl September 8,1937

SIDE-A
1. Prelude No.2 (arr.: Otto Klemperer)
2. Concerto in F-1st movement: Allegro(pf: Oscar Levant)
3. Song Group
a) Swanee (Al Jolson)
b) The Man I Love (Gladys Swarthout)
c) They Can't Take That Away From Me (Fred Astaire)
SIDE-B
1. excerpts from Opera "Porgy and Bess"
a) Introduction and Summertime(Lily Pons)
b) My Man's Gone Now (Ruby Elzy)
c) Buzzard Song (Todd Duncan)
d) The Train Song (Anne Brown)
e) I Got Plenty O' Nuthin' (Todd Duncan)
f) Bess, You is My Woman Now (Todd Duncan)
g) I'm On My Way (Todd Duncan)
唯一の「聞いてはいけない」レコード?!
父はレコード棚にあるものは全て自由に聞いて良いと言いましたが、その中でずっと以前から唯一、絶対に手を出すなと念を押されたレコードが存在しました。1937年9月8日、ハリウッド・ボウルで行われたジョージ・ガーシュウィン追悼コンサートの模様をダイジェストで収録したこのレコードです。この日、ステージに登場したアーティストはスゴい。オスカー・レヴァント、アル・ジョルスン、フレッド・アステア、オットー・クレンペラー…錚々たる面々。父はこのレコードこそ家宝であると豪語しました。家宝だからレコード針を落としてはいけない、即ち「聞いてはいけない」のです。ですから父はこのレコードに収められているものについて、蕩々と語ることが何度もありました。でも百聞は一見にしかずっていうだろうに…。
ジョージ・ガーシュウィンが亡くなった2ヶ月後に開催された追悼コンサート。アメリカン・クラシックス&オペラのオリジネイターであり、ポップソングのヒットメイカーであり、超売れっ子ミュージカル作曲家であり、映画音楽家であり、なによりも名ピアニスト。“音楽に貴賤はない”事を実践した比類なき偉大な現代作曲家の追悼コンサートに相応しく、あらゆる音楽シーンのトップ・アーティストがこぞって参加した画期的且つ歴史的なステージ…。そんな事を言っていた父も亡くなってしまったので、「宮崎尚志のレコード棚」の話のネタとして、今回初めてその禁断の家宝レコードを聞いてみようじゃないか!

と思ったら…あれ?この輸入盤、まだ封を切ってないよ!2,300円とか、値段まで付いたまんま。なんと封を切ってもなかったのだ!一度も針を落としていないどころか、このレコードは購入してから何十年も、ビニール・ラップされたままの状態でレコード棚に保管されていたのだ!新品同様となると、これではサスガに今でも追い逸れと聞けない!!っていうか、父はこの録音を聞いたことがあったのか?いや、聞いたことは間違いなくあっただろう。しかし話のネタが…。
仕方なく、その録音がCD化されて流通していないか、ネットで探してみる。すると、あったあった!2枚組のボリュームでコンサートの模様を全収録したCDが出ている。CD化されているなら少しぐらい、ウチのレコード盤より音も明瞭になっているだろう、これは買いだ、早速カートに入れよう。しかし、あれあれ? 期待も虚しく、とっくに廃盤。世界中のネット・ショップを探しても、全て売り切れ御免の状態。中古すら出てない。あらら、話のネタが…。
仕方ない、ラプソディー・イン・ブルーにまつわるNaoshismなエピソードを書きつづるとしましょう。その点についてはネタに事欠かない。しかし、つまみ食い的な宮崎尚志ヒストリーになるので、今回は長編になると思います。御覚悟願います。
終戦後、GHQのレコード・コンサートで
まず最初に、ジョージ・ガーシュウィンの「ラプソディー・イン・ブルー」というピアノ狂詩曲そのものが、宮崎尚志を生涯、音楽の虜にした事実を挙げておかねばなりません。
この作品に接したのは、宮崎尚志が中学の頃。終戦直後にGHQが日比谷公園のような公共の場で屋外レコード・コンサートみたいなことをやっていたそうで(※脚注1)、それを父親=宮崎豊文牧師(私から言えば祖父)と聴きに行って、初めて耳にしたそうです。宮崎豊文は日本基督教団・富士見町教会の副牧師で、扁平足である上に肺結核を煩って肺の機能が通常の1/4しかない事から兵員として不適切とされて徴兵を免れ、終戦後には葉山伝道所(現在の葉山教会)に無給の非常勤牧師として掛け持ち赴任していました。故に貧しく、生活費を得るために駐留米軍の通訳という職を得ていました。牧会や礼拝など、教会での仕事以外は米軍の基地に通っていたという話ですから、そのレコード・コンサートについてもよく知っていたのでしょう。又、もともと豊文牧師はアメリカ贔屓で、そんな父親の影響もあって長男=宮崎尚志のアメリカへの強い興味は、少年時代から潜在的にあったようです。
※脚注1
これについては開催場所を聞き落として、忘れてしまいました。父は“公園、屋外”と言ったのは確かですが、岩城宏之さんなど同年代の方々で同じような体験をした方には、GHQが持っていた建物の音楽室のような場所で行われていたとか、諸説色々ありそうです。
|
戦争中は空から焼夷弾を平気で落としてくるアメリカ人ってのは、なんてヤツらだろうと思ってたんだ。けれどあの東京の大空襲の時に、空からバラ蒔かれたビラを読んだときに、その認識が180度変わったね。大空襲って1回だけじゃなかったんだよ、知らないだろう? 他ではどうだったかよく知らないし、そんな事が歴史教科書には出てこないから判らないけど、少なくともボクが住んでた池袋(東京)ではそうだった。 大空襲の前日だったか、低空で飛んできた米軍の飛行機の後から降ってきた紙吹雪に、近所の子供達は大喜びしたけど、読んでみたら大規模な空爆の予告だったんだよ。何時々々、大規模な焼き払いをする、けれど焼かない場所が明記されていて、一般市民はそこに避難するように書いてあったんだ。米国ミッションの立教学院の敷地と、負傷した米軍捕虜が収容されていた目白の聖母病院は焼き払わないって書いてあった。ただ誤爆だったのか立教の敷地内で、裏の方にあった聖公会神学院を丸々焼いちゃったけどさ(注:飛行機が墜落炎上したという説もある)。でね、その飛行機を追い掛けるように日本軍の兵隊がやってきて、敵の言うことなんかに耳を貸すなとかなんとか叫びながら、ビラを全部回収しはじめた。小さい子供が持ってるビラも、拳骨でぶん殴ってまで強引に回収するのを見たよ。でもボクはそれを隠し持って家に帰った。で、その予告日に警報が鳴って、空いっぱいのB-29が遠くから編隊組んで飛んでくるって言うんで、ビラに書いてあった避難場所の方角に近所の人達と一緒にボクらは向かってったんだよ。そしたらあちこちに日本兵が立ってて、おまえらどこ行くんだ、避難場所はあっちだ、と叫んで誘導してるんだけど、その場所ってビラでは空爆エリアん中で、行ったら絶対にダメだと直感で思ったから逆らって向かったんだ。 B-29が通り過ぎて、避難命令が解除されて帰宅の許可がおりたんだけど、ウチの近辺は焼けずに残ってたから嬉しかったな。けど池袋の方面を見たら一面焼け野原でさ。あるはずの建物が全部なくて、見渡す限り真っ平ら。ウチから見えるハズのない王子の“王様クレヨン”の煙突までハッキリ見えたんだよ。その手前に立教、目白の方角に聖母病院が立っているのが見えた時、激しい戦慄を覚えたね。ほとんど予告通り、正確に爆弾を落としていったアメリカ軍を敵に回して戦っているこの戦争に、あのビラを血眼になって回収するために自分の国の子供を拳骨でぶんなぐるような、ちっちぇー(=小さい)ことやってる日本軍が勝てるハズがないって。ハナっからやることのスケールが違う。しかも日本兵が誘導した避難場所に行った人達には、結局帰ってこなかった人がいると聞いて、尚更それを強く思ったんだ。一億玉砕なんて冗談じゃない。とっとと白旗挙げて、戦争が終わればいいなって毎日神様に祈ってたよ。だってそうなれば、デッカいスケールのアメリカに、自由に行けるようになるじゃないか!。 (宮崎尚志・談)
|
そして宮崎尚志は、父親に連れられてフリー・レコード・コンサートのようなものに出向き、「ラプソディー・イン・ブルー」を初めて聞くことになります。
|
レコードが流れてくるスピーカーっつったって、今のPAみたいなイイものなんかじゃないんだ。ラッパ・スピーカーのヒデぇヤツみたいなので、壊れた蓄音機みたいな音してた。親父としちゃぁ〜、ボクらが家にいても貧乏牧師の家庭だから何にもないし、敗戦国ってことでどこかのアジア系の人達が白昼堂々と金品奪いに押し入ってきて…そう、今で言えば外人強盗団だよ。戦後はそんなことは日常茶飯事だったんだよ。そいつらが、親父がふせって寝てるのに蹴飛ばしてね、寝てた布団まで全部持ってったりしたから、気落ちしてたボクを少しでも楽しませようと思って連れてってくれたんだろう。色んな音楽が流れてきたな。そんな中で『ラプソディー・イン・ブルー』が始まって、ボクはそれが終わるまで、完全に釘付けになったんだ。そりゃーもう金縛りみたいに、身動き一つ出来なかった。なんなんだ、この音楽は!聞いたこともないサウンドだ!ってね。そうこうしてるうちに中間のアンダンテになって…夕暮れ間近だったかな、野っ原に色んな人達がそれぞれに座ったり寝ころんだり、その風景に音楽が溶けていくようで、まるで総天然色の映画かと思うような美しい、幻想的な風景に見えてね。なんてステキなんだって身震いしたんだよ。曲が終わって興奮さめやらぬまま、隣にいる親父にその曲の感想を聞こうとしたら、寝転がってぐっすり寝てやんの。まったく、なんだってぇ〜の。 この曲が“アメリカン・シンフォニー(アメリカ交響楽)”って名付けられるハズだった『ラプソディー・イン・ブルー』って曲だって知ったのは、後になってからだったかな。それを作曲したのがジョージ・ガーシュウィンっていって、流行歌の作曲家だって聞いて、またビックリした。流行歌作家がクラシックもやっちゃうアメリカって何てスゴい国だ、こんな国と戦争してたなんて、(日本人である)自分がまるで何も知らない馬鹿みたいで、情けなくなっちゃった。でもその日、確かにそれまでの自分の価値観が完全にひっくり返った。 (宮崎尚志・談)
|
父親を尊敬してやまない長男=宮崎尚志は、その頃はまだ自分も牧師になるという志を強く持っていました。学校の仲間達と“人形劇団ポプラ”を結成し(この時に人形の製作術を学ぶため、人形劇団プークの故・川尻泰司氏の元を訪れ、以来生涯に渡ってのプークとの親密な関係がはじまっています)、脚本・演出・音楽に出演までこなしながら北海道遠征ツアーまでやった(この一件は新聞で大きく報道された)にも関わらず、全ての行動は牧師への道だと信じていました。宮崎尚志が常に見つめていたのは、結核によって肺機能がほとんど失われ、医者からは余命も僅かと宣告されていたにも関わらず、バイタリティー溢れる行動力で積極的に宣教し、教会の信徒や支持者から食料品の差し入れがあれば、近所に分けてしまうようなストイックさを常に発揮し続けた父=宮崎豊文牧師の背中でした(宮崎豊文牧師はその余命宣告から約30年も生き続け、1981年に没しています)。
しかし育ち盛りの息子2人を抱える宮崎豊文一家、やはり米軍基地での働きで得る収入だけでは食に事欠いてしまったのも事実。母親も質屋に着物を入れたりして日々の食費を工面をしていましたが、売るモノがなくなってしまってはいけないと、長男=宮崎尚志は年齢詐称して夜の街にアルバイトに出ます。友人から「練習して上手くなりたいから」と拝み倒して借りたアコーディオンを背負い、深夜のバーを回って演奏しては日銭を稼ぎ、そして立教大学英文科へと進む頃にはジャズ・ピアノもイッパシに弾けるようになっていました。本人曰く“自分は歩くジュークボックス”だったと。
|
音楽は、それが一家を支えるための稼ぎの手段だった。志はあくまで牧師でね。でも大学卒業まであと1年ぐらいのある日、恩師のファータケ(ファーザー竹田鐵三。戦前戦後に渡って長く立教大学チャプレンを務めた名物神父)から、お前は牧師になっちゃダメだと言い渡されてね。牧師になるために頑張って生きてきたのに、なんだそりゃって。なんでそんなことを今頃言い出すんだ、ボクは牧師になるために立教大学に入ったんだって詰め寄ったら、牧師は貧乏だから二代続くと家が潰れる、病気の親父さんとお袋さんを支えていく為には別の仕事に就く方が正しい、と言うんだ。でも何をやったらいいのかとファータケに聞いたら、お前はピアノが上手いし作曲も出来るから、音楽をやればいいじゃん、とか言うんだよ。そんな事考えたこともなかったから、すぐにはわからなくてね。音楽やるには、音楽の勉強をしなくちゃいけないって思ってたんだ。いっそのこと、ガーシュウィンに習いにアメリカに飛んでいきたいと思ったぐらい。けどガーシュウィンはとっくに死んじゃってるから、個人レッスンで芸大教授の島岡 譲さんに和声を習いに行ったりしたんだ。島岡さんはフランス和声学の権威でね、ほら、ガーシュウィンもパリにオーケストレーション習いに行っただろ?ミヨー(ダリウス・ミヨー)にさ。芸大なんかはドイツ和声を教えてたけど、ボクはガーシュウィンと同じフランス和声で習いたかったんだっていうのもあったんだよ。。 (宮崎尚志・談)
|
芸術作品もCM音楽も創作上での精神性は同一である
少年期の父が「ラプソディー・イン・ブルー」から受けたインパクトは、成人した後、果たしてガーシュウィンのような音楽家として生きたいという熱い思いになり、「音楽に貴賤なし」、「芸術がもたらす最高のものは感動である」という“Naoshism”の基本理念が自ずと形成されました。それは即ち、ジョージ・ガーシュウィンの音楽家としての生き様からの学びに他なりませんでした。ジャンルのない創作活動を行うこと…それは逆に言えばオール・ジャンルに亘る活動にもなりましょう。父は、人形劇団ポプラで培ったトータルなドラマ製作のノウハウを持った音楽家として、当然のように放送業界へと進んでいきました。まずはラジオで活躍、そしてテレビの実験放送へと。その後、たまたまCM音楽で名を成すに至ります(あ、CMにクレジットはないから、名前は知られちゃいないか…)。
|
「小生の基本理念は、作品に於けるCMであろうと芸術作品であろうとその製作態度に変わりはない…その境目はいささかも置かぬのが主義。自己の主張を他人に訴求するという部分で、本質に違いはないから、という考え方をもち続けて来た。」 。 (CM理論メモ「イントロダクション」より)
|
やっぱりオスカー・レヴァントだね
「ラプソディー・イン・ブルー」を自らの音楽のバイブルだとする父ですから、この曲のレコードは棚の中に幾つかありました。とは言うものの、この曲の演奏について常に言うことといえば「オスカー・レヴァントの弾くラプソディー・イン・ブルーの右に出るものはない!」でした。映画『アメリカ交響楽』と『巴里のアメリカ人』が大好きで、両映画に出演もしているオスカー・レヴァントを画面の中に見る度に「オスカー・レヴァントっ!」と叫んでいたものです。ですからレコードは古い録音ばかりでした。
1980年代半ばにコンパクト・ディスク(CD)の時代に入り、宮崎家の居間のステレオ・セットにもCDプレイヤーがセットされました(PioneereのLD/CDコンパチブルプレイヤーだったんですがね。2度ほど修理しましたが、今も動いてますよ)。その折り、音楽ソフトとして真っ先に買ってきたのは、フィリップ・アントルモン(pf)をソリストに迎えたユージン・オーマンディ指揮・フィラデルフィア管の「ラプソディー・イン・ブルー」が入ったCDでした。1967年の録音にも関わらず、何しろムチャクチャ音質が良いので、私も一緒に何度も聞きました。アントルモンのピアノをこれで初めて聞いたのですが、徹底してクラシック作品として弾いていて泥臭さが皆無、オーケストラとの呼吸もバッチリで、素晴らしいバランスを持った“クラシックな演奏”でした。父は「気に入っているとは言えないけど、今までに聞いた中では一番まとまりが良い演奏だね。ノーカットだし。」と言ってました。
その直後、父の知人の誰かが「ラプソディー・イン・ブルー」の最高の録音・最高の演奏が入っていると、映画『マンハッタン』のサウンドトラック盤をプレゼントされました。ゲイリー・グラッフマン(pf)をソリストに迎えたズービン・メータ指揮、ニューヨーク・フィルハーモニックの演奏。これについて父は「うーん、最高じゃないなぁ。けどニューヨークの匂いは強いね。都会的だ。」と言っていました。
暫くして近代作曲家の自作自演を記録したSPレコードからのCD復刻版が出回るようになってきて、ガーシュウィン没後50年を記念して『ガーシュウィン自作自演集』が出ました。これは私が買って父にプレゼントしたものですが、ガーシュウィンをソリストに迎えたポール・ホワイトマン楽団との演奏録音で、1927年のもの。こればかりは父も初めて聞いたものだったらしく大変喜んで聞いていました。生涯の憧れの作曲家の自作自演を聞くというのは、さぞかしワクワクしたことでしょうね。しかも、ガーシュウィンのピアノは本当に上手かったし。[※追記:ガーシュウィン自作自演録音盤は既にLPで所有しており、初めて聞いたわけではなかったようだ]
続いて、カメラ店なんかにも置かれていた廉価盤のクラシック名演シリーズの中から、バーンスタインがコロムビア交響楽団を弾き振りした1967年の録音を収めたCDを買ってきました。これはレコードで既に持っている録音と同じでした。理由は簡単、「安かったから」。
CDで4種類を持っていた父に、演奏としてどれが一番好きかと訪ねたことがあります。するとやはり「バーンスタインだな。素晴らしいよ、このレコード。バーンスタインのピアノはサバ読みが多くて全然ウマかないけど、感動的なガーシュウィンなんだよ。」といった答えが。そして宮崎家では毎度お馴染みでもある、レナード・バーンスタインとの出会いのエピソードが続くのです
バーンスタインに見初められて…?
20歳そこそこの若き宮崎尚志は家計を支えるため、銀座の会員制高級クラブのピアノ弾きをやっていました。米軍の将校などがよく訪れる場所だったので、ジャズ・ピアノを弾いていたそうです。ある日、アメリカのオーケストラが来日し、そのスタッフらしき人々がクラブにやってきたそうで、若い指揮者らしい男の周りには取り巻きが数人くっついて移動していたとか。取り巻きの中央で殿様のようにワハハと笑ってるその若い男を見て、父は「いけすかねぇ〜野郎だ」と感じたので、いつになく騒々しい周囲に気を取られずにピアノに集中したんだそうです。しかも激しいブギウギなんかを暫く弾いていたら、その“いけすかねぇ〜野郎”がおもむろにピアノに近寄ってきて(取り巻きも一緒にくっついて)、
「お前のジャズ、エラく上手いな。よし、ゴキゲンな演奏を聞かせてくれたお礼に、今度はオレ様が弾いて聞かせてやるぜ!」
…と話しかけてきた。なんなんだコイツは!と思いながらもピアノを譲ると、取り巻きは一気に興奮状態。その男は意気揚々とジャズを弾き始めたのですが、父曰く「これがスンゲぇ〜下っ手くそなの。もう忘れちゃったけどクラシック曲も弾いてたな。クラシックは上手かった」。
少し弾いて、取り巻きによるお約束の大喝采を受けて上機嫌のその男は、ピアノから立ち上がって席に戻るかと思ったら戻らない。「早くどいてくれよ、ボクはこのピアノを弾くのが仕事なんだからサ、って思って、こっちは不愉快だったワケさ。でもそいつが、なんかキョロキョロしはじめて、側にいるヤツに何か言い始めたんだ」。その途端、取り巻きが一斉にザワザワしはじめ、通訳らしき人が血相を変えて父にこう言ったそうです。
「君っ!この方はアメリカの大指揮者であり作曲家でもある。求められても滅多にサインをしないこのお方が、今、自ら君にサインをしてあげたいと言っている。こんな事ははじめてだ。この栄誉を君は無条件で受けるべきだ。君、何か書くものを出しなさい!」
父は丁重に「そんなモン、いらないよ」と答えたそうですが、取り巻きはもう聞く耳持たずの興奮状態。このままでは収集付かないので渋々OKすると、その男はテーブルにあった紙ナプキンか何か(紙切れの切れっ端みたいなものだと父は言っていた)にサインをし、父にプレゼントしたとか。その男は最後に「お前、いつかアメリカに来い。」と言って帰っていったそうです。そのサインの人物こそ、レナード・バーンスタインだったというのです…ホントかぁ?!
当時のバーンスタインは、ブルーノ・ワルターの代役でニューヨーク・フィルを振ってオーケストラ・シーンに登場した全米注目の若手指揮者であり、ミュージカル『ウェストサイド物語』を書く前だったので、作曲家としては名が知られていたとは言い難い。だから父もレナード・バーンスタインという名はまるっきり知らなかったんですって。しかもサインになると、普通では読めなかったりする。だから「一体誰だったんだコイツは?」という感じで、無理矢理貰ったサインは家に持ち帰り、しばらく机の上に置いておいたらしい。本音では、ジャズの本場=アメリカの音楽家らしき人物から「お前のジャズは良いぜ」と言われたことが一番嬉しかったのでしょうけど。
そのうち、ミュージカル『ウェストサイド物語』でバーンスタインは作曲家として大ブレイク、シェークスピア悲劇的な現代アメリカン・ミュージカルとして、日本にもその作曲者レナード・バーンスタインの名は即座に広まりました。「作曲者の顔に見覚えがあったし、勿論サインの形にも。で、スコアの間に挟んで積んでおいた例のサインを出してきて見てみたら、まるっきり同じでやんの!」。
その直筆サインは、旧宮崎邸(池袋・要町)最上階の3F倉庫に、膨大な譜面類と共に保管されている…と言われて久しいのですが、残念ながら私は一度も見たことがありません。又、旧宮崎邸は1980年代末に大型台風による突風で屋根が飛び、倉庫の譜面が雨ざらしになるという大被害を受け、その際に多くの古いスコアが破損、又はシミだらけになるほど汚れてしまいました。その中にサインがあったことは父の証言からは間違いないようです(サインは未だに行方不明です)。
映画好きの私ら息子たちは「それってエルマー・バーンスタインじゃないの?十戒だ!ユル・ブリンナーだ!」とか、「バーンスタインのそっくりさんが来て、どっきりカメラやってたんじゃないの?肝心の本人の知名度が日本ではそれほどでもなかったから、空振りに終わったってオチで…」などと言って、父をからかったものです。
|
※追記 このエピソードを改めて再考してみますと、父がまだ20代そこそこの頃、レナード・バーンスタインが来日したという公式な記録は残念ながらありません。又、ミュージカル『ウェストサイド・ストーリー』を書く前となると1957年以前であり、その頃に海外の交響楽団が来日した記録を手繰ってみると、めぼしいものといえば1955年のアメリカのシンフォニー・オブ・ジ・エアー(アルトゥーロ・トスカニーニのNBC交響楽団の後身)、1957年のヘルベルト・フォン・カラヤン率いるベルリン・フィルぐらいか。そうなると、やはりシンフォニー・オブ・ジ・エアーが間違いなさそうで(アメリカのオケですし)、1955年5月頃ということになります。しかし、この日本初の海外オケの大規模ジャパン・ツアーにはバーンスタインは同行していません(トスカニーニも同行せず、代わりに3人の指揮者が交代で振ったらしい)。その当時のバーンスタインは、シンフォニー・オブ・ジ・エアーの前身であるNBC交響楽団の宿敵、ニューヨーク・フィルの副指揮者。では当時、“偉大な作曲家”といわれるに相応しいと思われるアメリカのマエストロをあたってみると、丁度シンフォニー・オブ・ジ・エアー初来日公演に指揮者として同行した、「交響曲第5 1/2番」のドン・ギリス [Don Gillis]ではないか?という気もしてきます。父の話に出てくる“レナード・バーンスタイン”は、実はドン・ギリスだったのではないかと。しかしそれを検証することも、タチの悪いアメリカ人のドッキリだったかを証明することも、残念ながら今や出来ません。肝心のサインも見つかってませんしね。 |
日本の音楽教育は極端に偏っている
父は俗に言う“エリート”というものの必要性は認めてはいましたが、“エリート意識”については断固嫌いました。詳しくは多岐に渡るので省略しますが、結論の1つを申しますと、その意識を強く持つ者のほとんどが“タイトルだけを欲しているような卑しさの発露”だと言うのです。故に名誉欲を排し、TVに顔を出して自分自身を売ることを頑なに拒み(出演した番組はごく僅か)、教壇から生徒に向けて極めてストイックな芸術精神論と、独自の哲学(="Naoshism")を35年に亘って叫び続けました。そんな父=宮崎尚志が常に憤慨していたのは、クラシックという“枠組み”でした。
そもそもルードヴィッヒ・フォン・ベートーベンが楽聖とされて現在も尚、崇められている事に疑問を持っていました。「ベートーベンってぇ〜のは、現代に於いてはそれほど大したことないっていうふうに、どうしていつまでたってもならないんだろう?」が口癖でした(※追記:これは「ベートーベンの作品群を教科書として100年以上も変わらず学んでいるのは良いとして、そもそもの教科書自体を変えて学んだっていいんじゃないか?それとも音楽は進化していないのか?」という意味を含む)。現代に於いては「リヒャルト・ワーグナーだけがベートーベンに代わって崇められてしかるべき存在」であると言うワケです。シンフォニスト(交響曲作家)になることを早々に辞めて、イタリアでの大衆娯楽(エンターテイメント)であったオペラを総合芸術“楽劇”に昇華させ、音楽的に非常に深く、しかも観て聴いてビックリする音楽主導のスペクタクル・エンターテイメントを極めたからだと。その在りようは1977年のアメリカ映画『スターウォーズ(エピソードIV)』の音楽に的確に反映され、1980年代以降にはブロードウェイ・ミュージカル「オペラ座の怪人」、「ミス・サイゴン」等に反映され、その全てが興行的にも大成功を収めたという事実…即ち、現在もその芸術の手法は有効だという証であり、コマーシャリズムと芸術性という“相反する”とされているものが同居し得ることをも証明してみせました。ワーグナーが確立させた総合的芸術プロデュース方法論は、いまだに現役バリバリであるという論法です。
しかし1970年初頭の頃まで、某音楽大学教授が公然と「ワーグナーやムソルグスキーはクラシック作曲家として認められるべきではない。それは交響曲を1曲も書いていないからだ。ワーグナー唯一の交響曲は未熟な習作に過ぎない。」と平然と言い放ってしまうほどスゴい時代が長く続いたのも事実で、創作的精神論を盾に、反コマーシャリズムを良しとするかのようなクラシック・シーンの枠組みに、常に怒っていました。つまり父に言わせれば「それじゃクラシックはいつまでも赤字経営じゃないか。その論法だとガーシュウィンは除外されちまうわな。ガーシュウィンは大ヒットを連発して、祖国の人に愛された大メジャーだし、流派としてはどこにも属してないからね」。
そもそも“音楽に貴賤はない”と考えていた宮崎尚志なワケで、故に敢えて“枠組み=ジャンル”で言うならば、ガーシュウィンに倣ってオール・ジャンルに亘る音楽を書きました。CMであれバレエであれシアターピースであれ、その中では世界中のあらゆる音楽エッセンスを柔軟に取り込み、自分色に染め上げて提示しました。ロクに発表されなかったものの「演歌」も沢山書いています。何故、作曲家として円熟しても尚、クラシック・シーンに本腰入れて移行しないのかと聞いたら、
|
クラシックの作曲家を大勢知っているけど、その多くが公式の書類なんかで『職業』の欄に記入する名目に“作曲家”とは書いてないんだよ。それは日々の糧を得るための“本職”が、他にあるからなんだ。勿論、後進の育成は重要な仕事だよ。でもボクにはできない。できるだけ作曲に集中したいんだ。ボク自身は終生、公にも“作曲家”で生きたいんだよ。それがプロの作曲家(職業作曲家)の在り方だと思うんだ。ボクの名刺には“作曲家・宮崎尚志”としか書いてないだろう? 作曲が本職だっていう表明なんだ。多摩美の客員教授だとかコンセルヴァトワール尚美の講師なんてぇのは、あくまでボクが現役のプロ作曲家だから講壇に呼ばれているに過ぎないんだし、何よりそれだけじゃ全然生計立てらんないもの!! だから逆に、普通に先生が教えるような事は申し訳ないけど、一つだって教えられない。それこそプロの教師や教授でないと出来ないだろう? だからボクは現役バリバリのプロ作曲家として、ココから言うべき事、伝えるべき事を容赦なく言うぞって、講義を聴きに来た子達にはいつも言ってるんだよ。最初に“音楽には貴賤はない”ってはじめてね。。 (宮崎尚志・談)
|
ここで言う“音楽に貴賤はない”というのは、非常に単純な比較で言えば「クラシックとポピュラー」という二元論ですが、Naoshismから紐解くと、音楽を“高尚な芸術”と“俗なもの”とを区別しようとするライン(線引き)の事で、音楽を作る上での精神論とは全く関係のない、外野の話なのであります。
まず前提として、一つの“音楽”が“作曲者”と密接に繋がっているのは作曲中(製作途中)であり、完成した時点で音楽は作曲者から離れて独立する、というのがあります(故に多くの作曲家は過去に完成させた自分の作品を聞き返したがらない)。その論理の上に立って、例えばある音楽を作った張本人(作曲者)が「オレのこの曲は真の芸術。それに比べて○○氏のあの曲は下劣だ」等と言ったところで、もはや作曲家から独立した音楽自体は決してそんなことを一切主張しません。飽くまで、その作者本人の負けず嫌いな気負い、又はエゴイスティックな論理的志向性が、自ら作った音楽に対して格付けを行っているに過ぎません。しかもその格付けは絶対的なものではなく、単なる一評論でしかないのです。
精神論としてのNaoshismは、公に認知されるべくそのラインを引いたことによって「クラシックを博物館入りさせた」事を問題にしています。保護管理下に置かれているという意味ですが、その根元にはエリート主義的思想(下心)によって、誰かが線引きをしたことが最大の問題としています。資本主義経済の急速な世界規模の拡大に伴い、クラシックと呼ばれる音楽が極めて窮屈な場に追いやられ、音を出すのに金がかかる上に大きな利益を挙げることも容易ではなく経済効率の悪い音楽のシンボルとなった末、ひいては1980年頃から世界各国で続発した歴史あるオーケストラの倒産という“自然淘汰”を招いた元凶こそ、クラシックとポピュラーという“線引き”であり、それは本来の音楽そのものの立ち振る舞いとは無縁のものだと、言います。
反面、訳知り顔で言う輩には 「クラシックやジャズのレコードは売れないのが当たり前の不良債権。レコード会社はポップスやロックで大ヒットを当て、その利益を回して他の音楽のレコードを作っている。一般企業の論理なら、損失を出す可能性大のクラシック・レコードなど無駄の最たるもので、切り捨ててしかるべきだ。」 などと論理展開する者もいます。しかしこれは結局、思考の前提としてクラシックとポピュラーの線引きがあって、既に両者の優劣が刷り込まれており、ある種のコンプレックスの反動として出てきた話であって、Naoshismの根幹である“音楽に貴賤はない”という出発点からはほど遠いものです。これは音楽の在り方云々ではなく、“一商品”(金銭上での比較)としてのみに価値基準を設けた、一方的な論理に過ぎません。しかもその論理展開は結局、エリート主義への反動に他なりません。Naoshismは、こういった意見にも強く反発します。
たとえば「Naoshismな音楽の聞き方」というのは、究極的には作曲者不在、演奏者不可視の状態をさしています。音楽のすべては実際に出てくるサウンドにあり、そのサウンドにはまず作者の生き様や美学が投影されており、聴き手はそれを演奏者を介して受け取るだけで良いのです。勿論、“Art for Arts Sake”の作曲家神格化論では断じてありません。いうなれば“民謡”といわれる音楽、即ち音楽以外のデータが完全に失われ、どこの誰が作ったとか、誰が歌ったとかが全く不問のまま、人間の記憶の伝承として歌い継がれる音楽の在り方、それこそが音楽を聞く上での最も基本形であるというワケです。そこには音楽だけしかありませんから、聴き手は音楽が自ら喋り始める様々な物語を注意深く捉えようとします。そこには常に新たな発見があり、音楽を聴く本質的な愉しみと歓びをもたらす、それは即ち「感動」である、というのがNaoshismです。
成熟した資本主義社会に於いて芸術がその社会の一端を担うようになるには、それを享受する人々の意識度がアップしなければ達成できない。そうでなければ芸術なんて一般的には愉しくもなんともない、一部のマニアが狂喜してうんちく合戦するような“ヲタク”なものから脱することが出来ない。Naoshismは「芸術のもたらす最高のものは感動である」というポイントから、社会を担う人間一人一人(受け手)に芸術の有りようを提示すると同時に、作り手(送り手)にもそれを強く求めます。合理的・機能的な生活様式へと変化する現代社会に於いて、本当に必要なものは“感動する瞬間を得ること”であり、多くの人が感動を求めるようになった時、芸術はそれに確実に応え、感動を広め、分かち合う役目を果たすのです。
本来、名曲と言われる芸術作品には、必ず心を振るわせる“閃き”が内包されているにも関わらず、表面的にも美しかったり、愉しかったり、滑稽だったりします。しかも聴き手が目一杯のめり込んでも決して壊れないという、大変良くできたものです。すぐ壊れるようなものは芸術ではなく、単なる超合金ロボです(昔、勇者ライディーンの超合金はゴッドバードに変身出来たのが魅力だったが、のめり込んで遊んでいるとすぐに手足が折れたものだ…関係ないか)。
偉大な音楽家との出会い(1):Maestoro芥川也寸志さん
ガーシュウィンの影響下から形成された“Naoshism”の本質は、しかしながら時代々々の商業音楽シーンにフィットし浸透するものではありませんでした。「スカっとさわやかコカコーラ」をテーマソングに、コカコーラが僅かな期間で日本全国に行き渡っても、テーマソング自体は数年であっさりと別モノに変えられてしまう程、移り変わりの激しい時代に突入。それと同時に、商業音楽は、日本経済の一端を担う巨大な存在として独立していきました。時代は“売れたモン勝ち”に急激に傾いていき、「消費文化」などという新語まで作られたものです。そんな中、日本のクラシック・シーン行く末に危機感を抱いた人物に芥川也寸志さんが居ました。
芥川さんは黛敏郎さん、團伊玖磨さんと「三人の会」を組織して、クラシック系の作曲家の自活を提唱しただけでなく、日本の著作権料を整備し直し、積極的にTVに出演して司会者兼指揮者として大活躍、“お茶の間”の人気を獲得し、音楽家の一般的な認識の向上(底上げ)に尽力されていました(この当時の指揮者/作曲家は「題名のない音楽会」の黛敏郎さんにしろ、「オーケストラがやってきた」の山本直純さんにしろ、アプローチは違うものの積極的に放送メディアに顔を出していたのは凄い時代だ)。その活動の一環で1960年代に、現在のワイドショーの草分け的な番組であったTBS「土曜パートナー」をスタート、アシスタントを兼ねる歌手に、NHK初代“うたのおねえさん”を経てフリーになった中野慶子(即ち、私の母)を起用しました。この当時、まだクラシック音楽と商業音楽の間には、互いに相容れない何かがあったようで、歌手として全国的に着実な人気があった中野慶子は、芥川さんに痛く気に入られて共演していた事もあってか、クラシック・シーンからの注目度が非常に高かったそうです。そんな中、“音楽に貴賤なし”とばかりにコマソンから管弦楽からシャンソン、前衛バレエ、ビッグバンド、果ては冗談音楽まで節操無く書きまくる商業音楽の権化=宮崎尚志と結婚するとなるや、童謡を数多く手がけていたクラシック・シーンの作曲家陣から「なんでやねん!勿体ない!いや、冗談やない!」といった意の言葉を多数頂戴したそうです。しかしこれを好機と見ていたのは芥川さんでした。
芥川也寸志さんは暫くして中野慶子を通じて、宮崎尚志に急速に接近します。それは新たに「日本作曲家協議会」を立ち上げる為、その創立メンバーとして加わって欲しいとの思いでした。この申し出を、宮崎尚志は一度断っています。しかし芥川さんは「これからの日本の音楽はクラシックだのポピュラーだのと縄張り争いをしていては互いに発展は望めない。本来、音楽には貴賤はない。」という考えを明らかにしました。フリーランスの作曲家として飛ぶ鳥を落とす勢いだった宮崎尚志としては、日本クラシック界の大スターが自分と同じ考えを持っていたことについて大変感銘を受け、協議会のファウンダー・メンバー入りを承諾したそうです。又、この時、芥川さんは宮崎尚志に対し、大きな「作品」(例えば交響曲のような絶対音楽)を書くように強く勧めたとも伝えられています。
偉大な音楽家との出会い(2):Violinist 潘 寅林さん
時は流れて1980年代、盟友・大林宣彦監督の映画『廃市』の為に書き上げた弦楽四重奏のサントラを録音する際、スタジオにやってきた中国人の第一ヴァイオリンの奏でる、心が軋むような演奏に感動し、落涙します。そのヴァイオリニストは当時、読売交響楽団のコンサート・マスターであった潘 寅林(パン・インリン/Pan Yinlin)さんでした。上海に産まれ、若くして上海交響楽団のコンサートマスターを任されるほどの実力があり、天才的なソリストとしても将来を嘱望された、クラシック・ヴァイオリン一筋で生きてきた潘さんでしたが、1960年代の文化大革命の折に当局からの弾圧を逃れて亡命した経験を持ち、迫害も規制もない自由な音楽表現の場を求めて1981年に日本の読響に入団したところ、3年後にはコンサートマスターに昇格。そんな折りに請け負ったスタジオ仕事が、映画『廃市』のサントラ録音だったようです(事実未確認)。
この時、宮崎尚志は始め「読響のコンマスが来た」とビックリしたそうですが、その演奏表現を聞いて「偉大な、本物の音楽家によって、産まれて初めて自分の書いた音楽で感動するという経験をした。」と2度ビックリしたとか。逆に潘さんはというと…
|
凄い音楽を演奏していると感じた。こんな音楽体験にはなかなか出会えない。この音楽がどのように演奏されるべきか、悩むことなく瞬時に理解できました。作曲者が言いたいこと、演奏者に求めることは、作者に直接指示を仰がなくても、書かれた音符を奏でるだけで、音楽の方から指示が飛んできたのです。宮崎先生と私は、確かに音楽で会話しました。私は録音が終わっても尚、もっと先生が書いた譜面はないのですか!もっと、もっと演奏したい!もっと譜面を下さい!と叫びました。その幸せな音楽の時間を、終わらせたくなかったのです。
(潘 寅林 - 2000年3月・ミレニアム植樹祭打ち上げの席での、私との談話の中での発言)
|
…とのこと。これを機に潘さんと宮崎尚志は強い信頼関係で結ばれ、2000年の全国植樹祭(大分県)に於ける、360度サラウンド+1500人で演奏された、再現不可能な巨大編成のオラトリオ「ミレニアム植樹祭 in 大分」のコンサート・マスターとして、当時シドニー交響楽団のコンマスだった潘 寅林さんを指名、潘さんは万難を排して駆けつけました。潘さんは植樹祭終了後に行われたパーティーで、副指揮者兼シンセサイザー奏者で出演していた私に、「あなたのお父さんの音楽を演奏させて頂けるなら、私はたとえ地球の反対側に居たとしても飛んでくるでしょう。」と話して下さいました。それを聞いた父=宮崎尚志は「潘さんのような偉大な音楽家にそう言われちゃ〜、自信ついちゃったなぁ。でも、ボクもこのオラトリオ書いて、やっと“音楽の一年生”になれたなって、本当に思ってるんだ。」と照れくさそうに語りました。

第51回全国植樹祭会場設営風景(大分県・大野町「平成記念公園」2000年3月)
 ガーシュウィンにインスパイアされた“音楽に貴賤はない”というポリシーで、約40数年間やってきたありとあらゆる事が、オラトリオ「ミレニアム植樹祭 in 大分」に完全に集約されている事は疑いようが無く、2時間半の全編を多様な“メロディー”で紡いでいく様は、もはや宮崎尚志しか成しえないワン・アンド・オンリーの充実度。ジャンルを作為的に統合したり超越したりすることなしに、一人の音楽家が経験してきた様々な音楽的要素がフュージョンされた、“大きく開かれた、パーソナルな作品”であり、宮崎尚志の人柄がそのまま投影されたものです。しかもそれには、ガーシュウィンの「ラプソディー・イン・ブルー」や「パリのアメリカ人」の立ち姿に、非常に近いものを感じます。この時、宮崎尚志は本当の意味で初心に返って、虚飾のない、等身大の自身を見つめたのかもしれません。そしてそこにはガーシュウィンに憧れてやまなかった、若き日の自分をも見たに違いありません。
ガーシュウィンにインスパイアされた“音楽に貴賤はない”というポリシーで、約40数年間やってきたありとあらゆる事が、オラトリオ「ミレニアム植樹祭 in 大分」に完全に集約されている事は疑いようが無く、2時間半の全編を多様な“メロディー”で紡いでいく様は、もはや宮崎尚志しか成しえないワン・アンド・オンリーの充実度。ジャンルを作為的に統合したり超越したりすることなしに、一人の音楽家が経験してきた様々な音楽的要素がフュージョンされた、“大きく開かれた、パーソナルな作品”であり、宮崎尚志の人柄がそのまま投影されたものです。しかもそれには、ガーシュウィンの「ラプソディー・イン・ブルー」や「パリのアメリカ人」の立ち姿に、非常に近いものを感じます。この時、宮崎尚志は本当の意味で初心に返って、虚飾のない、等身大の自身を見つめたのかもしれません。そしてそこにはガーシュウィンに憧れてやまなかった、若き日の自分をも見たに違いありません。
余談ですが、オラトリオの作曲にあたって父は、ドミトリィ・ショスタコーヴィッチのオラトリオ『森の詩』を初めて聞いています。意外なほどキャッチーな歌が次々に飛び出すこのオラトリオを聞いて、「駄作って言われているけど、作られた経緯なんか気にしないで聞けば、結構面白いよ、これ。でもな、これ聞いて自信ついたぜぇ! 当時、ショスタコは出来なかったことが、今度はいっぱいできる。」と、妙にハッスルしていたものです。
ちなみに“音楽の一年生”の意味は、ひとつのポリシーを貫いて生きてきた中で、音楽というものの何たるかの、僅か一端を垣間見たという事でしょう。音楽という深淵なる世界に出入りできるパスポートを入手した…とファンタジックに表現するとそうなるかもしれません。これはそれを手に入れた個人でしか理解できないものでしょうから、私なんかが何をかいわんや、というものなんですがね。しかし芸術家たる者はすべからく、芸術という無限階段を見据え、それをギャーギャーわめきながら一段ずつ登る、それこそにこの上ない歓びを見出すものです。お金や地位、名声を得るより、ずっとずっと嬉しいものなんですよ。もっとも、その歓びは誰とも共有できない、本人だけの歓びなんですけどね…。
 ガーシュウィンは、どうだったんだろう?何年生だったのかな?よくよく考えてみれば、興味は尽きませんね…あっ、なんだかしらないけど、ガーシュウィンの「ピアノ協奏曲 in F」が聞きたくなってきたな…私の一番好きなピアノ協奏曲なんですよ、キース・エマーソンの「第1番」、セルゲイ・ラフマニノフの「第3番」と並んで…ですけどね。
ガーシュウィンは、どうだったんだろう?何年生だったのかな?よくよく考えてみれば、興味は尽きませんね…あっ、なんだかしらないけど、ガーシュウィンの「ピアノ協奏曲 in F」が聞きたくなってきたな…私の一番好きなピアノ協奏曲なんですよ、キース・エマーソンの「第1番」、セルゲイ・ラフマニノフの「第3番」と並んで…ですけどね。