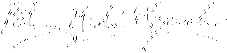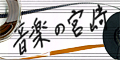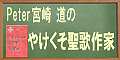Powerd by
sogaku.com
宮崎尚志のレコード棚
エレクトリック・ライト・オーケストラ (E.L.O.)
『アウト・オブ・ザ・ブルー』
Electric Light Orchestra(E.L.O.): Out Of The Blue (1978)

弦楽ロックの金字塔
頭文字をとって“E.L.O.”…これを“エロ”と読んだヤツの多かった事多かった事…そう読むならLじゃなくてRだろって。
ちなみに、今これを読んでいる方で、ELOを全く知らないという方はいらっしゃいますか?知らないとおっしゃる方々は、もしかしたらビートルズの前の世代か、まだ小学生の子供たちか、洋楽ポップスを好きでない方々かしら? ELOは知らないけど、バンドリーダーだったジェフ・リンなら知ってるぞ、という人もいるかもしれませんね。ともあれ、このバンドは全盛を誇った1970年代末から現在も尚、強力な影響力をさりげなく発揮し続けている巨星です。そのリーダーであり、バンドのほぼ全曲を書いきたジェフ・リン(vo,g,etc)は“ポップ・マエストロ”と称され、1986年のバンド解散後にプロデューサーとして大活躍、かの再結成ビートルズの「フリー・アズ・ア・バード」と「リアル・ラヴ」を実質的に製作したのはこの人です。
ポップ・マエストロを有するだけじゃなく、ELOは4ピース(g+b+key+dr)のロック・バンドに、3人の弦楽奏者(ヴァイオリン×1、チェロ×2)がいる、ユニークな編成でも常に話題でした。しかし1974年頃からレコーディングにフル・オーケストラを導入し、オケとバンドが渾然一体となって奏で上げる、気品さえ感じさせるポップ/ロック・ナンバーで大ヒット・シングルを連発、ギネス・ブックに「1970年代に最も多くの全米Top40シングルを放った英国のバンド」として記録される程の人気を誇りました。1978年はELOの絶頂期に当たり、2枚組の大作となった7thアルバム『アウト・オブ・ザ・ブルー』は圧倒的な完成度を誇り、世界中で大ヒット。ポピュラー・レコード史を語る上では欠かすことの出来ない歴史的名盤として知られています。
ブラスロック編成の応用
はて、ビッグバンド・ジャズを経てブラス・ロック/ファンクを好んでいた宮崎尚志にしてみれば、ブラスロックでもないこのELOに興味を持った、というのが私には実に不思議でした。それで聞いてみましたところ…
|
エレクトリック・ライト(ELOのこと)はシカゴなんかと同じ編成でありながら、ブラス・セクションをストリングスに置き換えてるだけだろ。ブラス・ロックじゃなくて“ストリングス・ロック”ってので、どんな新しいサウンドを創ってるんだろうって思ったのさ。もっとも、ボクにしてみればスタジオでは別に珍しい編成じゃないんだけど。 で、思ったより面白かった。でもレコードでは編成の大きいオーケストラが入っちゃってて、既にこのバンドの音じゃない。でも弦楽ロックっていうよりオーケストラ・ロックになってるのが、却って面白味があったよ。ストリングスのアレンジが面白い。シンセサイザーの使い方もいい。音がカッチリ作られていて、オリジナリティーがある。しかもエンターテイメント性も高い。ジャケットも綺麗だし、このレコードは素晴らしい。 (宮崎尚志・談)
|
このアルバムを買った1978年から翌年1979年にかけて、父はダビングしたカセットテープを車に積み込み、アース・ウィンド&ファイアーのアルバム『スピリット〜魂』、『太陽神』と共に、移動中によく聞いていたようです。毎年夏休みに軽井沢で行われる教会キャンプに家族揃って出かけた際、父はよく『アウト・オブ・ザ・ブルー』をかけてくれました。特に3曲目の「スウィート・トーキン・ウーマン」は、私ら息子にとっては“軽井沢のテーマ”となるほど強く印象づけられました。

又、長岡秀星氏が描いたスペース・オペラな“ELO UFO”のジャケット・ワークは、子供心に衝撃的でした。とにかくカッコよかった!見ているだけでワクワクしたものです。一時期、居間にはこのアルバムと、アース・ウィンド&ファイアーの『太陽神』、『黙示録』(全てジャケット画は同作家)が並んで置いてあった事があり、さながら長岡秀星コレクションでしたね。
E.L.O.はどこがスゴいか?〜宮崎尚志の見解
はて、父がELOに大きな興味を持った事は判った。しかし父がレコードを仕入れてくるということは、限りなく“アメリカで流行の最先端の音楽とサウンド”をいち早く学ぶ事に他ならなかったワケですが、それまでの宮崎尚志の指向性とは、ELOは相容れないものを感じました。何しろ父はELOの祖とも言えるビートルズを、全くと言って良いほど好きじゃなかったし。EW&F(アース・ウィンド&ファイアー)であれば、よーく理解出来たんですがね、ブラス入りのファンクが基本だし。その点を聞いてみたら、父は以下のような話をしました。
|
(1) 理想的なシンセサイザー使用例 エレクトリック・ライト(しつこいようだがELOのこと)は、フル・オケの中で違和感なく、シンセサイザーがアンサンブルに加わっているように聞こえるのが、実は最先端だったんだよ。20世紀最大の画期的な、全く新しい楽器としてシンセサイザーが世に登場したっていうのに、“シンセサイザー協奏曲”なんて聞いたことないし、あったとしても全然知られてないでしょ。以前、エマーソン・レイク(いわゆるEmerson,Lake&Palmerのこと)なんか聞いたらね、シンセサイザーのミックスがやたらデカくってね、どんどん前の方に出して来ちゃうんだよ。シンセサイザーって楽器に誰もが興味を持っていたのは事実だけど、他の楽器に比べて“殿様”みたいな扱いをされていたのは悲劇的だ。(2) シンセサイザーに対する誤解 シンセサイザーが“どんな楽器音でも合成できる夢の楽器”だっていう大誤解というか、デタラメが広まって、他の楽器の連中から疎まれて、孤立して自己完結の方に向かっちゃったのは本当に残念に思う。それによって一般的にはデタラメを助長する結果にもなったんだし。「スイッチオン」(Walter Carlosの『スウィッチト・オン・バッハ』のこと)にはじまって、冨田くん(=冨田 勲)がそれに続いていった、クラシック曲のシンセサイザー演奏は、今まで聞いたことのない楽音で組み立て直した、新しいアンサンブル・サウンドを作ろうとしたのだと思うんだが、一般的には部分的に聞こえる音が“○○○の楽器音にソックリ”とか、既存の楽器音のリアリズム(再現性)に注目しちゃって、肝心の作者達の意図するとろなんて、ハッキリいってどーでもよかったんだ。そうした一般的な嗜好性にシンセサイザーそのものが飲み込まれた結果が、デジタル・サンプリングの登場だ。1970年頃のシンセサイザーは、確かに楽器としては未熟だった。特にMOOGは問題多かった。それが年月を経て改良されていって、ヤマハのDX-7みたいに、どんな場所でも、どんな楽器とも合わせられる楽器としての安定感を獲得した。現場で実際にマニュアル演奏してないとはいえ、その象徴的な出来事は冨田くんのサウンドクラウドのコンサートだと思うよ。生楽器のソリスト達とシンセサイザー・オーケストラの共演を何度も成功させている。そのノウハウはおいそれと真似が出来ない凄いものだ。ただ“シンセサイザーの冨田勲”がやっているから仕方ないのだけど、指揮者(冨田氏)と一体化したシンセサイザー・オーケストラが絶対的な権力を握っていて、シンセサイザーの土俵に生楽器が乗った形になっていたのは残念だけどね。 (3) 楽器としてのシンセサイザーのあるべき姿 ところがエレクトリック・ライトは、オーケストラとロックバンドが同一線上にあるサウンドを作っちゃったんであって、しかもシンセサイザーが何の不自然さもなくアンサンブルに加わってるんだから、まいっちゃうよ。シンセの使い方として理想的、実にセンスが良い。ロック・バンドの後ろにオーケストラを並べたんじゃなくて、オケがロックやってるみたいだろ。これみたいに、オケがズカズカとロックバンドに絡んでくるようなサウンドっていうのも他にはなかった。これを実現させて発売出来た事自体、凄い。ロックバンドとオーケストラの共演ってのは、腐るほどあったよ。その殆どがオケはバンド演奏の色づけに過ぎなかったり、チグハグだった。でもエレクトリック・ライトは、オケがいないと彼らのサウンドが出ない位、オケに比重を置いている。ここではシンセサイザーは万能楽器ではなくて、生楽器にはない独特の“楽音”で、常にアンサンブルに加わっている。このセンスが、プログレッシヴ=Progressive Rock)にはなかった新鮮さだ。 (宮崎尚志・談)
|
確かに1978年、まだ小学生だった頃の私は、このアルバムを何度聞いても“シンセサイザー”が鳴っているとは気付きませんでした。何しろ当時の私は、シンセサイザーの音が大嫌いだったのです。シャープな切り口で太々しいワリに、どこか悲しげな(ピッチが不安定だからか?)シンセサイザーが全面に出しゃばっている音を聞くと、何故か辛くて悲しくなっていました。ジョルジオ・モロダーのプロデュースしていたサウンドは、特に嫌でした・・・ドナ・サマーとか。しかしELOのそれは、完全に“アコースティック”なテイストとしか思えなかった。故に、かなり後になって『アウト・オブ・ザ・ブルー』で聞けるシンセサイザー・サウンドの多彩さに、心底ビックリしたものです。
例えば歌謡曲・・・ピンクレディーの「ペッパー警部」等で聞けるシンセサイザー・サウンドは、ほんのちょっとしか出てこなかったから嫌味に聞こえなかった、という印象は今でもよく覚えています(気になっていたんですがね)。「UFO」だって、イントロ等でバリバリに聞こえる程度で、決して全編に渡って出しゃばってないし。
その他の弦楽ロック
弦楽ロックバンドというのはELOが最初なのでしょうか? ELOの登場は1971年。それ以前にはヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ等の弦楽器を奏するメンバーを有するロック・バンドというのは、そう多くはないようです。1960年代末にはアメリカの“ニューヨーク・ロックンロール・アンサンブル”(後に映画音楽家となった故マイケル・ケイメン在籍)や、ELOの前進である“ザ・ムーヴ”が存在しましたが、これらはメンバーが楽器持ち替えでチェロを弾いていた。1970年登場の“ジェントル・ジャイアント”も楽器持ち替えでヴァイオリン+チェロの重奏を実現してました。1969年登場のイギリスの“カーヴド・エア”はサイケデリックなヴァイオリン入りのロックをやっていて、専任のヴァイオリニストとしてダリル・ウェイ(vln)という名人がいました…。そう考えると1970年代初頭ではELOのような形態のロックバンドは、やはり他になかったかもしれません。ELOの後に続いた“エスペラント”は弦楽四重奏団+女声ボーカルを3人も有するバンド・セクションを合体させた大所帯で、スゴいサウンドを出していましたが、メンバーが多すぎて運営難で解散に至っています。1990年代でしたか、日本では弦楽器をメインに据えたバンド“Brew-Brew”(あっ、vln.で金原千恵子さん在籍でしたね)がアルバム『文化ポップス』で登場しましたが、その頃にはELOはもうなかった・・・。
ある意味、専任の弦楽セクションを持つロックバンドで、安定した運営が行えるほどの商業的成功を得たのは唯一、ELOだけだったのではないか? 特異な編成、ロックバンドとしては大所帯でありながら、シングルを確実にヒットチャートに送り込むと同時に、アルバムも軽く100万枚単位で売ってしまう離れ業をやってのけたリーダー=ジェフ・リンの手腕だけは、世界で誰一人として真似が出来なかったんですね。
バンドって、やっぱライヴでしょ!
『アウト・オブ・ザ・ブルー』を心底気に入った私は、こんな素敵なロックがこの世に存在するなら、もっと聞きたいと思いました。1979年にELOが初来日して武道館公演を行うと聞いた時、彼らの音楽をライヴで聞きたいと本気で思いました・・・まだ小学生だったんですがね。その時、世の中はボブ・ディランが来日公演やることで持ちきりで、ELOなんかロクにニュースにもなってなかったような記憶がありますが・・・。1980年には映画『ザナドゥ』の主題歌(オリヴィア・ニュートン=ジョンとのコラボ)が大ヒットして、ELOへの興味はより強くなり、中学に上がった1981年からお小遣いを注ぎ込んでELOのアルバムを集中的に買い集めました。丁度、ラジオからELOの最新シングルとして「トゥワイライト」が流れていて、わぉ!ファンタスティック!カッコいい!と思ったのも契機になりました。余談ですが、同時期に必ず流れてきたのがクィーン&デヴィッド・ボウイの「アンダー・プレッシャー」で、こちらは妙に切迫していて怖かったのを覚えています。今は大好きなんですがね。

で、「トゥライライト」を聞くためにアルバム『タイム〜時へのパスポート』(1981)を買ってみた。これが私にとって、産まれて初めて買ったロック・アルバムでした。しかも全曲継ぎ目なしのコンセプト・アルバム…この辺りに私のプログレ好きの発端があるような気もする…。その音楽とサウンドは、期待を全く裏切らないものでした。こりゃ凄い!ロックっていいなぁ〜、そんな風に思ったものです。しかし父はこれを何度も耳にしてもELOだとは全く気付かなかったと言ってましたし、このアルバムではメンバーの弦楽三重奏の音が聞こえてない。メンバー写真もバンド・セクションの四人だけになってる…あれ?どうしたんだ?

続いて私は、『アウト・オブ・ザ・ブルー』の次に出たアルバム『ディスカヴァリー』(1979)を買ってみた。聞いてみれば、TVやラジオでよく耳にした「コンフュージョン」や「ロンドン行き最終列車」が入っていたので、おぉ、あの曲だ、これは当たりだ!などと一人で大喜びしたもので、やはり音楽とサウンドは期待を全く裏切らない仕上がり。本当にスゴい!これがロックってモンなのか!でもレコードの内ジャケットのメンバー写真はやっぱり四人だけ。弦楽ロックバンドとしてのELOはどうしちゃったんだ?

私は弦楽ロック=ELO本来の音が聞きたくて、3rd『第三世界の曙(1974)に辿り着きました。しかし出音にビックリ!終始、チェロがギコギコと無骨に鳴っていて、ヴァイオリンは踊るが如くに華麗に大活躍(ミック・カミンスキーのヴァイオリンって凄く好きだ!)。ELO本体がかつて奏でていた音は、凄くヘヴィーでダイナミックなロックでした。ELOは、ビートルズの「アイ・アム・ザ・ウォルラス」のサウンドをライヴで実現出来るバンドとしてスタートしたとはいえ、ブラス・ロックの金管セクションを弦楽に置き換えるという安直なアイディアを逆手に取り、弦楽ロックだからこそ可能な重厚な世界観を作り上げていたのに衝撃を受けました。なにしろ、カッコよかったのです。
ELOが発表した全てのスタジオ・アルバムを揃えて、バンドの足跡を辿ってみたところ、興味深いことにELOは3作目の『第三世界の曙』以降、レコード上では(弦楽ロックバンドとしての)バンド・サウンドの追求を辞めてしまい、この編成はライヴ用だけのものになってしまった事です。結果、4作目の『エルドラド』からオーケストラが加わり、本来のバンドとしての機能は失われたのに反して益々人気を獲得、世界のトップバンドへと成長していったという皮肉な話。ELOは皮肉を抱えることで巨大になった、変なロック・バンドだったのです。父にそういったELOの話をすると…
|
バンドでなくちゃ出来ないサウンドって、結局“生”(ライヴ)でしょ。スタジオに入ったら、バンドじゃない方がサウンドのヴァリエーションは広がる。だってバンドは編成が決まってるからね。バンドじゃなければ、録音の日にち毎にガラっと編成を変えられる。エレクトリック・ライトも、録音では弦がメンバーとして一緒に居る必要がないんだよ。録音毎にスタジオ・ミュージシャンを呼べば良いんだから。 (宮崎尚志・談)
|
なるほど。確かにそうかもしんない。シカゴ等のブラス・ロック・バンドでは、ブラス・アレンジはブラス担当のメンバーが書いている場合が多いし、楽曲だって提供する。しかしELOはリーダー=ジェフ・リン以外は曲を書かせて貰えてないし、弦楽のアレンジはリチャード・タンディー(key)とジェフ・リンが主だってやっている。オーケストラを入れてからはルイス・クラークにアレンジを任せている(ルイス・クラークは、後にクラシック曲のディスコ・メドレー『フックト・オン・クラシックス』で一世風靡する名アレンジャー/指揮者)。弦楽器奏者は自分たちのパートを自ら作り出すのではなくて、譜面貰って演奏しているのだから、バンドのスタイル自体がかなり違ってますね。
ロックな教育
宮崎尚志は時折、旅行中にいきなりロックやポップスを流してくることがありましたが、私なんかは当時小学校高学年で、まだまだ朝日ソノラマのソノシート(仮面ライダーとかヤマトとか)を楽しんでましたし、一方でTV「熱中時代」(作曲は平尾昌明さんでしたね)をTV放送を録音したりして聞いてました。後の“警視庁特命係の杉下右京警部殿”の歌う「カリフォルニア・コネクション」なんか大好きでした。一方、1978年に映画『未知との遭遇』を観て以来、映画(主に洋画)のサントラへの興味が沸いてきた頃でした。両親に頼んで“黒いLPレコード”(ソノシートは赤かったから)を買って貰うことも増えてきた頃です。
そこに父は、ドライブの車中という私たちが逃れられない環境下で、カーステレオからロックやファンクをガンガン流し始めました。それは、音楽ってものは子門真人、水木一郎アニキ、杉下右京・・・違った、水谷 豊だけじゃないんだぞ、世界には凄い音楽がまだまだいっぱいあるんだと言いたかったのでしょう。例えばこれがクラフトワークでも流れていたら、私ら息子達の人生は大きく違ったものになっていたと思います。お陰様で、ELOの『アウト・オブ・ザ・ブルー』は私の“無人島に持っていくレコード”です。
なんでそうなるのかと言えば、『アウト・オブ・ザ・ブルー』は一点の翳りもないポップ&キャッチーなフィーリングに溢れた、抜群の音楽集だったからです。良い音楽は、いつ、どこで、どのように聞いても、やっぱり良いんですね。有り難いことに、父から一生モノの音楽を教えてもらったというわけです。感謝。