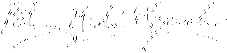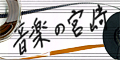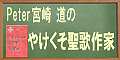野外録音!
至福の田園フォーク
英国の四人組フォーク・グループの1970年のデビューアルバム。スタジオではなく、野外レコーディングでアルバム製作した特異なグループとして知られています。フォークギター×2、フラットマンドリン、キーボード(ピアノ/アコーディオン/オルガン)という編成で、絶対メジャーになるハズもないであろう地味極まりないシンプルなサウンド、上手くもなんともない演奏。それでも今聴くと驚くほど無垢でピースフルで本当にいい。
四人の演奏は物凄くラフで、ロクに打ち合わせ出来てないみたいな瞬間も多々ある上、本当にお世辞にも上手い連中ではないのに、一度聴いて気になってしまうと心を捕らえて放さない魅力があるのが不思議。野外での録音だけあって、鳥のさえずりがずっと入ってるし、時に上空を飛ぶ飛行機のエンジン音、マイクが風で吹かれるボボボーッという音も曲間に入ってきます(曲中には入ってこないのが凄い)。イージーリスニングにも成り得ますが、真面目に聴けば純粋に楽曲の良さが際立っていて、曲の構成も良くて聞き易いし、バンドとアルバムのコンセプトが見事に合致していて全てが心地よいアルバムに仕上がっています。私はこれ、大好きなんです。今までで何度聴いたことか。
棚の奥から・・・宮崎尚志の秘蔵レコード
家のリビングにあった父のステレオセットの使用許可を貰った私が、父のレコード棚の蔵盤を片っ端から聴いていた頃…多分私が中学3年か高校1年の頃だったと思いますが、父は次第に「このレコードを絶対聴いてみろ、イイぞぉ〜」と、ご推薦盤を選んでくれたものですが、何かのきっかけで「昔、買ったレコードで、野っ原で録音したLPってのがあるんだよ。普通の演奏の後ろで鳥の声とかがそのまんま入っちゃってる、エラく良いレコードでね....えーと、何ていうグループだったかなぁ〜、名作なんだよ」と言い始めて、そのグループの名前を思い出すまで数週間、折に触れては「なんだったっけなぁ〜」と考えていました。
ある夜、私がレコードを聴いていたら父が「思い出した思い出した、確かここにあったと思う!」と言いながら、レコードプレーヤーの上に設置されていた棚にあったレコードを出し始め、「やっぱりあった!そうだ、ヘロンだ。これだよ!大切だからここに入れといたんだな」と私に見せてくれました。そして是非聴けというのです。そんなにイイのか?と聞くと、「道は絶対に好みだと思うよ。とにかくイイんだから。」と念を押されてしまいました。早速プレーヤーにかけて聞いてみて、私は一発でハマりました。確かにいい!
ほぼ全曲ミドルテンポのゆったりした感じ、残響もへったくれもない録りっぱなしみたいな音、全体的にくぐもった音質(レコードではそんな感じの音です)、マイクのそばで呟くような歌、合ってるんだか合ってないんだか判らないような3声のコーラス、曲間でハッキリ聞こえてくる鳥のさえずり、木々を揺らす風の音。なんかヘンな音でした。けど凄く空気感のあるトータル・サウンドで、言うなれば目の前でグループが演奏しているかのような錯覚に陥りました。
聞き終わってから凄く良かった、面白かった、気に入った、と父に報告しましたら「そうだろ〜、絶対気に入ると思ったんだ」と得意気な顔をして、そこからしばらくの時間、この1枚のレコードについてあれこれ話しました。
録音芸術作品とはかくあるべし
父は概してフォーク・ミュージックの類が好きではなかったにも関わらず、この“田園フォークの権化”のようなヘロンに惹かれていたのは何か?というのが私の疑問でした。
父は、ヘロンは演奏が上手くないことおびただしいにも関わらずリスナーの心を和ませるのには、まず基本的に楽曲の良さが挙げられるが、自然のノイズだらけの野外録音、しかも人工的音響効果等(スタジオでのエコー処理など)の加工一切ナシであることがまず最初にスタジオの音に慣らされたリスナーの耳にショックを与え、しかも編成にハッキリとした低音部(ベースとバスドラム)がないことでオーディオ的にはボトムを支える部分が希薄になる為、サウンドのフォーカス(輪郭)が曖昧になり、そうした宙に浮いたバンドサウンドが形成される中に風の音や鳥の声が交じる時、一種の催眠術のような効果を生みだしている気がする、と分析しました。生々しい浮遊感とでもいいましょうか、そういった感触は敢えて作ろうとしても作為的になるのが関の山で、この『ヘロン』はグループの能力だけではなく、レコード製作に於ける総合的なメイキング(=プロデュースによって“無作為の何気なさ”の実現に成功した、としました。故にフォークが好き嫌いとかは関係なく、グループの体質とアルバム製作の両方のトータル・コンセプトの上に立った見事なプロデュース・ワークであることを、父は絶賛していたワケです。
 なるほど、と納得した私でしたが、更に疑問が沸きました。父は常々、若者の音楽(特にロックとフォークを指していたと思われます)はメッセージ性/明確な主義主張の発露でなければ意味がないし興味がないと豪語していたのですが、ブリティッシュ・フォークのフィールドから登場したヘロンの音楽(歌詞)にはそういったものが全くなかったのです。センチメンタルなラヴソングを妙にドライに歌っているだけですから、父にとっては“意味ナシの権化”でもあると思われたからです。
なるほど、と納得した私でしたが、更に疑問が沸きました。父は常々、若者の音楽(特にロックとフォークを指していたと思われます)はメッセージ性/明確な主義主張の発露でなければ意味がないし興味がないと豪語していたのですが、ブリティッシュ・フォークのフィールドから登場したヘロンの音楽(歌詞)にはそういったものが全くなかったのです。センチメンタルなラヴソングを妙にドライに歌っているだけですから、父にとっては“意味ナシの権化”でもあると思われたからです。
しかし、父の見解は意外なもので、このレコードをこういった方法で製作したこと自体に、言葉に出来ないほど強いメッセージがあると言い切りました。スタジオという“箱”が次第に高度に整備されていき、ポピュラーに於けるレコーディング技術が飛躍的に複雑化し音質も向上していく最中、そこを飛び出して屋外で録音するという方法はスタジオシーンの潮流から逸脱した行為で、これも当時のひとつのアンチテーゼであって、徹底的に社会の潮流からの“逸脱”が貫かれていることに注目すべきだと。ベトナム戦争の影響で社会からドロップアウトし、都会を捨てて自然に帰ろうというヒッピー的な若者の思想が根底に強く感じられるへロンは、敢えて飾り気のない(毒にも薬にもならないような)穏やかな歌によって、逆説的にも平和で穏やかな生き方を説く若者の強いメッセージへと転換している。これはブラスロックのシカゴ・トランジット・オーソリティー(シカゴ)の行っている社会運動型の直接的なアンチテーゼとは対極の姿勢だが、向かっているベクトルは同じだと考えられる、と言うのです。ほぉ〜、なるほど、そうきたか。
そして父は更に続けます。音楽という芸術は様々な力を内包するが、録音芸術には譜面を見ただけでは判らない音楽の裏側を映し出させることもできるし、時代の空気を閉じこめることもできる。音楽と録音の両方の芸術性が互いに高め合う相互関係のポイントを掴み、それを“記録された音”にすることで、音楽は無限の可能性を手に入れられるほどレコード製作者(プロデューサー)という作業は重要だ、『ヘロン』はその最良の例だと。反面、皮肉なことだが『ヘロン』の楽曲だけ取り出してライヴで演奏しても、レコードほど意味深く聞けるハズもないだろうなぁ〜、とも。ありゃりゃ…。
野外録音は高等技術 〜 宮崎尚志の野外録音体験談
この時、父は昔、生命保険協会のCM「兜編」で“草笛”を録音に使った経験を話してくれました。片田舎で草笛を吹く名物おじさんがいることを知り、ユニークなサウンドを求めていた父は早速そのおじさんとコンタクトを取ったところ、草笛は草自体の鮮度が命なのでスタジオへ持っていくことは出来ないということを告げられ、直接そのおじさんの住む田舎へ録音班を率いて出向いていったのだそうです。ですが草笛は本当にデリケートで、笛を作成してから僅かな時間しか楽音が出せないということで、急遽野外レコーディングを敢行したとのこと。ですがそのおじさんは初めてのレコーディングということで大変緊張なさったのか、演奏を間違えてしまったり音が正確に出なかったり、草笛自体を何度も何度も作り直し、時には鳥がうるさかったり風が吹いたりして雑音も多く、膨大なNGテイクが出て録音はかなり長時間に渡ったそうです。しかも現地が雨模様だったこともあって2日ほど宿泊して天候回復を待っての録音だったとか。どうやら草笛でメロディーを単独録音してから、そのテープをスタジオへ持って帰ってオケをオーバーダビングしたようで、出来上がったものはまるで全編スタジオ録音のように仕上がっていました。
『ヘロン』を聞いてみると、あまりの素っ気なさに“誰でも出来るような簡単な感じ”さえ受けますが、ジャケット裏のレコーディング風景を撮った写真を見るとマイクはスタジオ録音と同じように複数立てられています。父は実際に「兜編」の草笛野外録音を行った経験から、この録音は驚くほどのNGテイクを出したであろうことに触れ、悪条件をモノともしないメンバーの忍耐力と共に、極めて高度なライヴ・レコーディング技術の賜であると評しました。何しろどんな上手くいった演奏でも、マイクが一回でも風に吹かれてボボボーッと鳴ってしまったら問答無用でNGですし、録音当日が雨模様だったらその日は中止になるのですから、大変な作業です。簡単そうに見えてその実、誰も出来ないほど難しい、これが芸術の極意です。なるほど、総合的に『ヘロン』はレコード盤の上だからこそ成立した、孤高の録音芸術作品なんですね。