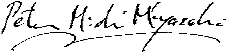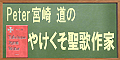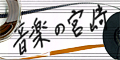Powerd by
sogaku.com
Peter宮崎 道のやけくそ聖歌作家:聖歌集エッセイ #15
第196番「聖霊くだりて(VENI CREATOR)」(Jun.15 2022)
「スケールは主張する」
ペンテコステ(聖霊降臨日)の定番聖歌
日本では梅雨に入ろうかといった季節に当たることの多いペンテコステ。幼い頃からクリスマス、イースター、ペンテコステのキリスト教会三大祝祭日(?!)は家族そろって礼拝に参加したものですが、そういった日の礼拝は2時間超えのため「忍耐」を養いました。小学校の朝礼に於ける校長の話なんて、短いモンでしたよ!
クリスマスには盛り沢山の定番クリスマス・ソング、イースターには華やかな定番イースター聖歌が幾つもあり、それらは歌わなくとも「聞く」だけでも楽しいものですが、ペンテコステでは(私の記憶では)定番曲が1つぐらいしかありませんでした。その曲はグレゴリオ聖歌で小節線がないヤツ。決まったビートがない曲はホントにイヤ!それが「VENI CREATOR SPIRITUS」として世界的に知られる曲でした。古今聖歌集では276番「みたまよくだりて(ながつくりましし)」でした。
その昔は「讃美歌」にはこの聖歌は収録されておらず(後に「讃美歌21」に339番「来たれ聖霊よ」として収録)、聖公会の礼拝で初めて知りました。ところがこの聖歌、一度メロディーを覚えてしまうと歌詞を見ただけで口をついて出てくる不思議なキャッチーさがありました。年に一回だけしか歌わないのに、3年もするともう楽譜は必要ありませんでした。
増補版'95には「来ませ来ませ」と、第9番「かみのかたちに」(羅運栄・作)の2つの“韓流聖歌”が収録されました。ところが両方ともマイナー調でやたら重厚。2006年発行の「日本聖公会 聖歌集」では韓流聖歌は数多く収録されていますが、特にこの2曲の“お先真っ暗感”は突出しています。そういった作風にも関わらず、この2曲の楽曲的な完成度の高さには舌を巻くものがありました。選び抜かれたであろうメロディーは研ぎ澄まされて高いエネルギーを有しており、ついでに構造的には伝統的な欧米の聖歌のスタイルを踏襲して取っ付きやすいのがポイントでした。
モード8
グレゴリオ聖歌はハーモニーを伴わない、純粋に1本のメロディー・ラインをユニゾンで歌う音楽であり、必ず決められた音域内(大体が1オクターヴ以内)で作曲するという決まりがあったとか。そこでまず基本型としてドリア、フリギア、リディア、ミクソリディアという4つの「教会旋法(モード)」と呼ばれる音階(スケール)を設け、使用音域を制定し、それぞれに“歌い終わりの音”を決めました。
興味深いのは4つのモード(スケール)を設定したことで作りやすくなったでしょうが、他の色々な決め事が災いして楽曲的なアイディアがすぐに底を尽く事を懸念した様子。そこでスケールの使い方のバリエーションを各1種類ずつ追加し、“ヒポ”を名称の前に付けた新たな4モードが追加され、西暦9世紀ごろには教会旋法の全8モードが出揃いました。
作曲とはいえ、もしかしたら即興の「鼻歌」だったかもしれませんが、ネウマ譜に書き記せた曲だけが後世に遺されました。グレゴリオ聖歌の時代には長調や短調といった概念がまだ確立していなかったとされ、故に教会旋法という明確な決まり事があったことによって現代に於いても音楽的な整合性が保たれています。
この「VENI CREATOR SPIRITUS」ですが、モード8の旋法、別名“ヒポミクソリディア”で書かれています。これは現在も使われている第7旋法“ミクソリディア”と同じ、現在でいうトコロのト長調のスケールでファ(F)にシャープが付かない形ですから、ミステリアスでありながらどこか明るいムードがあります。同じスケールであってもミクソリディアとヒポミクソリディアの使用法には明確な違いがあったみたいなんですが、どうも時代を経るにつれて作曲者たちがどんどん型を破っていってしまったようで、ヒポミクソリディアは現在では有名無実です。
尚、トーナリティー(長調とか短調とか)の元祖となる旋法は8つの中にはなく、後年に追加されました(イオニアンとエオリアン)。作者と目されるラバヌス・マウルス・マグネンティウスは9世紀頃を生きた司祭なので、この聖歌はまだ8モードだった時代に生まれたのでしょう。あくまで比較論ですが、8つのモードの中で第7〜第8旋法(ミクソリディア系)は明るいムードを持っていたため、当時としては出来うる限りの精一杯の「とにかく明かるい曲」を作ったんじゃないでしょうか。
とはいえ、この歌が現代に於いて「聖霊によって覚醒した十二使徒。世界を救え!ハレルヤ無敵集団、いざ出動!」といった感じではありませんよね。その無敵使徒たちの殉教の様を知っていると、彼らの(決して明るくない)未来を暗示しているようにも捉えられてしまいそうです。近代になって付けられた和声は、この旋律に対して可能な限りポジティヴで美しい響きを探った結果だと思うのですが、逆にミクソリディアン・スケールのメロディーが持つ現実離れしたムードを強調しています。
喜び踊れ!
五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして、炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると、一同は聖霊に満たされ、“霊”が語らせるままに、ほかの国々の言葉で話しだした。(新共同訳「使徒言行録」:二章一節〜四節)
そもそも新約聖書に於ける、この聖霊降臨日の記述は、その表現からして既にミステリーであり、「ヨハネの黙示録」と同じく(預言者に替わるエヴァンゲリストによる)新しい文学的表現の開花を感じさせ、如何に「現実離れした出来事が起きたンよ!」と伝えたかったかが判ろうというものです。別の表現もあったでしょうが、真っ赤なベロに見えたんでしょうね。熱溶解した鉄が注がれる…では地獄の責め苦ですしね。火の玉がアタマの上にとどまった…ですと、ひとだまですか?と使徒の妖怪憑依説が出来てしまいそうですしね。
その様子は現実離れしていながら、その直後“自動翻訳機能”をプラグインされた使徒たちが異国の言語で語り始めます。これは使徒たちからすれば、我が身に起きた「奇跡」の実感であり、それは神を証するべき「ギフト」であり、途方もない驚きと喜びに違いありません。何しろ、学んでもいない語学が瞬時に身に付くなんて、誰もが欲しい奇跡ですよね!バベルを帳消しにする奇跡ですからね。となると…、やっぱり踊り出したくなるでしょう?
そこで私は、Elpisのペンテコステ・コンサートにてこの聖歌を演奏する際、ダンス・アレンジする方法を考えました。一定のビートにキッチリと乗せるには、決まった拍数で小節線が引けなければなりません。この聖歌は文字数(音符の数)が11 - 10 -11 -10と決まっていて一定の拍子に乗せやすい構成で、助かりました。
しかし1000年以上も生きながらえてきたこの音楽、その旋律が内包する主張の強さは尋常ではありませんでした。どのようにアレンジしても原曲のイメージが崩れません。サスガ、20世紀半ばになってジャズに革命をもたらした“モード”は、そのスケール自体に確固たる主張があり、アレンジしても表情が変わらないんですね。ハーモニーを簡素化してEDMに仕上げても、匂い立つミステリアスなムードは健在です。
主張するスケール(音律)
「VENI CREATOR SPIRITUS」に限らず、グレゴリオ聖歌からの聖歌は1曲1曲が独自のムードを持っています。そもそも“ドレミファソラシド”のスケール(音律)で作られていないから、現代に於いては異質に感じます。かつて、どこかの誰かが言っていました、「グレゴリオ聖歌は人間の感情を排除し、天国をあらわそうとした音楽だ」…ホンマでっか?
例えばこの聖歌が作られたとされる9世紀頃、同じ“ミクソリディアン・スケール”で作られた曲は他にも沢山あったでしょう。その時、この聖歌は現在のような独自性を持っていたとは、私は思えません。何故なら、当時の教会音楽では「異質」ではなかったからです。
スケールによって長調/短調という概念が生まれ、世界的に“ドレミファソラシド”(長調)と“ドレミ(b)ファソラ(b)シ(b)ド”(短調)がポピュラー音楽では固定化されている現在に於いて、教会旋法モード7〜8のミクソリディアン・スケール(ドレミファソラシ(b)ド)はビミョーに違うので異質に感じてしまうだけなんでしょう。
しかしジャズの世界に居る人々にとって、ミソクソディアンは基礎中の基礎。異質でもなんでもないワケです。ジャズは和声を進化せた後、“次の音楽”を目指してスケールを進化させました。演奏中でありながら、ずーっと作曲中の“ゾーン”に入るジャズのインプロヴィゼーション…そのスケールの有り様は紡ぎ出す音楽のキャラクターを特徴づける上で重要な要素なので、もはや1オクターヴ=8分割に留まらない多様なスケールが考案され、日々アップデートされ続けています。
中には故アラン・ホールズワース(g)のように、数学を用いて考案した独自のスケールで、とても個性的な(変態的ともいわれた)音楽を奏でたジャズ人も多くいます。つまりジャズ人は既に知っていたのですよ、ハーモニーではなく、サウンドではなく、何より「スケールこそが主張する」、音楽はスケールにこそオリジナリティーがあるのだと。
スケールにオリジナリティーがあるということはつまり、メロディーこそが音楽のオリジナリティーを有するという認識で、そうなりますと日本の「著作権」ではメロディーのみが登録を許されているのも納得です。もっとも作曲家が歌メロだけ作った後、編曲者がイントロや間奏に新たにメロディーを作って楽曲を構築したとしても、何故かそれにらは「著作権」は適用されないってのは理不尽ですね。現在はどうなっているんでしょ?
ヒポ検証:遊んでみた
ちょっと遊んでみることにしました。この聖歌を極めてシンプルな4つのメジャー・コードで、明るくラフに演奏してみます。難しい事を何も考えてない演奏です。実際にやってみますと、この聖歌はやはりモード8、“ヒポミクソリディアン”で書かれていたのが判ります。尚、ヒポ(Hypo)とは“低い”という意味らしいです。
原譜はBb《メロディー=Fミクソリディア》で書かれています。これを判りやすいように2度アゲて、C《メロディー=Gミクソリディア》にしました。結局、旋律に対して5度下の伴奏が付けられていることになるんですね。なるほど、実態は“ヒポ”(低い)なワケだ…なんてこたぁ〜ないか。
Fのメロディーラインだと思っていたら、実はBbだった…そういう“復調”のような、どっちつかずの浮いたようなメロディーラインになっているからこそ、現代の誰かが思わず「人間の感情を排除し、天国をあらわそうとした音楽」だと言いたくなっちゃったのでしょう。今なら判る気もします。
実は聖歌421番「平和の鐘が広島から流れる」も、同じようにミクソリディアン・スケールのメロディーを持ち、メロに対して5度下の調で伴奏するというフォームを持っています。ですが421番は現代の曲ですし、教会モードの使い方は厳格ではないので、結果として全く異なる印象になっているのは注目すべきです。
さいごに
というわけで未来永劫、ペンテコステといえば「VENI CREATOR SPIRITUS」は外せないでしょう。年に一回、この聖歌を歌う時は、ただ“ミクソリディアン・スケール”の曲を歌っているんだと思いましょう。そしてそれは廃れてしまったいにしえの音楽要素ではなく、現在のジャズ界隈ではバリバリの現役です。20世紀に劇的に変容した西洋音楽史の遺産を未来に繋いだのはジャズをはじめとするポピュラー・ミュージックだったのだと考えたら、「VENI CREATOR SPIRITUS」を歌うのも「ノルウェーの森」(ビートルズ)を歌うのも、メンタリティーは何ら変わらない気もしますよ。