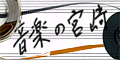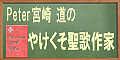『VAMP - Original Motion Picture Soundtrack』- Liner Notes
目次

『映画「VAMP」の音楽を作る 』 by 宮﨑 道
第1回: ドラキュライズム~父との対話
小中和哉監督のホラー映画「VAMP」の音楽を製作したのは、2018年8月末~10月初旬の間。その間、私は苛烈を極めた偏頭痛に苦しみ、半ば引きこもり状態となり、台風による強風で家の屋根が飛び、地元の全公共交通機関がストップしてMA(音声の最終ダビング)に行くのすら不可能に…といったバッド・シチュエーションが畳みかけた。
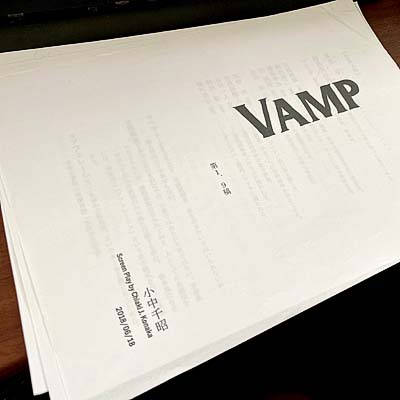
急激な体調不良から、何度も降板を考えた。だが高校時代、小中和哉監督のSF特撮8mm自主映画「地球に落ちてきたくま」をリアルタイムで観て影響を受けた私としては、小中監督と映画を作る経験は得難いもの…。だが実は、監督のお兄様である小中千昭さんが台本上に描き出した映画の内容が“吸血鬼の物語”であった事が何より魅力だった。私が吸血鬼にこだわりがあった背景には、亡き父の存在が大きく関係している。
作曲家であった父・宮崎尚志は大林宣彦監督の処女作「EMOTION:伝説の午後 いつかみたドラキュラ」、市川染五郎(現・二代目 松本白鸚)主演の舞台「ドラキュラ・その愛」の音楽を手がけているが、どちらも通常の仕事を超えた力の入れようを見せた。実は父はドラキュラ映画が大好きで、私はそのせいでパイプオルガンやチェンバロといった古楽器が嫌いになるというトラウマを長い間抱えることになったのだが…。ある日、私は父に「なんでそんなに吸血鬼が好きなの?」と質問すると、父曰く…
「つまり西洋キリスト教信仰にある“永遠の命”の概念の逆説的発想なんだよ、ドラキュラって。永遠の命を手に入れたけど、結局、最も“死”を拒絶し恐れているのは、他ならないドラキュラ自身なんだ。だから何が何でも生き続けなきゃならないってガンジガラメになっててさ。そんなドラキュラの存在って、如何にして人は幸せに生きるのかって問いかけてくると思わないか?」(宮﨑尚志・談)
私は、それを興味深く聞いた。そして父はそれを「ドラキュライズム」と称した。
更に2003年、死の床にあった父が何度も「生かされる喜びって言うけど、生かされる苦しみってのもあるんだな」と口にするのを耳にした。ここにひとつの答えがあった。吸血鬼は「永遠の命を得た喜び」と「永遠に生かされる苦しみ」という絶対的な矛盾を抱え、それを統合できず、果てしなく彷徨える魂なのだ。それは人間を超越しても尚、極めて人間的であるという点で、激しく魅了されるものを発見した。ある意味、吸血鬼そのものがひとつの「美学」なのだ。だからこそ吸血鬼モノという題材を音楽で表現することは、精神的なハードルが高い。美学だから。だがハードルが高ければ高いほど、そこには「まだ知らない自分」に会えるチャンスがある。
第2回: 偏頭痛再発~降板するか否か?

「VAMP」は音楽ナシの状態で既に映像作品として、又、和製の吸血鬼物語として面白く、全編80分間に渡って観る者を画面の前に縛り付けるだけの力があった。しかもこの映画の前半には小中監督自身が“何かを越えてきた”感じがあった。同じダーク・ファンタジーといっても監督の前作『赤々煉恋』とは印象が全く異なり、血の匂いのするディープ&カオスな世界が形成されていた。
特に主演の中丸シオンさんと高橋真悠さんの2人の熱演には目を奪われた。だから音楽は、画面の邪魔をしないよう必要最小限にとどめるべきだと私は考えたが、小中監督は「音楽にいっぱい助けてもらわないと!」と真逆のことを主張、ほぼ全編に渡る50弱の箇所に細かく音楽を指定した。当初、監督の意図するところは理解できなかった。最初で最後となった(実際に顔を合わせての)音楽打ち合わせの段階では、映画『コヤニスカッティ』を参考に、ミニマル・ミュージックやポスト・クラシカルなどの硬質で冷たいムードでいこう…と合意していたものの、実際のところは、「はて、どうしようか?」。なので見切り発車状態で作曲を開始した。
真っ先に手を付けたのが、本編中盤のラヴ・シーン(Track10「愛のテーマ」)である。音楽が絶対必要なシーンであり、事前にメインの主題となるメロディーを置くという“論理的な計画”をしていたためだ。このシーンに対して私から3曲を提示、小中監督がそのうちの1つを選んでメインテーマが決定した。そしてここから本格的な作業に入ることになる。当の私はワクワクしていた。テーマが決まって落ち着いたせいで、全体のイメージが更に大きく膨張中だったからだ。
ところがタイミング悪く、私の持病である“重度の季節性偏頭痛”が再発、発症から数日で症状はピークに達した。その痛みは苛烈を極め、慢性的な寝不足となり、急速に体力が奪われていった。1日のうちで痛みのない快適な時間は数時間、それも日を追う毎に少なくなっていき、次第に症状のピークから回復する兆しすら全く見えなくなった。お先真っ暗。何故この大切な時に…と悔やんだ。
作業が遅々として進まなくなった分、小中監督とは連日、短時間ながら電話で話し合った。刻々と変わる我が身の病状を伝え、それでもこの作品を一緒にやろう、スケジュールも余裕があるから…と励まして下さる小中監督の寛大さに毎度も救われた気がした。本音を言うと今回の偏頭痛はひど過ぎて、降板を考えたのも一度や二度ではなかった。
顔を突き合わせての打ち合わせはもう出来ないかもしれないと考え、1曲出来上がっては所定の本編シーンに合わせたデモ・ムービーを作成し、動画投稿サイトを介して監督にチェックしてもらう方法で作業を進めることに。その過程の中で監督と私の間には必ずといってよいほど、微妙なイメージのズレが生じた。たとえ音楽的には問題なかったとしても、監督は決して首を縦に振らなかった…鬼か?!
第3回: 役者のマインド
当の私はまだ、この映画は「音楽がなくとも成立する」と考えており、反対に監督は全音楽に対しても明確なイメージを持った上で「音楽がなければ成立しない」と考えていた。私は監督の意図するところを懸命に探りながらも、自分が感じる「そこに付くべき音楽」を作ろうとしていた。が、我に返ってみると、そもそも監督の意図するところが判っていないなら本末転倒なのだ。共に1つの目標に向かってゴールを目指さなければ、特にハードルの高い“吸血鬼モノ”である「VAMP」は、たとえ《完成》したとしても、《成立》はしないのだ。
だからこの際、自己を一旦放り出して、監督の演出に従って「役者が演技をするように作曲する」ことで、監督の求めているツボの在り処を探る方法に転じた。そのやり方は、私にとって新しい挑戦だった。その時を境に、私のマインドは“役者”になった。
本来、実写映画の製作に於いて、音楽は一番最後にプラスされる要素で、しかも完成する映画に対して大きな影響力を持つ。映画音楽の作曲家は、観客席に近い位置から音楽を付けていく…つまり作る側と観る側とを繋ぐ役割を、かなりクールな観点で担うものでもある。
しかし「役者が演技をするように作曲する」となると、作曲家は観客席ではなくスクリーンの中に飛び込み、我を忘れて役者と共演するイメージで作曲することになる。それは作曲のスタンスにも、大きな精神的な違いをもたらす。なにしろシナリオに書かれていない透明な役を、監督の演出に沿って演じるのだ。意識の上では「自分」は居なくなり、論理的な計画性もなくなる。
ところが面白いことに役になりきるほど私は没入し、ポテンシャルを発揮できるゾーンに到達して、毎日短時間ながら「生かされる苦しみ」を追求した。小中監督の注文は依然として減ることはなかったが、向かうべき共有イメージへ足並みは揃ってきて、迷うことなく作業は進むようになり、同時に「VAMP」の音楽は急激に冷えていった(深部体温30.0℃以下のタッチ)。
とにかく毎日、激しすぎる頭痛に苦しめられていたので、「生」への渇望は常に私の手の中にあった。映画の冷たいタッチの中で主人公が「生」を願うシーンには、より深く共感していった。
そしてある日、本編のラストカットに付けられた音楽を聞いた小中監督は「泣きました…」と言った。この時、ようやく監督と私には共有イメージが確立できたのだと思った。毎度のことだが、監督の頬を感涙で濡らす爽快感は映画音楽作曲の醍醐味である。何しろ、監督は作品を隅々まで知り尽くし、完成予想図を見据えている唯一の人であり、そんな人が泣く…ということは、もう勘弁してくれー…じゃなく、完成図を超える何か感動的なケミストリーが起きたという事だからだ。
しかし監督は泣いても音楽へのこだわりは依然として強く、要望は更に細かくなった。それもそのはず、監督には「新しい完成形」が既に見えていて、まっしぐらに向かっていたのだ。このシーンではこのパートを低音で奏でて欲しい、このシーンではメロディーを“女性の歌う声”にしてほしい…など、音楽の中に踏み込む壮絶な音楽演出をしはじめた。“女性の歌声”に関しては我が妻に依頼し、「聞いている側が不安になる」ような、全然上手く歌ってない歌声を入れてもらった。これがスタッフの間で好評、改めて映画の音楽は面白いと思った…我が妻は大いに不服のようだが。
第4回: 私、呪われてる?!
MAまで残り1週間あまり。全曲が揃いそうな見通しが立った頃、監督から一報が入った。「エンドタイトルロールに流れるテーマ曲のフルバージョンを追加で作ってくれませんか?映画の主題歌が結局、決まらなかったので」。お安いご用です…とは簡単に言えない身体の状態ながらも、その申し出を快諾した。私は元々、映画の「主題歌」について、ジェームズ・ボンドやディズニー映画を除けば、音楽的な意味では「主題」になってない作品が多くて残念に思っていたので、主題歌が決まらなかったことで幸運なことに「VAMP」は徹頭徹尾、音楽によるイメージの統一が図れ、映画らしいエンディングを“音楽によって作る”ことが出来る。
全曲が完成し、残るセルフ・ミックスダウン作業には2日間用意していた。だが運悪く、非常に強い台風24号の到来による気圧低下でひどい目眩の中、ミックスするスタジオへ向かうも、1日目(9/29)は短時間でアウトラインを整える程度、自分で十分に納得のいく仕上がりまで追い込めなかった。翌2日目(9/30)は台風が直撃、しかもミックス・スタジオの地域は停電中で使用不可。仕方なく自宅で手早くミックス・マスターを完了させ、翌日の東京でのMAに備えた。

一夜明けた台風一過の早朝(10/1)、自宅の屋根瓦が強風で飛び、近隣の家屋にも被害を与えていた。依然治まらない頭痛をおしての諸々の手続きと、散乱した屋根の破片の回収に追われた。自宅ガレージに停めてあった車にも屋根が落下し、フロントガラスは破損していた。しかも更なるバッド・ニュース…。地元から東京へと繋がる2つの電車は終日運休となり、高速道路も通行止め。一般道もあちこちで浸水や倒木などで交通規制されていた。どうあがいてもMA初日に東京のスタジオへ行く道は断たれてしまった。八方塞がりとはこのことだ、踏んだり蹴ったりだ、陸の孤島だ。この仕事で私は呪われているんじゃないか?と真剣に思った。結局、小中監督と話して本MAまで4日間の猶予があることを知り、その間に自身にかかった呪い(?!)を1つずつ片付けていくことになった。
当時の私にとって何よりの問題と障害は、いっこうに治まらない偏頭痛の激痛と、それに伴う慢性的な睡眠不足だった。ところが地元の耳鼻科医が効果的な治療法を知っており、その治療を受けて奇跡的に改善、本MAの日には東京へ出向くことも可能となり、発作的にやってくる頭痛もなくなった。そしてMAは滞り無く終わるかと思われた。
第5回: 呪い、再び

不可解な事はまた起きた。2曲の音楽トラックが、無残にも音痴なアンサンブルに…複数のパートの調律が全く合っていなかったのだ。更にもう1曲には、不気味な電気的ノイズが乗っていた。いずれもミックス時には全く気づかなかったことだ。たまたま他の問題もあってその日のMAは完了せず、後日に改めて行うことになったため、これ幸いと、私も後日、問題の音楽の修正版を作り、入れ替えてもらう事で解決した
帰宅してその日のうちにミックスをやりなおしつつ原因を探ったが、音痴なアンサンブルになった要因だけは不明だった。音楽製作で使用したコンピューターのソフトウェアに、その時にだけ不具合が生じたとしか考えられない、起こるはずのない事が起きていた。
関係者向けの試写会で改めて本編を観た際、私は音楽のサウンドに“広がり”が不足している事に気づいた。音楽が左右に広がらず、常にセンターに寄り気味。自分のミックス作業での追い込みが足りなかったは否めない。同時に(前々から判っていたのだが)長年愛用してきた音楽製作システムの限界を感じた。先述の音痴アンサンブルも通常使用なら起こらない事例であり、このシステムが疲弊しているのは間違いなかった。私は愛用してきたシステム(手に馴染んだ道具)の使いやすさを優先し、新しいものから敢えて目を背けていた。でも、このままではもう無理かもしれない…私はすぐに考えを改めて、音楽製作システムを全面リニューアルすることを決意する。
ホラー映画の製作に関わると、身の上に不可解な事が起きるという言い伝えがあるが、これだけいっぺんに重なると、それってホントかも…という気にもなる。だが30年間悩まされてきた偏頭痛の治療法に出会えたり、積年の懸案事項でもあった音楽製作システムの刷新に踏み切ったりと、好転するきっかけにもなったので、悪いことばかりではなかった。呪いにも自然界のバランスのようなルールがあるのかもしれない。
第6回: 知らない自分を知る

映画が無事に完成した後、小中和哉監督に質問した。何故、執拗なまでに細部に渡る微調整を要求し続けたのか?に答えて曰く、「普通、誰もそんなことやってくれませんよ。あなたならなら絶対やってくれるって信じてましたから。実際、私にトコトン付き合ってくれたじゃないですか。アップしてくれる音楽付きの動画をチェックするのが毎回楽しみで、本当にワクワクしましたよ」。…たとえそれがお世辞でも、そうでなくても嬉しい。それは「監督に気に入られた」という様なものではなく、「誰かに伝えたい」という同じ志を1つに集約するためにコミュニケーションを密に計ったという、実は単純な話だ。
自分の音楽の出来はさておいて、映像と合わせた感じは上々で、満足のいくものだった。音楽が芝居の邪魔をしない、映像より先回りしてドラマの展開を説明しない、それでいてちゃんと作品をカラーリングしている。南蛮渡来の吸血鬼モノでありながら現代日本文化の根幹を担うセンスである“萌え”をも匂わせつつ、内容は極めてシリアスである…全体のバランスはとても良いと思った。
だがその後、約8ヶ月間、私自身は「VAMP」の音楽を一度も聞き返すことはなかった。敢えて避けていた。その冷たく重い悲苦のムードは、当時の偏頭痛の激痛を呼び覚ますトリガーになり得ると危機感を抱いていたからだ。
一般公開を間近に控えた今(注:2019年8月16日記述)、改めて聞き直してみると、そこにはちょっと知らない格好をした「自分」が居ることに気づいた。いかにも日本で育った顔をした、素の自分である。「演じる作曲」を試み、より遠くへ向かったつもりが、より自分自身に近づいていた…のような。「無限に広がるとは遠ざかることであり、遠ざかるとは(近くへ)返ってくることである」と、老子が『道徳経』に著したが如しである。
これがあるから映画のための作曲は楽しい。無論、その音楽は完璧ではなく改善点だらけ。己の至らなさを後世にまで残す黒歴史である。それでも尚、そこに偽りのない自己…それまでと少々異なる自己を発見できたなら、私はそれを芸術と呼んで構わないと思う。芸術作品は(たとえ作者の黒歴史であっても!!)残すべきものだ。何故なら作者の素顔が刻印されているからである。即ち、作者の顔(生き様)が見えない作品は、芸術ではないと私は考える。
しかし、やはりサウンドの広がりに関しては依然として問題が残ったまま。「VAMP」オリジナル・サウンドトラックは、今すぐには発表する予定はないが、いずれこの音源をキチンとミックスして納得いくかたちにしておきたい…いつになるやら。
第7回: 最終回

2019年8月23日から数週間に渡って、映画「VAMP」はキネカ大森(東京)、シネマスコーレ(名古屋)、シアターセブン(大阪)の3都市3館で開催されるキングレコード主催「第6回・夏のホラー秘宝まつり2019」で一般公開される。2018年11月に完成してから10ヶ月経って、ようやく「誰でも観られる」ことになる。この間、作品はストックされていたワケではなく、海外の映画祭で既に多くの人々の目に触れている。このように映画は国境を越え、ひとたび公開されれば映画史リストに連なる。だから“映画人”は誰しも常に真剣だ。レジェンドの黒澤明や小津安二郎らと同じ1つの大きなツリーに連なるのだから。なのでたとえ儲からなくとも、取り組む姿勢は常に全力だ。私はそういう映画人の姿勢に常に感化されている。猫背を真っ直ぐ伸ばされる思いがする。それは表現の方法が異なるせいだろうか…。
追記: 生きた証 (2023年7月7日・記)
尚、石田信之さん(TV「ミラーマン」の鏡 京太郎役で知られる)は2019年6月13日、この映画の公開を観届けることなく亡くなった。享年68歳。長いガン闘病の中でもご自身は出演作の1つ1つを全力で取り組み、どんな役でも決して悔いを残さない心構えだったそうだ。『VAMP』が遺作となった。私は“ミラーマン”にお会いしたかったが叶わなかった。
2022年7月11日には主演の中丸シオンさんが逝去。享年38歳。5年間もの間、闘病していたとは『VAMP』の撮影時には誰も知らなかったそうだ。『VAMP』の打ち上げで一度だけシオンさんとお会いしたのは、今も私の大切な思い出となっている。この映画はシオンさんが自らの“生きた証”として取り組んだに違いないと、勝手ながら思っている。
中丸シオンさんの逝去を聞き、長年手付かずのままだったオリジナル・サウンドトラック盤の製作を決意した。シオンさんの生きた証が『VAMP』に立てられているなら、生前の彼女が痛く気に入っていたこの映画音楽を完成させなければ、私自身の生きた証は中途半端になってしまう…と思えたのである。全曲を見直し、曲によっては演奏しなおしてリミックスするのに3ヶ月間かかった。ミニマル・ミュージックに感化された冷たいこの音楽は、一寸の狂いなく小中和哉監督と最初に話し合ったイメージの具体化に他ならない。シオンさんと石田信之さんは、完成したサントラ盤を聞いてくれているだろうか?
Base Designed by
CSS.Design Sample